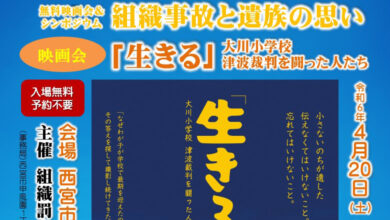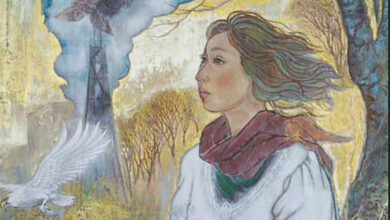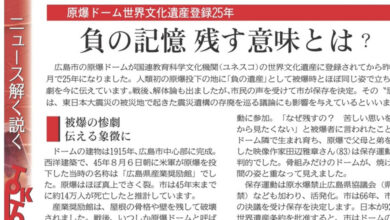いま、沖縄から-① 労働/生きる•いのち
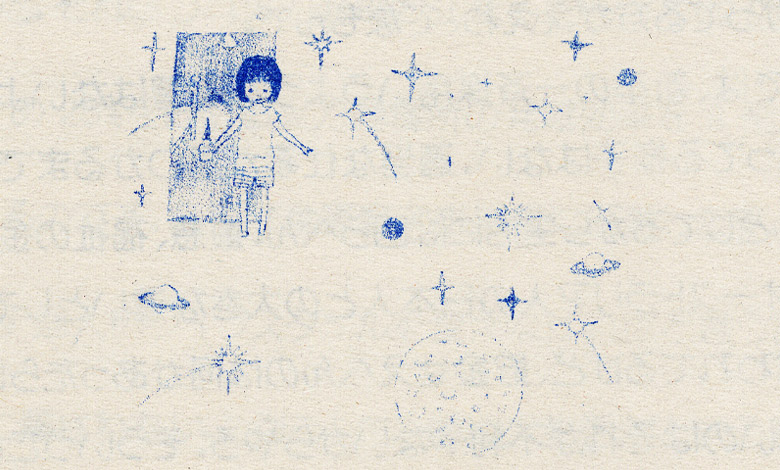
平井真人
はじめて「お目」にかかるのに堅苦しいタイトルですみません。僕は神戸市北区淡河に生れ、幼少より大阪で育ち、沖縄に移り住んで30年になります。生活は沖縄の伝統的な型染め「びんがた」を基にした現代的な染めの作品制作と、沖縄の芸術大学で非常勤講師の勤めで収入を得ています。実は4年前、僕が沖縄県立芸術大学に常勤的に勤めている時に健康保険、厚生年金、雇用保険の適用を申し出ました。すると突然、芸術大学は「予算が無い」「カリキュラムを変更する」等の理由を付けて、2年間で収入を4分の1に激減したのです。その問題をきっかけに沖縄の6大学の非常勤講師たち約20名でユニオンを立ち上げ、各大学の労働環境の改善に取り組むようになりました。
僕のユニオン活動(労働組合)は染色作品を制作する表現とは一見無関係のようですが、労働は個人の生き方(表現)であり、活動はいきる権利を確認するコミュニケーションの場なのだと、今になって気付きました。とりわけ、僕自身の染色表現において布は人間そのもの、表現方法は人間の多様な生き方だと、すなわち労働であると思うのです。
個人では困難な大学との交渉や情報開示など、ユニオンの要求には大学は誠実に対応しなければなりません。交渉をした事で、それまで無かった交通費の支給や有給休暇の適用が可能になりました。それらは一般の会社では考えられない事で又、大学の閉鎖性の内実も明らかになって来ました。
巷では現在、昨年からのアメリカ金融危機で非正規労働者の「派遣切り」は大問題になっています。しかし、それは新しい問題ではなく非常勤講師は以前から使用者(大学)の都合で雇われ、悪くなったら突然切られる「労働の調整弁」と扱われて来ました。それらは今までの女性の働き方が男性に広がっただけの事でもあるのです。
非常勤講師の収入は週1回1コマ授業(90分×前•後期各15回)で年収約30万円です。毎日、幾つかの大学を掛け持ちして授業を行い大半が年収200万円以下。いわゆる、現在言われている「ワーキングプアー」なのです。
いま、沖縄での大問題はこの4月から琉球大学が外国語授業半減計画を強行します。教学上許されないことで、また国際化を叫ばれている中で考えられないことです。その削減分(2500万円)はほとんど約50名の非常勤講師が受け持っている授業で1人平均50万円の減収となるのです。大学は具体的な授業計画を示せないカリキュラム変更を『改善』とたいぎにしていますが、目的は国からの交付金目当ての経費削減達成度です。
最も立場の弱い非常勤講師を狙ったものです。大学は非常勤講師を雇用している認識は全くなく、経費としての「もの」扱いが証明されました。人間の権利、とりわけ大学の主役である学生の教育権やサポートする教員の生活権を真剣に考えない大学で人間教育の第一義「いのち」が共有できないのです。どうして、沖縄でこんな事態になるのか?どこに、波及するのか?皆さんも一緒に考えて欲しいと思います。
~ヒカン桜満開のオキナワより~ (ひらい•まさと/染色家•大学非常勤講師