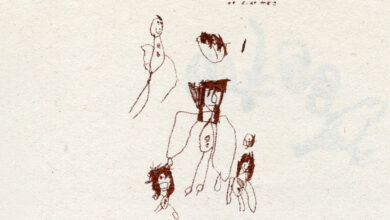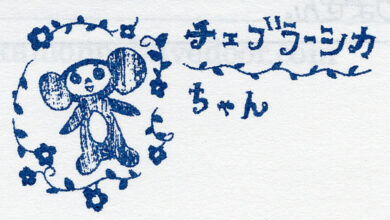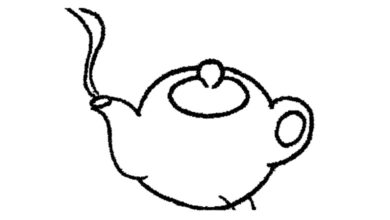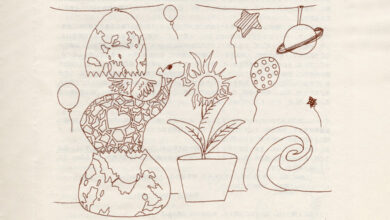オーストラリアから④ 個人主義と「全体主義」
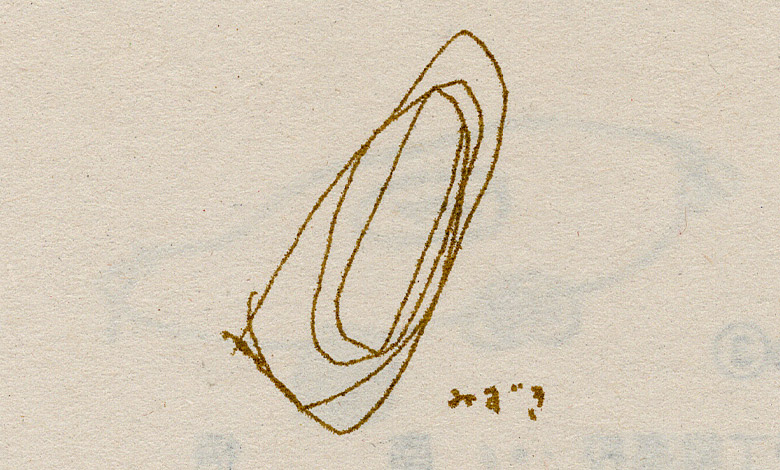
堀蓮慈
前号でちょっと触れたエピクロスは「哲学とは幸福になるための方法である」て言うてる。それは宗教にしても同じことで、戦後日本みたいに、宗教や哲学言う人生の基本的価値観にかかわることをないがしろにして、ひたすら経済的安定を求めるような浅薄な人生観では、結局、大勢に流されて、ほんまの幸福を見失いそうな気がする。
こっちで漱石に関する本読んで、「彼は西洋の個人主義と日本の全体主義のズレを自分自身の中に感じていた」いうような文章に出会うた。2つの異なった原理の狭間で葛藤するんは、多くの近代日本の知識人に共通する宿命やったわけやが、漱石はイギリスに留学したから、よけい身にしみたんかもしれんな。
「全体主義」いう表現は穏やかやない、て感じる人もおるやろ。政治用語としてはファシズムのことやからな。日本は曲がりなりにも民主制度があるからファシズムではない、て一応は言えるけど、たとえばワイマール憲法法下でナチスが政権取った時、制度より先に人々の頭の中がファシズム化してたはずで、民主主義が内面化してない限り、制度は簡単に形骸化し、崩れ去り得る。
ぼくの考えるファシストの定義は、「みんな同じ」であることを快適に感じ、「みんなと違う」者を排除する人間や。自ら積極的に排除はせんでも、少数意見を主張する勇気を持たん者は結局その同調者となる。•••これって、ほとんどの日本人にあてはまるんやないか?
「空気を読めへん」ことに対する非難もそれと同根で、その場の空気を乱さへんことに価値をおいたら、おかしな方向に流された時にも歯止めをかけられへん。「時代の空気」に流されてあの無謀な戦争につっこんでいった歴史をくり返さんとも限らん。
オーストラリアは個人主義が当然の前提で、周囲の人間にどう見られるか、いうんは二次的なことのようや。
若い女の子も平気で太いし、裸足で町を歩いてる人間もおる。民族的な性格の差は、農耕社会と牧畜社会の差に由来する。いう説には一定うなずけるけど、日本かていつまでも農耕社会やないんやから、もっと個人主義的になる方が自然やと思うがな。
最近ネットで読んだ記事によると、特に学校で、周囲から浮かへんことにものすごう神経を使う。いう傾向が強まっているそうな。浮いてしもたら毎日が苦痛でたまらんからやろが、それは「周囲がどない思おうが自分は自分や」て言えるような「自分」を支えるよりどころがないために、他者からの評価に依存してしもてる。いうこっちゃ。ここで冒頭の話とつながってくるんやけどな。
最も危険なんが、そのよりどころを国家や民族に求めた場合。一時右翼をやってた雨宮処凛がそのへんの心理を説明してるけど、そういう人間が増えたらファシズム体制は完成する。そないなったら日本からこっちへ逃げてくる人も増えるかもしれへんな。
Sponsored Link