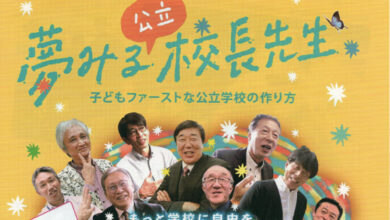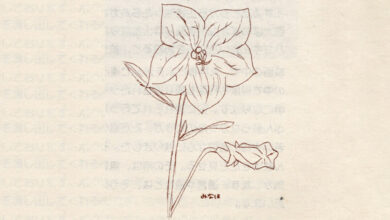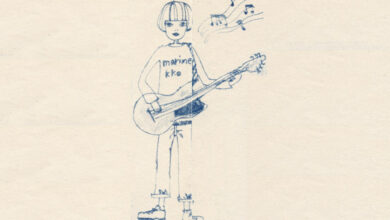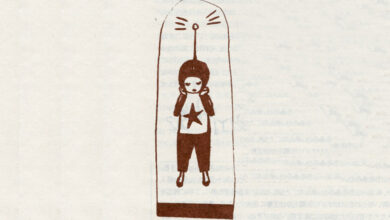脱学校原論③ 要はカネの問題?
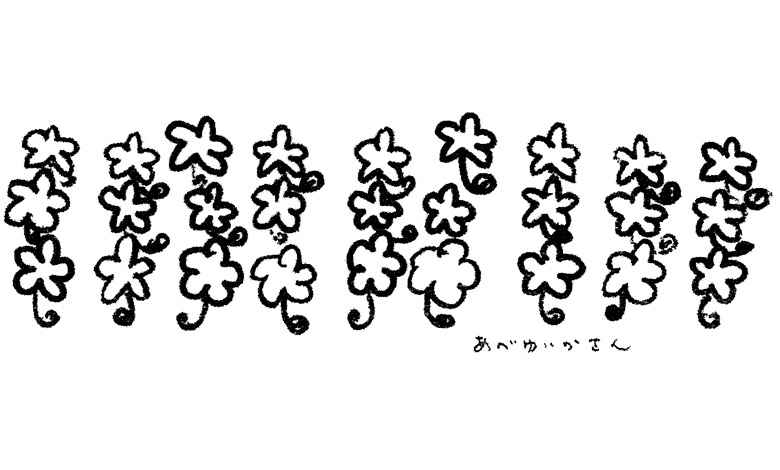
堀蓮慈
軍隊と学校が近代国家の両輪やったんは間違いない。ある人に言わせたら、国家は「学校で魂を奪い、軍隊で命を奪う」んや。日本の場合、学制をしいて20年後に日清戦争に突入しているが、学校を経験してる若者は、兵隊としての訓練が相当やりやすかったはずや。いまだに小学校1年から「前にならえ」いう号令かけてるぐらいやから(あないきっちり並ばせることに何の意味があるか、問い直す人はおらんのか)。
国家の側のそういう狙いに対し、民衆の側は「子どもが将来ええ給料を取るために学校へ行かす」いう形で乗せられてしもた。とは言うても、昔の中国の科挙みたいに、官僚になって栄耀栄華ができる、いうんを目標にしてがり勉した人間は一握りで(今でも東大法学部あたりにおりそうやが)、ほとんどの庶民は「貧困を抜け出してひとかどのもんになりたい」いう気持ちやったんやないかな。そこまで考えずに「回りがみんな行くから」いう理由で行った場合もあるか。いずれにしても近代化途上では、学校に関して国家と民衆の利害がある程度一致した部分もあったんやろな。
封建時代は身分制度ががっちりしてたから、能力があっても出世はできんかった。それと武士には「金の話をするんはみっともない」いう美意識があって、学問するんは主君のため、ひいては天下国家のため、いう大義名分があった。天皇制国家では、何事も最終的には「国のため」やわな。もちろん偽善やけど。ところが戦後は価値観がカネ一本になって、「ええ生活するために勉強する」いうホンネが臆面もなく語られるようになった。ぼくらはそういう環境で教育されてきたんや。ホリエモンが時代の寵児になったんも道理や。
ところが今、「ええ学校」へ行ったからいうて「ええ生活」ができるか、いうたらかなり疑問になってきた。たしかに役人になったら、あるいは大企業に入ったら、給料も高いし安定もしてるけど(大企業の場合、30年後はどないなってるかわからんし、それ以上にリストラ食らう危険もあるが)、それが幸せか?いう問いに対し、イエス、て答えるかどうか。そこで価値観が分かれる。ぼくの考えは、システムに依存するんをやめて自分なりの生き方を選ぶんが幸せへの道、いうこっちゃ。今のところそういう道を選んだ多くの人はフリーターいう形で低収入に甘んじてるけど、今の流れが変わらん限り、いずれ雇用形態も変わらざるを得んのやないか。
最近、大阪の「学校に行かない子と親の会」の「ココナッツ通信」で、「教育問題は労働問題の影のようなもの」いう意見を読んで、なるほど、と納得した。経済全体の話をせずに学校制度だけ論じてもあんまり意味はない。もちろん「人間としての成長」いうことについて論じるなら話は別やが、それは学校なんてもんの枠を超えた大きな話になるなあ。
 脱学校の社会 (現代社会科学叢書)
脱学校の社会 (現代社会科学叢書)
イヴァン•イリッチ(著), 東洋(翻訳), 小澤周三(翻訳) / 東京創元社 / 1977年10月20日
<内容>
現行の学校制度は、学歴偏重社会を生み、いまや社会全体が学校化されるに至っている。公教育の荒廃を根本から見つめなおし、人間的なみずみずしい作用を社会に及ぼす真の自主的な教育の在り方を問い直した問題の書。