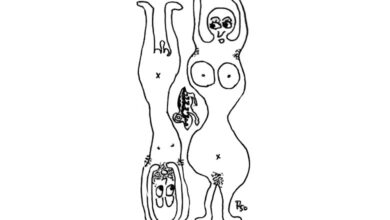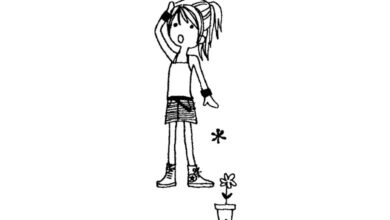神戸新聞社会部

神戸新聞社会部 木村信行
ご無沙汰しております。メールをきっかけに原稿依頼があったので、そのまま手紙形式で書かせてもらうことにしました。
それにしても息の長い活動、ご苦労様です。もう15年になるのですね。石田さんの生きた長さと同じ時間。僕が大学に入学した年です。長いような、短いような。
4月に尼崎のJR脱線事故が起きたとき、僕も高塚事件のことを考えました。1分1秒に追われる高密度社会は、緩和されないどころか、ますます厳しくなっていますよね。僕自身、職業柄もあるのでしょうが、物事をじっくりかんがえる「ゆとり」はほとんどなくなってしまいました。たとえこま切れの時間があったとしても、それは脳を休める時間。経済活動の仕組みが変わらないものだから、「ゆとり」をいくら叫んでも、現実味のない空論になってしまいます。
文部科学省もゆとり教育を撤回しつつあります。国際的なテストで少し順位が落ちたぐらいでヒステリックに盛り上がった世間の「ゆとり」批判を見ていると、僕たちの体に棲みついてしまった化け物とは、一体なんなのかと考えてしまいます。この化け物と向き合うことこそが、高塚事件を考え続けるという態度なのでしょうね。
しばらく前、必要に迫られて永住外国人の地方参政権問題を集中的に勉強したのですが、インターネットの世界で繰り広げられている過激な「反対論」を見ると、ぬくもりや迷い、弱さといった人間の実像に触れようとしないまま、物事を単純化し、いたずらに不安をあおる態度が確実に広がっていると感じます。
感受性の平均値が相当低下しているのではないでしょうか。そこには、新聞を含むメディアの責任が大きく関わっていると思います。記者1人1人はそれなりに悩んでいたとしても、全体としては、単純化、刺激化の追及に終始しています。
衆院選挙が始まりました。小泉さんの政治をメディアは「劇場型政治」と批判するけれど、要はメディアの実態を利用し、世論をまきこむ効果的な手法を取っているだけです。僕たちはこの選挙で、どんな国のあり方を選択するのでしょうか。そもそも、二大政党制を進める小選挙区制度を選んでしまった時点で、多様な考えは淘汰される宿命にあります。この通信が発行されるころには、新しい政権が出来ているのでしょうね。
だらだらと考えていると支離滅裂になりそうなので、この辺で終わりにします。でも、こんな時代だからこそ、所さんたちのように、考え続ける、こだわり続けることの大切さが、森の中に残されたガラス玉のように輝いて見えるのだと思います。
Sponsored Link