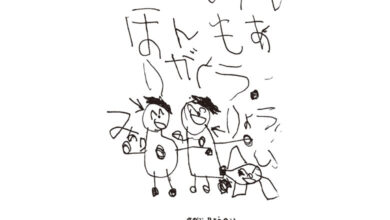30年の時が流れて

ホームスクーリング•ネットひめじ 久貝登美子
私が、30年前に石田僚子さんの門前追悼に初めて参加した時は、つれ合いと共に5歳の娘を連れて三人で参加しました。
鉄製の、見るからに重たそうな門扉の両側、低い石垣に添って、一本一本丁寧に並べられた赤いカーネーション。その花の色は、いきなり明日を生きることを断たれた17歳の少女の流した血の色にも、花に込めた羅針さんの怒りの色にも見えました。
理不尽に奪われた命を悼むために路上で歌い、集まったお金で買えるだけのカーネーションを毎年7月6日に門前に並べることを選び取った羅針さんの生き方を知り、それは私にとってカルチャーショックでした。そして、「生きる意味」への示唆をいただいた様に思いました。
何故、私が門前追悼に参加し続けたのか。
勿論、門扉事件が象徴する学校教育が内包する様々な問題への異議申し立てもありますが、単なる抗議活動ではなく、静かに僚子さんへの死を悼む場を続けるという運動のあり方への共感からでした。
30年の時が流れて、当時5才だった娘は、いまや一児の母となりました。
私は学校教育への疑問から、娘が就学期を迎えた時、ホームスクーリングで育てたいと思いました。娘の選択を尊重して、小学校へ入学はしましたが、結局、小学校三年から中学卒業までを学校教育の外で、娘は育ちました。その際、私たちはとても豊かな時間を過ごせたと思っています。
社会に目を向ければ、「学校化社会」はむしろ強化され、一方で学校の果たす役割は変化を余儀なくされているのではないでしょうか。経済格差が拡がる中、子どもの貧困がクローズアップされています。学校は、子どもを教化、管理、選別する装置としてではなく、子どもたち一人一人の状況に目を配り、より福祉的な役割にこそ、重きを置く必要があると思います。
また、ITに象徴される科学技術の進歩は止どまるところを知りません。「進歩」そのものが社会に何をもたらし、どのような結果を引き起こしているのかということが忘れられているのではないでしょうか。
暮らしが便利になる一方で、失うもの、置き去りにされるものがあることを、私たちはいつも気にかける必要があります。
門前追悼を長きにわたって呼びかけ、裁判を始めとして、通信の発行や講演会など、地道な活動を続けてこられた「ぐるーぷ 生命の管理はもう止めて!」の皆さまの多大な努力に心から敬意を表すると共に感謝したいと思います。本当にご苦労様でした。そしてありがとうございました。