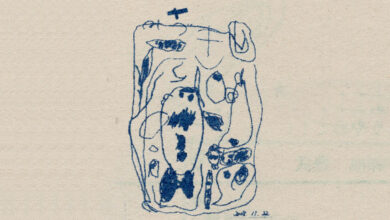校内ケース会議は生徒指導を変える?!
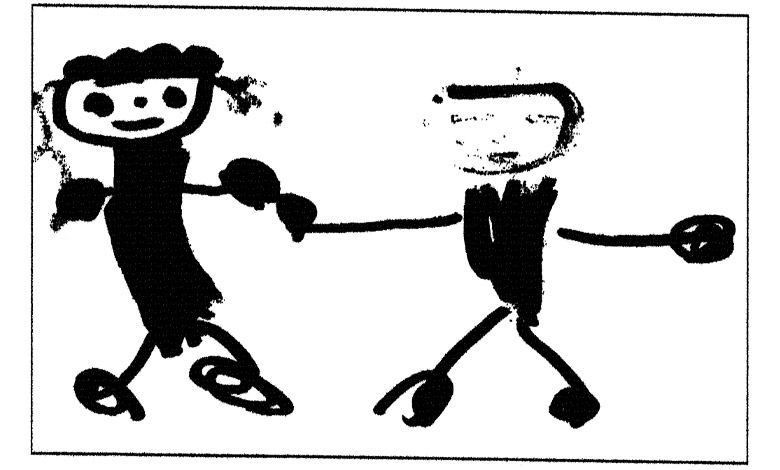
弁護士 峯本耕治
昨日、大阪市内のある中学校で2年生の子ども全員を対象に講演をしました。先生や保護者向けの講演は、良くも悪くも慣れてしまっているのですが、子どもを対象として、しかも、中学生を対象にすることはめったになく、「本当に話が伝わるのか」と、久しぶりに緊張する講演でした。子どもたちにメッセージが伝わったかどうか分かりませんが、講演の後に、全員でお礼の縦笛演奏をしてくれたり、花束贈呈してくれたりと、たいへん感激しました。茶髪のやんちゃそうな子どもたちも、静かに聞いてくれて、しかも、笛まで吹いてくれて、「やっぱり、子どもは可愛いいなあ」と再確認した一日でした。
ところで、この講演の依頼の趣旨は、「その中学では、管理型の生徒指導をしていることもあって、子どもたちに、今一歩、覇気がないので、元気が出る話をしてやって欲しい」というものでした。前回のニュースで、「校内ケース会議の活用が、これまでの生徒指導のあり方を変化させる可能性を秘めている」と書きました。そこで、今回は、この校内ケース会議というものが、どのようなものか、簡単にご紹介したいと思います。
私がイメージしている校内ケース会議は、子どもの問題に悩みや不安を抱えた教師が、ケースを持ち込み、関係する教師がスクールカウンセラー等の専門職(本当はスクールカウンセラーと共に、スクールソーシャルワーカーがいれば良いのですが)と共に、必要な情報を交換•共有し、対応方法を議論しあう場です。構成メンバーはケースごとに変わりますが、担任、生徒指導担当、学年主任、養護教諭、スクールカウンセラー等の専門職が主要なメンバーになります。
ケース会議では、子どもの問題行動を表面的に捉えて、その規制方法等を考えるのではなく、子どもや家族に関する色々な情報を交換しあうことによって、子どもの問題行動の背景や原因を理解し、それを踏まえて適切な対応方法を見いだすことを目的とします。
1月26日に「ケース会議をやってみよう!」というテーマで、校内ケース会議の持ち方についての教師向け研修を目的とするシンポジウムを開催しました。シンポの会場で、実際に3つのケース会議を実演したのですが、そのうちのひとつは、次のようなケースを題材にしました。
「学級崩壊をもたらすような問題行動を繰り返している子どもに対して、それまでは、担任が一人で注意や指導を繰り返していたが、一向に改善しないために、疲れ果てた担任が、学年主任に助けを求めたところ、学年主任の呼びかけで、ケース会議が開催された。このケース会議の場で、養護教諭から『子どもが保健室に来てすぐに寝ている』とか、『靴下がすごく汚れていたことがある』等の情報が提供され、子どもの問題行動の原因として、親のネグレクト(養育の怠慢•放棄)が背景にあることが明らかになってきた。そこで、関係する教師が、担任教師をサポートしながら、子どもに対して受容的に関わり、また、児童相談所等との他機関との連携を図りながら、家庭に対しても、効果的な働きかけを行っていくことになった。」
当たり前のことのように思われるのですが、これまで、多くの学校では、このような情報交換や率直な議論の場を持ててきませんでした。また、チームとしての対応も決して容易なことではありません。実は、それが、現在の学校が抱える一番の問題と言って良いかもしれません。
もちろん、このようなケース会議を開いたとしても、すぐに解決方法が見いだせるわけではありませんし、一朝一夕に問題が解決するわけでもありません。しかし、ケース会議を通じて、教師がチームとして対応するという雰囲気ができることによって、担任教師が孤立感や閉塞感に陥ることを避けることが可能になります。
そして、何よりも、このような情報の交換や共有、議論を通じて、子どもの問題の背景や原因を見つめる目や対応スキルが育っていきます。
そういう意味で、ケース会議の活用は、問題行動を問題行動としか捉えず、表面的な指導•規制方法に焦点が集中してきた、これまでの古典的な生徒指導に風穴を開ける可能性を秘めています。
前述のシンポジウムには、私的な研究会の主催によるものであるにもかかわらず、大阪府教育委員会•大阪市教育委員会の後援が得られ、会場にも、教師だけでなく、教育委員会の方が多数出席されていました。「これまでの生徒指導のあり方ではダメだ」という雰囲気が、教師の間でも、かなり強くなってきているようです。
 子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
清水克之(著), 佐藤拓代(著), 峯本耕治(著), 村井美紀(著), 山野良一(著), 松本伊智朗(編集) / 明石書店 / 2010年2月5日
<内容>
子ども虐待と貧困との関係を乳幼児期から青年期までの子どものライフステージに沿って明らかにする。執筆者のまなざしは、親の生活困難に向けられ、子どもと家族の社会的援助の必要性を説き、温かい。貴重なデータも多数掲載している。
 子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
小林美智子(著), 松本伊智朗(著) / 明石書店 / 2007年12月6日
<内容>
公権力の介入を求めるまで深刻化した子ども虐待。だが介入は虐待防止の切り札といえるのか。2005年の日本子ども虐待防止学会シンポジウムの記録を基に編まれた本書は、日英の経験をふまえ、虐待を防ぐために本当に必要な「ケアする社会」を構想する。
 スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
山野則子(編集), 峯本耕治(編集) / ミネルヴァ書房 / 2007年8月1日
<内容>
はじまったばかりのスクールソーシャルワーカーの活躍を描く。スクールカウンセラーや養護教諭とともに様々な問題に悩む親子に、社会的問題を含めて解決にあたる事例を紹介します。今までにない児童生徒へのアプローチに非常な関心がもたれています。
 子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
峯本耕治(編集) / 明石書店 / 2001年12月12日
<内容>
先進的なシステムをもつイギリスの児童虐待防止制度の詳細と、実際の運用状況を具体的に紹介する。ライン等も示し、問題点にも触れる。