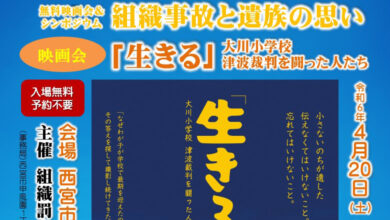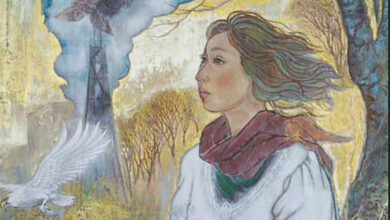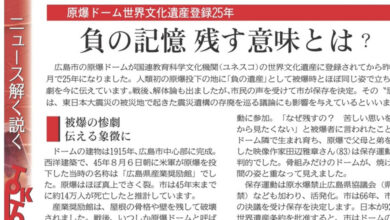大丈夫?子どもたちの人間関係

弁護士 峯本耕治
1 萎縮する子どもたちの人間関係
2週間ほど前のことですが、夜10時頃にファミリーレストランに入ると、私の隣の席に中学3年くらいか高校1年蔵の男女4名がいました。多分、塾帰りで、それ自体は特別なことではないのですが、その4人全員が、私がいた30分くらいの間、ほとんど一言も会話をすることなく、それぞれ携帯電話でメールをし続けていました。子どもの世界では珍しい光景ではないのかも知れませんが、私にとっては驚きでした。子どもたちの人間関係やコミュニケーションは、一体、どうなっているのでしょうか?
最近は、小•中•高を問わず、教育相談担当の先生が決められていて、中学校を中心にスクールカウンセラーや心の相談員等の配置も進んできています。教育相談を担当している教師やスクールカウンセラーから話を聞くと、子どもたちから寄せられる相談には、学年を問わず、かなり共通点があるそうです。例えば、
• 友達を傷つける言葉を言ってしまったけど、嫌われないだろうか? どうしたら良いか?
• 最近、友達の態度が前と違うような気がするけど、嫌われたのかも知れない?
• 自分はクラスの友達からシカトされているのではないか?
• 今はAさんがいじめられているけど、次は自分がいじめられないか?
• 友達の中で、面倒なことを自分ばかりやらされているような気がするけど、嫌と言えない。どうしたら良いか?
小中高を問わず、このように、自分が嫌われたり、いじめられることを恐れたり、基本的な人間関係に関する相談が非常に多いそうです。少年事件で出会う子どもたちも、同じなのですが、子どもたちの人間関係が、気遣いだらけの人間関係というか、非常に萎縮した関係になっていることが判ります。
もちろん、自分の子ども時代を振り返っても、人間関係にはそれなりに気を使っていましたが、最近は、それがかなり極端になっているようです。
2 いじめと携帯メール
原因は何でしょうか。社会全体の未熟化など、色々な社会的要因がかかわっていると思いますが、私は、いじめ問題が、一つの大きな原因になっていると思います。
以前は「いじめ」というと特別な出来事というイメージがあったのですが、最近は、むしろ一般化してしまって、大きな事件としては取り上げられなくなっている反面、子どもたちに、「いつ自分がいじめられるかもしれない」「友達から嫌われないようにしないといけない」というような気持ちを必要以上に持たせ、人間関係を萎縮的にさせたり、希薄化させたりする大きな原因となっています。
そして、萎縮化•希薄化を一層進めているのが、最近のメール、特に携帯メールやインターネットの急激な浸透です。簡単に携帯メールを使えることにより、コミュニケーションが間接的なものになって、しかも、表面的なものになってしまっています。直接会って会話すると、当然、腹が立ったり、傷ついたり、傷つけられたりすることが多くなりますが、メールでの会話では、もともと、それほど突っ込んだ会話をすることは不可能ですし、お互いにとって心地よい表面的な会話で済ませることが可能です。少なくとも、直接会って話をする場合と比較すると、あまり、人間関係上の葛藤を感じなくて済みます。
最初に紹介した4人の子どもたちも、ひょっとしたら、一緒に居ながら、互いにメールで会話をしていたのかも知れません。そうだとすると、もっと不気味ですが。
今の子どもたちは、「傷つきたくないけども、人とは常につながっていたい」「誰かに愛されたい」という気持ちを強く持っているといわれていますが、私も少年事件や家族、学校の問題にかかわる中で、そのことを強く感じます。
前号で、秋田真志さんがテレクラや出会い系サイトが関係する少年事件が増えていると書かれていました。その通りで、しんどい家族が増えて、家族の中で居場所を失った子どもたちが増え、同時に、友人関係が萎縮化し希薄化する中で、逆に、人とのつながりや愛されることを極端に求める、寂しい子どもたちが増えています。
3 対人関係技術•能力の低下が招く児童虐待•DV
このような子どもたちの人間関係の萎縮化や希薄化の問題は、それだけに止まらず、実は、様々な社会問題を引き起こす危険性があります。
それは、人間関係の萎縮化•希薄化は、そのまま対人関係技術•能力の低下を招くことになるからです。あまり意識することはありませんが、人は、子ども時代からの人間関係の中で、対人関係の技術や能力を身につけていきます。
人と出会い、会話をし、時には喧嘩をし、その中で、人を傷つけたり、傷つけられたり。傷ついたり、落ち込んでも、気を取り直したり。人を傷つけた後に、それをカバーしたり。喧嘩しても仲直りしたり。相手に言いにくいことを言う方法を学んだり。どうしてもうまくいかない人とは、付き合わないようにしたり。自分の思い通りにならないことを学んだり。腹が立った時に、それを表現する方法を学んだり。ストレスを溜めない方法を学んだり。
子どもたちの人間関係が萎縮化•希薄化することは、つまり、このような対人関係技術や能力を身につける機会が減ることを意味します。
弁護士として色々な事件を担当していると強く感じるのですが、人の抱えるトラブルのほとんどに人間関係上のストレスが関係しています。それは、個人や家族の問題に限らず、会社の事件や純粋に経済的事件であっても同じです。
ですから、対人関係技術や能力の低下は、そのまま人間関係のストレスを高め、様々なトラブルを発生させることになります。
そして、人間にとって、最も基本的な人間関係が、夫婦関係や親子関係からなる家族関係です。
今、児童虐待やDV(夫婦や恋人間の暴力)が本当に大きな社会問題になっています。どちらも、「家庭の中で、自分の思い通りにならない事があった時、それによってストレスを感じた時に、言葉によるコミュニケーションではなく、力や暴力によって解決しようとする、自分のストレスを発散しようとする」という点において、共通した性格を持っています。
つまり、児童虐待やDVの問題も、夫婦や親子関係における、対人関係技術や能力の問題そのものです。ですから、子どもたちの対人関係技術や能力が低下するということは、そのまま、このような家族問題が今後も増えつづけていくことを意味していると言って良いと思います。
家庭教育•学校教育の場を通じて、例えば、ソーシャルスキルトレーニング等の導入により、子どもたちの対人関係技術•能力を育てる場を意図的•積極的に作っていかないといけない時期が来ているのかも知れません。
子どもたちの人間関係は、私たち大人の人間関係の反映でもあるので、なかなか難しい問題ですが、皆さんは、どう思いますか?
 子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
清水克之(著), 佐藤拓代(著), 峯本耕治(著), 村井美紀(著), 山野良一(著), 松本伊智朗(編集) / 明石書店 / 2010年2月5日
<内容>
子ども虐待と貧困との関係を乳幼児期から青年期までの子どものライフステージに沿って明らかにする。執筆者のまなざしは、親の生活困難に向けられ、子どもと家族の社会的援助の必要性を説き、温かい。貴重なデータも多数掲載している。
 子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
小林美智子(著), 松本伊智朗(著) / 明石書店 / 2007年12月6日
<内容>
公権力の介入を求めるまで深刻化した子ども虐待。だが介入は虐待防止の切り札といえるのか。2005年の日本子ども虐待防止学会シンポジウムの記録を基に編まれた本書は、日英の経験をふまえ、虐待を防ぐために本当に必要な「ケアする社会」を構想する。
 スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
山野則子(編集), 峯本耕治(編集) / ミネルヴァ書房 / 2007年8月1日
<内容>
はじまったばかりのスクールソーシャルワーカーの活躍を描く。スクールカウンセラーや養護教諭とともに様々な問題に悩む親子に、社会的問題を含めて解決にあたる事例を紹介します。今までにない児童生徒へのアプローチに非常な関心がもたれています。
 子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
峯本耕治(編集) / 明石書店 / 2001年12月12日
<内容>
先進的なシステムをもつイギリスの児童虐待防止制度の詳細と、実際の運用状況を具体的に紹介する。ライン等も示し、問題点にも触れる。