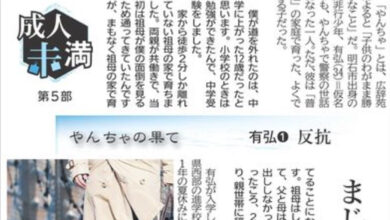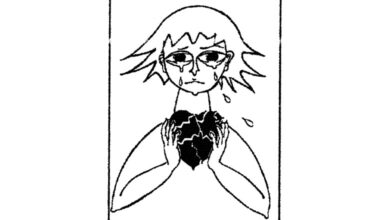どんどん遅れていく日本の少年司法制度
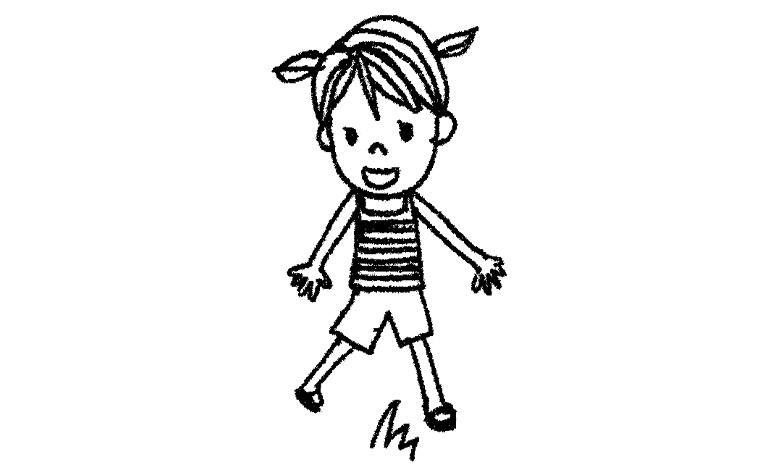
弁護士 峯本耕治
今年もまた、大阪(寝屋川)で辛い事件が起こってしまいました。いくら学校の安全を確保しようとしても、卒業生が教師に会いたいと言ってくるのを防ぐことは難しいですよね。
この事件についても、事件の背景•原因や警察捜査のあり方等について色々と思うことがあるのですが、現時点では余りにも情報が不足していますので、次回にしたいと思います。今回は、所さんからのリクエストもあって、海外の少年司法制度について簡単に紹介したいと思います。
日本では、再び、少年法の改正が行われようとしています。これまで刑事責任を問えなかった14歳未満の少年の事件について、あらたに警察の「調査権」を認め、少年院への収容も可能にすることなどを盛り込んだ少年法改正案が今国会に提出されているのです。神戸の小学生殺害事件以降の厳罰化の流れの延長線上にある改正と言って良いと思います。
日本では相変わらず、少年事件が続くと「厳罰が必要である」という単純な意見が主流を占め、それを超えた議論がなかなか起こってきません。結果的に、前回の少年法改正に見られるように、「少年審判への検察官立会」や「故意行為による死亡事件についての原則逆送」などの社会的ガス抜きとしか思えないような改正が行われるだけに終わってしまい、少年犯罪防止のために本当に必要と思われる改革が全くと言ってよいほど進んでいません。神戸事件以降を見ても、そういう状況が既に10年近く続いているわけで、今回再び、少年犯罪の防止にとって到底意味があると思えない改正、それどころか、「14歳未満の少年の事件は福祉の問題として対応する」という基本原則を損なう改悪が行われようとしているわけです。
しかし、その間も海外では、色々な新しい少年司法モデルへのチャレンジが続いています。1990年代以降、その中心となっているのが、リストラティブ•ジャスティス•モデル(被害回復のための少年司法モデル)、日本では「修復的司法」と呼ばれているものです。
リストラティブ•ジャスティス•モデル(被害回復のための少年司法モデル)とは、罪を犯した少年に自分の行為の責任を取らせること、少年の責任感を醸成することが、再犯防止につながるという考え方を前提としています。
問題は「少年の責任」という言葉の中身ですが、これまでは、犯罪を犯したことについての社会に対する責任という考え方が中心にあり、そこから、社会に対する責任を果たさせるために、厳しい罰則が必要であるとの懲罰的な考え方に行き着く傾向がありました。
しかし、このモデルにおける「少年の責任」は、社会に対する「抽象的な責任」ではなく、現実の被害者等に対する「具体的な責任」を意味しています。
「少年に責任をとらせる」という言葉も、これまでのような処罰(刑罰)を受けることによって社会に対する責任を果たすという受け身の意味ではなく、被害者が現実に受けた財産的•精神的な損害の回復を図るという、積極的な意味を持っています。
つまり、リストラティブ•ジャスティス•モデルとは、その言葉が示すとおり、少年司法システムの手続きを通じて、被害者に生じた有形•無形の損害を少年自身によって現実的に回復させること、それによって、少年に自らの行為の結果と責任を具体的に認識させ、少年の責任感を育てていくことを目的とするものです。
このモデルは、「少年の保護か処罰か」という伝統的な対立とは異なる観点からの第三のアプローチと言ってよいと思います。
最も徹底した形で、このモデルが採用されているのは、ニュージーランドで、少年の処遇を決定する方法として、ファミリーグループ会議(FGC)と呼ばれる手法が用いられています。
FGCとは、プロのコーディネーターによって、少年、家族(親族を含む広い意味での家族)、少年の福祉に関係する教師等の関係者、更には、被害者(もちろん、被害者が望む場合に限られます)が招集されて会議が開催され、その会議において、少年の処遇プランを決定するというものです。このシステムは、ニュージーランドの先住民であるマオリの人々の間で伝統的に利用されていた紛争解決方法を採用したものです。
ニュージーランドでは、1989年の青少年•家族法によって、このFGCシステムが、民事•刑事を問わず、青少年の福祉に関わる問題を取り扱う時の中心的な方法となりました。少年事件をはじめとして、青少年の福祉に関わる重要な問題が発生した場合には、原則としてFGCが招集され、そこで、青少年の処遇が決定されます。
少年事件手続きに関して言えば、少年は、まず、警察又は少年裁判所(ユースコート)から、FGCに送致されます。FGCは、最も重大な犯罪を除く、全ての少年事件を扱うことができて、送致を受けると、少年司法コーディネーターが会議を招集します。会議には、少年の家族(親族に限らず広い意味での家族)、被害者、その他利害関係を持つ人々が呼ばれ、全ての関係者が、処遇の種類等についての情報が与えられた上で、少年の抱えている問題•困難の改善•解決方法と犯罪行為に対する解決方法について自ら意見を述べ、解決策についての協議を行い、少年を含む関係者自身によって、少年の処遇が決定されるわけです。FGCにおいて、選択できる処遇には、監督命令(スーパービジョン命令)、被害弁償、社会奉仕命令、運転免許の剥奪、謝罪、警告などがあり、最もよく利用されるのが、社会奉仕、謝罪、被害弁償などです。
ニュージーランドでは、実際に、このFGCシステムによって、非行•犯罪少年の多くが、裁判手続きを経ることなく処遇されることが可能となり、例えば、1984年には、調査対象となった全少年事件の45%が裁判所に送られていましたが、FGC導入後の1993年には14%に減少しました。また、1987年から1989年の間に刑務所収容処分を受けた少年の数は各年平均374人であったものが、1990年には112人に激減しています。
このFGCシステムには次のようなメリットがあると評価されています。
① 少年自身を協議に参加させることによって、少年自身に自らの犯罪行為の結果とそれによって生じる社会的責任を、直接的に自覚させることができます。それが、少年の責任感の醸成に大きく貢献します。他方、少年自身も、自らの謝罪の意思、更生の意思を明確に示す機会を持つことができます。
② 被害者が協議に参加できることによって、被害者自身、損害を回復する現実的機会が与えられると共に、少年の処遇決定手続きに関与することによって、被害者の精神的に納得が得られやすい。これまでの経験で、被害者の多くは、この協議において、加害少年に対する恨みをぶつけることよりも、加害少年からの真摯な反省の態度や言葉、更生の意思が示されることを要求する傾向が強いことが明らかになっています。このような話合いの手続きは、少年自身の態度に大きな影響を与えると同様に、被害者の傷ついた心を癒す上でも大きな影響力を持っています。
③ 親や家族はもとより、友人、学校の先生、近所の人など、少年の生活に重要な関係を持つ全ての人を協議に巻き込むことによって、少年を社会に再統合する上で、最も良いと思われる手段を様々な観点から検討することができます。また、そのような協議の過程自体が少年の成長や社会復帰をサポートすることになります。また、親や家族にも、少年の行為の結果に対する責任を具体的に意識させることができ、親や家族の子どもに対する監督力を高める効果も持ちます。
また、イギリスでも、1990年代の後半に、リストラティブ•ジャスティスモデルを採用した大きな少年司法制度改革が行われました。
イギリスでは、それまで、一部の重大犯罪を除き、少年事件はユースコートと呼ばれる少年裁判で取り扱われ、有罪•無罪の事実認定から最終的な刑(処遇)の決定•宣告までの全ての手続きが、この少年裁判所で行われていました。
ところが、この改革によって、初めて裁判を受けることになった少年で、自らの有罪を認めた少年の処遇については、実質上、少年裁判所とは別のところで決定されることになりました。以下に、その内容を、要約して紹介します。
① 少年が少年裁判所に起訴された場合、それが初めての起訴であって、かつ、少年が有罪であることを認めた場合には、少年は、処遇決定のために、少年裁判所からユース•パネルという委員会に送られます。
② 少年裁判所から送致を受けたユース•パネルは、少年と親•保護者(16歳未満の場合は強制、16歳•17歳の場合は強制でないが奨励されます)、更に、必要があれば、他の親族や教師、被害者(合意を前提とする)などの関係者を招いて話し合いを行い、最終的に、少年との間で、少年が果たすべき義務を定めた「契約」(コントラクト)を締結します。
③ この「契約」には、被害者あるいは地域社会が受けた損害を回復するため、及び、犯罪の原因を克服するために、少年が果たすべき義務が具体的に記載されます。
通常、次のような義務が内容とされています。
• 被害者への手紙又は面会による謝罪
• 被害者への金銭による被害弁償
• 家庭カウンセリングセッションや薬物中毒からの治療回復コース等への参加
• 地域社会における無償の奉仕活動
• 学校への規則正しい登校、トレーニングスキームなどの教育的措置に応じること
• 特定の行為の禁止、特定の場所に行くことの禁止
④ 「契約」では、施設への収容を内容とすることはできません。従って、少年裁判所が、例外的に施設収容処分を課す必要があると考える場合には、ユースパネルへの送致は行われません。
⑤ 少年が「契約」に定められた義務を果たすべき期間は最長12ヵ月で、少年裁判所がユースパネルに送致するに際して、犯罪の重大さに応じて、その期間を決定します。ユースパネルは、少なくとも3ヵ月おきに、少年が「契約」に従って義務を履行しているか否かを監督•確認します。
⑥ 少年が「契約」に定められた義務を守らなかった場合には、少年は、少年裁判所に戻され、少年裁判所において、もとの犯罪に対して、刑(処遇)が言い渡されることになります。その際、少年裁判所は、少年が「契約」に定められた義務をどの程度守っていたかを考慮して、刑を決定しなければなりません。
⑦ それ以外にも、ユースパネルにおける話し合いの結果、少年との間で、少年が果たすべき義務について合意が成立せず、契約締結に到らなかった場合、少年はユースパネルから少年裁判所に戻され、少年裁判所で刑の宣告を受けることになります。
⑧ これに対し、少年が「契約」に定められた義務を履行し終えた場合には、それが、少年裁判所に報告され、「契約の終了」が宣言されます。
⑨ 契約を無事終了した少年は、通常、名前を公表されません(イギリスでは、少年裁判所の裁量により有罪判決を受けた少年の名前を公表することが認められています。)。
このイギリスの新しい少年司法システムは、少年裁判所やユースパネルが一方的に刑や処分を言い渡すのではなく、少年自身との合意による契約という方法をとることによって、少年の責任感を引き出そうとしている点で、なかなか巧妙なものです。
少年法の分野に限らず、日本の現状からすると、イギリスやニュージランドのように、リストラティブ•ジャスティス•モデルに基づいた大胆な制度改革が行われるとは、とても思えません。
現在、大阪や関東で、弁護士等が中心となって、NPO活動として、このモデルを利用した取組がスタートしていますが、公的な制度への導入の見通しは今のところありません。
しかし、このモデルは、現在の制度内においても、ちょっと工夫すれば十分に利用可能なものだと思います。例えば、保護観察処分が言い渡された後に、調査官、あるいは保護観察官(保護司)が、少年と保護者だけでなく、その他の親族、学校の先生、職場の監督者など、少年の更生を援助してくれる可能性のある関係者を集めて、関係者自身に主体的に話し合わせて、少年の保護観察中の生活や監督方法、教育方法、対応等を具体的に決定させたり、また、試験観察の場合にも同じような方法が利用できます。また、少年院から退院する際にも、同様の方法が採れるはずで、そうすることによって、少年の更生をかなり支えることになるのではないでしょうか。
早く「厳罰」議論を卒業して、本当に何が必要なのかを考えることができる状況になりたいものです。このままでは日本の少年司法制度はどんどん取り残されていってしまいます。
 子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
清水克之(著), 佐藤拓代(著), 峯本耕治(著), 村井美紀(著), 山野良一(著), 松本伊智朗(編集) / 明石書店 / 2010年2月5日
<内容>
子ども虐待と貧困との関係を乳幼児期から青年期までの子どものライフステージに沿って明らかにする。執筆者のまなざしは、親の生活困難に向けられ、子どもと家族の社会的援助の必要性を説き、温かい。貴重なデータも多数掲載している。
 子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
小林美智子(著), 松本伊智朗(著) / 明石書店 / 2007年12月6日
<内容>
公権力の介入を求めるまで深刻化した子ども虐待。だが介入は虐待防止の切り札といえるのか。2005年の日本子ども虐待防止学会シンポジウムの記録を基に編まれた本書は、日英の経験をふまえ、虐待を防ぐために本当に必要な「ケアする社会」を構想する。
 スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
山野則子(編集), 峯本耕治(編集) / ミネルヴァ書房 / 2007年8月1日
<内容>
はじまったばかりのスクールソーシャルワーカーの活躍を描く。スクールカウンセラーや養護教諭とともに様々な問題に悩む親子に、社会的問題を含めて解決にあたる事例を紹介します。今までにない児童生徒へのアプローチに非常な関心がもたれています。
 子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
峯本耕治(編集) / 明石書店 / 2001年12月12日
<内容>
先進的なシステムをもつイギリスの児童虐待防止制度の詳細と、実際の運用状況を具体的に紹介する。ライン等も示し、問題点にも触れる。