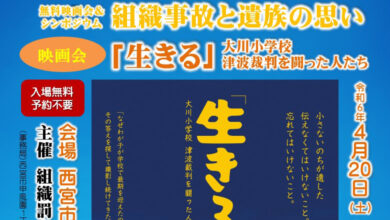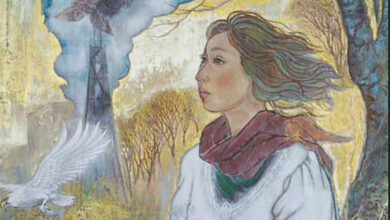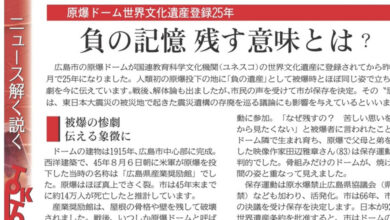「国家の品格」読まれました?

弁護士 峯本耕治
今、ベストセラーになっている本(藤原正彦•新潮新書)です。そのタイトルから、何となくナショナリスティック的なものを感じて、読んでいなかったのですが、何人かの人から「結構、共感するよ」と言われて読んでみました。
欧米的な論理と合理性の限界を指摘して、その大切さを前提としながらも、日本が持ってきた情緒や形の大切さ、武士道精神の大切さを訴えた内容で、「論理と合理性、市場主義、グローバル化のみの改革では社会の荒廃をくい止めることはできない。今日本に必要なのは、論理よりも情緒、英語よりも国語、民主主義よりも武士道精神であり、国家の品格を取り戻すことである」等と述べられています。
武士道精神や日本文化等から、引っ張ってくることには、どうしても少し抵抗を感じてしまうのですが、実は、色々言いながらも大変「日本人的」であると感じている私としては、その内容に、基本的に共感を感じてしまうのです。
著者は、その中で、「いじめに対して何をすべきか」について、「カウンセラーを置く、などという対症療法より、武士道精神にのっとって卑怯を教えないといけない。大勢で1人をやっつけることは文句なしに卑怯であるということを叩き込まないといけない。」と述べています。
これはまさにその通りだと思います。今、子どもたちのいじめのケースに関わっていると、子どもたちの心が無法地帯になっているのではないかと感じます。もちろん、いじめには、色々な原因があります。加害者側の子どもにも、たとえば、過去にいじめを受けていた経験があったり、親子関係のしんどさからくる大きなストレスを抱えていたり、また、被害者の側にも、いじめられる要因が少なからずある場合もあります。
ただ、どのような理由があるにしても、今の子どもたちを見ていると、自分自身が抱えているストレスの発散や、認められたい、優越感を感じたい等の「居場所」探しを、友達への攻撃やいじめという形で、何のブレーキもかからないままに、ストレートにしている姿が見えてきます。そして、周辺にいる子どもたちも、「いつ、自分がいじめられることになるかも知れない」という不安感をいつも持っていて、気遣いの多い友人関係になっているというのが、子どもたちの世界の普通の状況です。
私は、このような状態を「心の無法地帯」と呼んでいるのですが、少なくとも、私の子ども時代には「人をいじめてはいけない」とか「弱い者いじめをしてはいけない」「人には親切にしないといけない」という素朴な正義感が、もう少し、存在していたように感じます。こういう素朴な正義感が失われると、人は結構残酷なものですから、人間関係はしんどいものになります。
なぜこういう「心の無法地帯」が生じてしまったのかは分かりませんが(多分、大人の世界がそうなってしまったからだと思いますが)、一つ言えることは、親も学校の教師も、このような素朴な正義感を、ストレートに子どもたちに伝えてこなかったことは、確かだと思います。
昔は、特に誰かから意識的に教えられるということがなくとも、家庭•地域•学校等の様々な人間関係の中で、普通の発達環境の中で、自然にそのような素朴な正義感を学ぶことができたのでしょうが、今は、そのような発達環境は失われてしまっています。誰かが、しっかりと、ある意味、自分の人格をぶつけるような形で、必要なメッセージを伝えていかないといけない時代になってしまっているのだと思います。
そして、一般的に、それができるのは、やはり教師しかありません。教師が、心から子どものことを思い、「いじめはだめだ」、「それは理屈を越えてだめなんだ」「卑怯だからダメなんだ」「正義に反するから、人間としてダメなんだ」というメッセージを本気で伝えていくこと、教師がきちんと子どもたちに対峙して必要なメッセージを伝えていくことが、いじめ防止のために、そして、子どもたちの成長発達のために、今まで以上に必要になってきているのだと思います。
実は、イギリスのいじめ防止対策のプログラムの中心も「いじめがダメだ」というメッセージを明確に送ること、「いかなる理由があっても、いじめをすることによって、得をさせない、成功体験を積ませない」という点にあります。イギリスには武士道精神はありませんが、結局は、同じことを言っているのだと思います。
そして、同じようなことが、学級崩壊等への学校における子ども達の様々な問題行動への対応についても当てはまります。中学校のケース会議に出席すると、しばしば、子どもが授業中に平気で立ち歩いたり、教室を出ていったりしても、教師がどうしようもなくそのままにしてしまっているケース、授業中にゲームをしている子どもに注意しても、「人に迷惑をかけていないからエエやろ」と言われてしまうケースなど、教室が物理的な無法地帯になってしまっているケースに出会います。
つい、「何で、それを許すのか」「そんなんは受容と違う」と思ってしまうのですが、実は、そこにいくまでに長い経緯があって、個々の子どもたちのそういう状況は、小学校時代から始まっていることが少なくありません。
もちろん、子どもたちの問題行動の背景•原因には、家庭の問題、友人関係上の問題、学校の対応の問題等の様々な要因があり、これらの問題行動も、愛情要求の裏返しであったり、居場所探しであったりするわけで、それを踏まえた合理的な対応は必要となります。しかし、「授業中はきちんと授業を受けなければならない」、「人の話は聞かないといけない」等のことは、本当に子どもたちが成長発達していく上で大切なことです。
問題の初期の段階で、教師には、「子どもたちへの強い思い」を持って、このような素朴なメッセージを本気で伝えていくこと、ある意味、自分の人格をぶつけて、本気で勝負することが求められているのではないかと思います。
「国家の品格」は、日本の民族的なものや武士道精神から色々な価値をひっぱってきたり、また、自由や平等、民主主義の限界等をストレートに述べていて、憲法的価値観を大切に思う立場からは、どうしても抵抗感があるのですが、実は、書いてあることのかなりの部分に共感を感じてしまうのは私だけでしょうか。
一度、読んで見て意見を聞かせてください。
 国家の品格 (新潮新書)
国家の品格 (新潮新書)
藤原正彦(著) / 新潮社 / 2005年11月20日
<内容>
日本は世界で唯一の「情緒と形の文明」である。国際化という名のアメリカ化に踊らされてきた日本人は、この誇るべき「国柄」を長らく忘れてきた。「論理」と「合理性」頼みの「改革」では、社会の荒廃を食い止めることはできない。いま日本に必要なのは、論理よりも情緒、英語よりも国語、民主主義よりも武士道精神であり、「国家の品格」を取り戻すことである。すべての日本人に誇りと自信を与える画期的日本論。
 子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
清水克之(著), 佐藤拓代(著), 峯本耕治(著), 村井美紀(著), 山野良一(著), 松本伊智朗(編集) / 明石書店 / 2010年2月5日
<内容>
子ども虐待と貧困との関係を乳幼児期から青年期までの子どものライフステージに沿って明らかにする。執筆者のまなざしは、親の生活困難に向けられ、子どもと家族の社会的援助の必要性を説き、温かい。貴重なデータも多数掲載している。
 子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
小林美智子(著), 松本伊智朗(著) / 明石書店 / 2007年12月6日
<内容>
公権力の介入を求めるまで深刻化した子ども虐待。だが介入は虐待防止の切り札といえるのか。2005年の日本子ども虐待防止学会シンポジウムの記録を基に編まれた本書は、日英の経験をふまえ、虐待を防ぐために本当に必要な「ケアする社会」を構想する。
 スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
山野則子(編集), 峯本耕治(編集) / ミネルヴァ書房 / 2007年8月1日
<内容>
はじまったばかりのスクールソーシャルワーカーの活躍を描く。スクールカウンセラーや養護教諭とともに様々な問題に悩む親子に、社会的問題を含めて解決にあたる事例を紹介します。今までにない児童生徒へのアプローチに非常な関心がもたれています。
 子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
峯本耕治(編集) / 明石書店 / 2001年12月12日
<内容>
先進的なシステムをもつイギリスの児童虐待防止制度の詳細と、実際の運用状況を具体的に紹介する。ライン等も示し、問題点にも触れる。