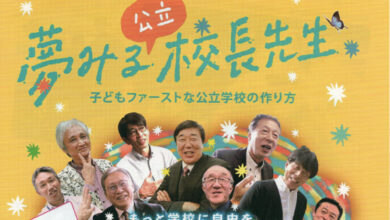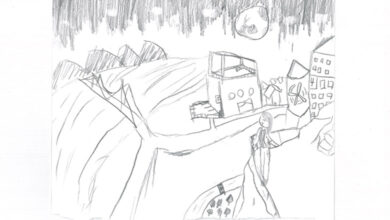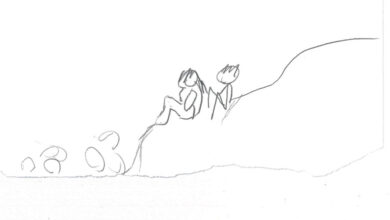最悪の年末年始と教育基本法「改正」

弁護士 峯本耕治
12月23日に年甲斐もなくラグビーの試合で頸椎捻挫をしてしまい、年末•年始は、いわゆる鞭打ち症状と腕•指のしびれに苦しんで、寝て過ごしました。これまで担当した交通事故の損害賠償請求事件などで、鞭打ち症状に苦しむ依頼者の方を多数見てきましたが、自分が経験してみて初めて、そのしんどさが判りました。交通事故の鞭打ち症状に長期間苦しんでいる人が、鬱病的な症状を示し始め、悪循環に陥っていくパターンが実感できました。
話は変わりますが、12月に教育基本法が「改正」されてしまいました。憲法と並んで根本規範を構成する教育基本法が、「改正」の実質的•現実的な必要性が全くないにもかかわらず、しかも、ほとんど議論がないままに簡単に「改正」されてしまうというのは、何とも異常な時代になってしまったものです。
その「改正」が国会で決議された前日に、近畿弁護士会連合会の子どもの権利委員会で、改正反対の集会を持ちました。国会決議が間近に迫っていることは判っていたのですが、最後にもう一度意思表示をしようということで集会を持つことになったのです。その時点では、愛国心条項などの法律の中身を議論しても、ありきたりで面白くないので、教育基本法「改正」が学校現場や子どもの権利にどういう影響を与えるかという視点から、学校の先生に来ていただいて学校現場の状況を報告してもらいました。その報告の中身は、かなり深刻なものでした。小中高から各1人の先生に来ていただいたのですが、共通していたのは、学校現場に現れている格差社会の厳しい現実でした。
小学校の先生からは、「ゆとり教育の弊害ばかりが指摘されているけれど、実際には、既にステップアップ方式の教科書が用いられていて、学力進度のスピードが速すぎて、完全に差をつけることを是認したものになっている」「保護者の経済状況が深刻になっていて、給食費、副教材費が払えない家族が増えてきている。仕事に追われて、懇談会等にも全く出席できず、家庭訪問をしても会えない保護者が非常に多い」「コンパス等の教材を100円ショップで買ってくる子が増えていて、数回使っただけですぐに壊れてしまって、辛い思いをしている」「土日も仕事をしている保護者が増えてきているので、子供は休日も一人でいることが多くなり、生活リズムが崩れてしまい、月曜の朝は、寝ていたり、妙に興奮していて授業にならない。そのため、担任教師としても、月曜は、とにかく無事過ごすことが大きなテーマで、勉強どころではなくなっている」等の報告がありました。昨年末のNHKスペシャル「ワーキング•プア」では、ダブルワーク(昼、夜双方仕事に出ている)の家庭が取り上げられていましたが、学校現場では既に特別なことではなくなっているようです。
中学校の先生からも、「就学援助率が高まり、多い学校では軽く50%を越えてきている。行政は財政上の理由から、就学援助の基準を厳しくしたが、それでも受給者が増えている」「義務教育でありながら、教材費以外に修学旅行等のための積立金が3年間で18万円くらいかかるため、これを負担できない家族が増えてきている。」等の報告がありました。
更に、高校の先生からも、「公立であっても学費負担ができないために退学する子どもが増えている」「子ども達の学校生活も変化し、アルバイトをしないと学校生活を送れないというのが、現在の公立高校の実態である」「大学進学を希望する子どもについても、推薦入試等で入試が早まったことにより、入学前に入学金を負担しなければならないのが一般的になっている。3年の10月には少なくとも80万円位は準備しなければならなくなっているが、奨学金は入学してからしか出ず、国民金融公庫等からのつなぎの融資も受けられないため、入学金を払えないという生徒がクラスの中に何人かいる」「奨学金にも制限が加えられてきている」等の厳しい現実が報告されました。
一般的な情報としては聞いていたのですが、具体的な話を聞くと、その厳しさにショックを受けます。経済的格差により教育の機会均等が確実に脅かされる状況が生まれてきていると言って良いと思います。それだけでなく小学校時代から親が子どもに向き合える時間的余裕がなく、親子の安定した愛着関係の形成が物理的に難しい家族が増えてきています。
今回の教育基本法の「改正」は、もちろん、このような厳しい実態を何ら改善することにはつながりません。それどころか、「改正」教育基本法は、表面的には見えにくいものの、そこには競争原理の積極的な導入が巧みに盛り込まれています。理念的にも、アメリカ型の新自由主義を背景としたものですから(実は、民主党の改正案は、この新自由主義的傾向がより強いものであったという悲しい現実がありますが)、むしろ、このような格差を積極的に是認するものと言って良いと思います。
このような格差は、90年代からのグローバリゼーションに象徴される経済環境と、その中で選択されてきた経済•社会政策によって生まれてきたものですが、この教育基本法「改正」の背景にも、「国•地方自治体の厳しい財政状況の中で、教育に一般的にお金をかけない形で、一部のエリート層を育てていくためには、競争原理を積極的に導入し、格差をやむを得ないものと是認していく」とう考え方が確実にあると思います。
しかし、ヨーロッパ(EU)では、このような裸の新自由主義的考え方は、既に後退し、大きな修正が加えられてきています。アメリカと並んで、最も新自由主義的政策が導入されたイギリスにおいても、1997年に労働党(ブレアー)政権が誕生してからは、第3の道が探られ、「社会的排除の撲滅」をスローガンとして、教育においても様々な改革が加えられてきています。最近では、若年失業率の高まりや格差への対策として、高校教育の義務教育化が検討されています。
今の日本の政策は、世界的に見ても明らかに時代遅れです。格差を是認し、固定するような政策がうまくいくはずがありません。今の教育を改革するには、一人一人の子どもを大切にし、その成長発達を保障する方向での改革を実施する以外にありません。
子どもは、親との安定した愛着関係を支え•ベースとして、学校生活•友人関係等における様々な体験や学び•遊び、人とのつながりを通じて、自尊心や自己有用感を高め、人への信頼感を育む中で、成長発達していくことができます。これは当然のことなのですが、私自身も、少年事件や学校ケース、虐待ケースなどの様々なケースを通じて達した非常にシンプルな結論です。
子どもたちにそのような環境を保障していくためには、少なくとも、過酷な労働環境の中で、物理的に親が子どもと向き合えないような状況は防がなければなりません。積立金を払えないために修学旅行に行けないとか、教材に困るような状況は辛すぎます。公立高校すら退学しなければならない状況や入学金を払えないために大学進学を断念しなければならないような状況は避けたいものです。また、教職員が、集団教育の中においても、互いに支え合いながら、一人一人の子どもを理解し、そのニーズに応えていくことができるようにするためには人的体制面での余裕が必要です。明らかに人が不足しています。
教育にはお金がかかります。日本の教育予算は先進国の中では最低水準です。教育や児童福祉の問題に関わっていると、この分野にどれほどお金が出にくいかを実感します。
安倍内閣は教育再生を最大のスローガンとしていますが、それは、子どもたちの教育に直接にかかわる現場に、どれだけまとまった予算を付けることができるかにかかっています。しかし、おそらく全く期待できず、ほとんどお金のかからない小手先の改革か、現場を混乱させる制度改革だけに止まると思いますが。
何とかしたいものですが、何かできないでしょうか?今年は、具体的なケースに関わりながら、もう少しそんなことも考えて見たいと思います。今のところ、全く見通しはありませんが。
 子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
清水克之(著), 佐藤拓代(著), 峯本耕治(著), 村井美紀(著), 山野良一(著), 松本伊智朗(編集) / 明石書店 / 2010年2月5日
<内容>
子ども虐待と貧困との関係を乳幼児期から青年期までの子どものライフステージに沿って明らかにする。執筆者のまなざしは、親の生活困難に向けられ、子どもと家族の社会的援助の必要性を説き、温かい。貴重なデータも多数掲載している。
 子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
小林美智子(著), 松本伊智朗(著) / 明石書店 / 2007年12月6日
<内容>
公権力の介入を求めるまで深刻化した子ども虐待。だが介入は虐待防止の切り札といえるのか。2005年の日本子ども虐待防止学会シンポジウムの記録を基に編まれた本書は、日英の経験をふまえ、虐待を防ぐために本当に必要な「ケアする社会」を構想する。
 スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
山野則子(編集), 峯本耕治(編集) / ミネルヴァ書房 / 2007年8月1日
<内容>
はじまったばかりのスクールソーシャルワーカーの活躍を描く。スクールカウンセラーや養護教諭とともに様々な問題に悩む親子に、社会的問題を含めて解決にあたる事例を紹介します。今までにない児童生徒へのアプローチに非常な関心がもたれています。
 子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
峯本耕治(編集) / 明石書店 / 2001年12月12日
<内容>
先進的なシステムをもつイギリスの児童虐待防止制度の詳細と、実際の運用状況を具体的に紹介する。ライン等も示し、問題点にも触れる。