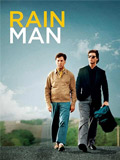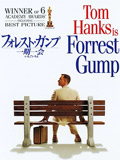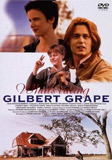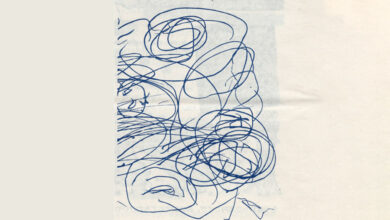発達障害について考える (1)

弁護士 峯本耕治
5月にまた衝撃的な事件が起こりました。会津若松で高校3年生の男子生徒が母親を殺害して、その切断した頭部を持参して警察に自首してきたという事件です。この少年は、県内でも有数の進学校の生徒で、中学校時代は勉強が良くできただけでなく、スポーツの部活でも活躍していたそうです。高校に入ってからは、友人関係に馴染めず、孤独感を募らせていたようですが、事件が一見して特異なものであることや、少年が高校生活において友人関係に馴染めていなかった等の情報から、少年がアスペルガー障害等の発達障害を抱えていた可能性が指摘されています。
現時点の限られた不正確な情報ではコメントすることも憚られますが、最近、一見特異な重大事件が起こるたびにアスペルガーや広汎性発達障害等の言葉を耳にするようになっていますので、今回と次回にわたって、少し発達障害について考えてみたいと思います。
昨日(6月16日)、私が代表をしているNPO法人TPC教育サポートセンターが、定期総会をかねて、発達障害に関するシンポジウムを開きました。基調講演の講師に北海道大学大学院教育学研究院附属子ども発達臨床研究センターの教授で、児童精神科医の田中康雄さんに来ていただきました。ご存じの方もいらっしゃると思いますが、田中先生は長年不登校の子どもの支援をされ、最近は発達障害を抱えた子どもの支援に中心的に携わっておられる児童精神科医で、その分野の第一人者と言って良い方です。
今回のシンポに来ていただこうと考えたのは、田中先生が、何よりも「子どもの視点に立って」というか、「子どもに寄り添うスタンス」で子どもや保護者に関わってこられた方で、謙虚さと共に、たいへん熱い思いを持った方だからです。イギリスから帰国直後にお会いしたことがあり、その後、05年12月に札幌で開かれた日本児童虐待防止学会のシンポジウムで一緒にパネラーをつとめる機会があったのですが、その時に田中先生のお話を聞いて、これは是非一度来てもらいたいと思い、今回その希望が実現したものです。
今回のシンポのテーマは、「発達障害 医学モデルからの脱出~育ち合う関係性を考えて」というものです。テーマから推測できるように、発達障害に対する医療診断の限界や弊害を踏まえて、「子どもの心を全て判ることは無理である」「誰もが不確実な中で生きていること」を前提として、「子どもにきちんと向き合う中で、子どもを理解していく必要性があること」、「子どものしんどさを個人の問題•課題として捉えるのではなく、子どもと子どもを取り巻く環境•人との関係性の中から生じてくるものであること」「そのため、障害を治療するのではなく、状況や関係性を修復することが必要であること」「その中で、子どもの心に触れ、心を認め、育ちを信じること」等のお話を、様々な具体例を示しながらしていただきました。
来て頂いた狙い通りの講演内容で、参加していた多数の教職員や臨床心理士等の専門職だけでなく、親の会等の保護者の皆さんにとっても、たいへんエンパワーされるお話だったと思います。
私自身にとっても、これまで教育や福祉、少年司法の現場で様々な発達障害的な症状を示している子どもたちに関わる中で、実感してきたことと本当にマッチするお話で、大変勉強になり、整理ができました。私は子どもの事件、大人の事件と問わず、色々なケースに関わる中で、人にはそれぞれ脳の個性があって、発達障害もその個性の延長線上で捉えられるのではないかと感じていたのですが(もちろん、環境の影響を大きく受けるわけですが)、田中先生からもそういう趣旨のお話がありました。「人の脳は誰でもADHD(注意欠陥多動性障害)系かアルペルガー系のどちらかの傾向を持っている」と冗談半分で話しておられましたが、私は明らかにADHD系です。
最初に紹介しました会津若松の事件についても、精神鑑定によって、仮に発達障害という診断が出たとしても、その診断によって何かがみえてくるわけではありません。しっかりと子どもと向き合うことによって、子どもが置かれていた環境、関係性の中からみえて子どものしんどさと発達上の課題を理解していく必要があるのだと思います。そうすれば、今回の事件も決して特異なものではないことが理解でき、本当に何が問題で、何が必要なのかの教訓を導き出せるものになるのだと思います。
次回は、田中先生のお話をもう少し具体的に紹介しながら、発達障害について、もう少し考えてみたいと思います。
 「発達障害」だけで子どもを見ないで その子の「不可解」を理解する (SB新書)
「発達障害」だけで子どもを見ないで その子の「不可解」を理解する (SB新書)
田中康雄(著) / SBクリエイティブ / 2019年12月6日
<内容>
自閉スペクトラム症、ADHD……
診断名よりも大切なこと
診断名はあくまでもその子の一部にしか過ぎません。「自閉スペクトラム症のAくん」「注意欠如•多動症(ADHD)のBちゃん」といった視点よりも、大切なのは、その子の目線にまで達して、気持ちを想像してみること。本書では、「発達障害」と診断される可能性のある子どもたち12のストーリーを例に、その子の気持ちを想像し、困っていることを探り、「仮の理解」を行う過程を解説。わが子の「不可解」な行動に、悩める親や支援者を応援する一冊です。
 もしかして私、大人の発達障害かもしれない!?
もしかして私、大人の発達障害かもしれない!?
田中康雄(著) / すばる舎 / 2011年2月22日
<内容>
どうしても、「片付けられない」「大事な物をなくしてしまう」「仕事の期限が守れない」「落ち着きがない」「思うようにいかないとパニックになる」「空気が読めないと言われる」……
子どもの頃から「苦手だな」と思うことがあった。それでも、とくに困らずそのまま大人になった人はたくさんいます。
しかし、こうした人の中には、社会に出てから「生きづらさ」が強くなり、悩み苦しむ人もいるのです。
「仕事や人間関係。がんばってるのになぜかうまくいかない」
それは、決して本人の努力不足ではなく、生来的に持っている発達のアンバランスさ、「発達障害」が関係しているのかもしれません。
「発達障害って、なに?」
「もしそうならどうすればいいの?」
本人と周囲の人、どちらの立場の人も、「心配だな」と思ったら、はじめに読んでほしい本です。
 子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
清水克之(著), 佐藤拓代(著), 峯本耕治(著), 村井美紀(著), 山野良一(著), 松本伊智朗(編集) / 明石書店 / 2010年2月5日
<内容>
子ども虐待と貧困との関係を乳幼児期から青年期までの子どものライフステージに沿って明らかにする。執筆者のまなざしは、親の生活困難に向けられ、子どもと家族の社会的援助の必要性を説き、温かい。貴重なデータも多数掲載している。
 子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
小林美智子(著), 松本伊智朗(著) / 明石書店 / 2007年12月6日
<内容>
公権力の介入を求めるまで深刻化した子ども虐待。だが介入は虐待防止の切り札といえるのか。2005年の日本子ども虐待防止学会シンポジウムの記録を基に編まれた本書は、日英の経験をふまえ、虐待を防ぐために本当に必要な「ケアする社会」を構想する。
 スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
山野則子(編集), 峯本耕治(編集) / ミネルヴァ書房 / 2007年8月1日
<内容>
はじまったばかりのスクールソーシャルワーカーの活躍を描く。スクールカウンセラーや養護教諭とともに様々な問題に悩む親子に、社会的問題を含めて解決にあたる事例を紹介します。今までにない児童生徒へのアプローチに非常な関心がもたれています。
 子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
峯本耕治(編集) / 明石書店 / 2001年12月12日
<内容>
先進的なシステムをもつイギリスの児童虐待防止制度の詳細と、実際の運用状況を具体的に紹介する。ライン等も示し、問題点にも触れる。
6月の映画サークル例会は「アスペルガー症候群」を題材にした実話に基づいた『モーツアルトとクジラ』でした。もしも機会がありましたら是非ご覧ください。『レインマン』『フォレスト•ガンプ』『i am sam』『ギルバート•グレイプ』もあわせてどうぞ。サークル誌の中に書籍より”苦難の旅が教えてくれた。愛するパートナーを惹きつける第一歩は自分自身の愛し方を知ることだ。”アスペルガー症候群であったといわれるアインシュタインの言葉に「常識とは18歳までに身につけた偏見のコレクションのことをいう」という言葉があります。あなたはADHD系それともアスペルガー系?皆それぞれに個性豊かに共存したいですね。 [か]
 モーツアルトとクジラ
モーツアルトとクジラ
ジョシュ•ハートネット(出演), ラダ•ミッチェル(出演), ピーター•ネス(監督) / 2006年4月14日公開
<内容>
アスペルガー症候群という悩みを抱えた男女が、障害や周囲の無理解を乗り越えながら愛をはぐくんでいく姿を繊細に描いたラブ•ストーリー。「レインマン」を手がけたロン•バスの脚本を、ノルウェー人監督ピーター•ネスが映画化。
 レインマン
レインマン
ダスティン•ホフマン(出演), トム•クルーズ(出演), バリー•レヴィンソン(監督) / 1988年12月16日公開
<内容>
事業に失敗して破産寸前のチャーリーのもとに、絶縁状態だった父親からの訃報が届く。
帰郷した彼は、父の遺産が匿名の受益者に贈られると聞きショックを受ける。
その受益者とはチャーリーがその存在さえ知らなかった自閉症の兄レイモンドだった……。
トム•クルーズ×ダスティン•ホフマンの豪華共演で放つ、珠玉のロード•ムービー。
 フォレスト•ガンプ
フォレスト•ガンプ
トム•ハンクス(出演), ロビン•ライト(出演), ロバート•ゼメキス(監督) / 1994年7月6日公開
<内容>
母子家庭で育ったフォレスト•ガンプは、知能指数は人に劣るものの、並外れた足の速さと誠実な人柄の持ち主。激動の時代の中、その俊足と優しさで周囲の人たちを助け、また自身も助けられながら、彼は波乱に富んだ人生を駆け抜けていく。
 i am sam
i am sam
ショーン•ペン(出演), ミシェル•ファイファー(出演), ジェシー•ネルソン(監督) / 2001年12月28日公開
<内容>
知的障害を抱えながらも男手ひとつで娘を育てるサム。しかし、成長に伴って子どもの知能の方が上回る。やがて、彼は家庭訪問に来たソーシャルワーカーに養育能力なしと判断され、娘を取り上げられてしまう。なおも愛娘と暮らしたいと願う彼は、女性弁護士と共に奮闘する。
 ギルバート•グレイプ
ギルバート•グレイプ
ジョニー•デップ(出演), レオナルド•ディカプリオ(出演), ラッセ•ハルストレム(監督) / 1993年12月25日公開
<内容>
アイオワ州の田舎町。ギルバートは食料品店で働きながら、知的障害を持つ弟と、夫の自殺から立ち直れず7年間も家を出たことのない肥満の母、2人の姉妹たちとの生活を支えていた。家族の世話に追われる日々に悶々とする彼は、ある日、トレーラー•ハウスで旅する女と出会う。