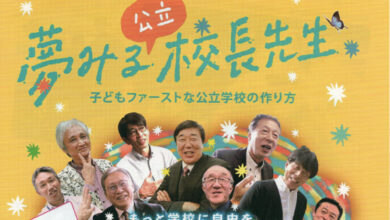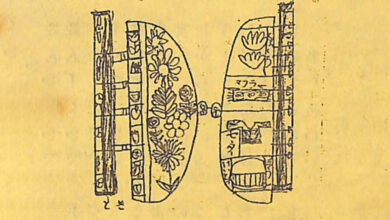子どもの発達のキーとなる自尊感情と基本的信頼感

弁護士 峯本耕治
1 子どもの貧困と虐待の本を出版しました。
以前からお話していた子どもの虐待と貧困に関する本をようやく出版することができました。書籍名は「子ども虐待と貧困 忘れられた子ども」のいない社会をめざして」(明石書店)です。子どもの貧困研究の第一人者の松本伊智朗さん(札幌学院大学)、保健所所長の佐藤拓代さん、児童相談所の山野良一さん、自立援助ホームの村井美紀さん、虐待防止行政の清水克之さんの共著です。この本は、2年前の12月に広島で行われた日本虐待防止学会の分科会(子どもの貧困と虐待)にパネラーとして参加したメンバーが、「せっかくだから熱い気持ちの間に本にしよう」ということになって書き始めたものですが、予想されたことですが、2年以上が経過してしまいました。
乳幼児期から学齢期、青少年期のライフステージにわたって、子どもの貧困と虐待の関係や、貧困から生じる虐待が子どもの成長発達にどのような影響を与えるのかを、それぞれの専門分野から、紹介しています。私は、その中で、「学校教育から見える子どもの貧困と虐待」のパートを書いています。学校教育から見える子どもの貧困については、松本さんらが出版されている「子どもの貧困」、阿部彩さんが岩波新書で出されている「子どもの貧困」をはじめとして、すぐれた本が多数出版されていますので、今回の本では、少し異なる問題意識で書いています。阿部彩さんが著書「子どもの貧困」の中で、「子ども期の貧困は、単なる学力や将来における職業、経済的な不利だけでなく、一生背負っていかなければならない不利をもたらす」という趣旨のことを書かれているのですが、私は、その「一生背負っていかなければならない不利=目に見えにくい不利」とは、貧困、そして、そこから生じる虐待がもたらす、子どもの「自尊感情•自己肯定感の低さ」、「人への基本的信頼感の低さ」であると考えています。子どもの発達にとって、「自尊感情•自己肯定感の大切さ」は一般的にしばしば言われているところですが、少年事件、児童虐待、学校における問題行動等の様々なケースに関わる中で、子どもたちの自尊感情•自己肯定感や人への基本的信頼感を具体的に育てることが、子どもたちの成長発達を支える上で、どれほど大切なことなのかを改めて実感させられてきました。それは単なる理念的なものであったり、抽象的なものではありません。子どもの成長発達を支える鍵となるものです。
この本の私のパートでは、貧困がもたらす「見えにくい不利」として、貧困自体が自尊感情•基本的信頼感を低下させる危険性を持っていること、それが虐待につながったとき、より明確な形で、それが現れてくること、そして、皮肉なことに、現在の学校現場にはそれを大きく低下させていくメカニズムがあること、それに対して、どういう対応やシステムが求められるかを書いています。機会があれば是非読んでいただければありがたいです。
今回のニュースには何を書こうかと悩んでいるのですが、この自尊感情•基本的信頼感の低下をテーマにしながら、貧困とは反対の家庭環境の中で育っている子どもたちの中でも、同じように自尊感情や信頼感を低下させやすい環境があることを、ある少年事件を通じてご紹介したいと思います。
2 ある少年事件で出会った子どもと家族
鑑別所で出会った少年Aは高校2年生で、事件の内容は、中学校時代の同じグループ仲間のXに対する傷害事件と大麻草の所持でした。その場には、同じグループ仲間のB,Cも一緒にいましたが、最終的に家庭裁判所に送られたのはAだけでした。
Aはグループのリーダー的存在で、Xが普段から約束を守らない等の理由でXに腹を立てていたところに、Xが他の友人に対してAの悪口を言っているという話を聞き、制裁を加えるということで呼び出して、暴力を加えたという事件でした。
Aの家族は、大企業に勤める父親、専業主婦の母親、国立大学生の兄、有名私立大学生の姉の5人家族で、両親は共に国立大出身の高学歴でした。
Aは小学校時代は成績も優秀で、真面目に頑張る優等生でした。親は非常に教育熱心で、特に、母親は本人が末っ子であったこともあって、子どもを手取り足取りバックアップし、Aもこれに一生懸命に応えて頑張ってきました。ところが、中学受験に失敗し、公立中学校に進学しました。当初は高校での私学受験を目標に頑張っていましたが、学力が思い通りに伸びない中で、学校生活においても無気力な態度を示すようになり、母親に対しても反発を始めました。中学2年の秋頃から、やんちゃなグループとのつながりができて、夜遊び等が見られ始めました。それでも、登校は続け、本人は友人と共に公立高校に進学することを希望していましたが、母親は何とか私学を受験させたいと思い、本人に私学受験を強く勧め続けました。他方、父親は時に手が出る非常に厳しい存在であったため、Aはやんちゃをしながらも父親に怒られることは極度に恐れていました。受験への不安もあって、再び母親の手取り足取りのサポートを受けながら短期間ですが、受験勉強をしました。その結果、両親や本人の本来の志望からは大きく落ちる高校でしたが、私立高校に合格しました。ところが、進学した私立高校では、校則等も厳しく、先生と合わず、友人関係においても馴染めなかったため、1年の夏休み明けから、学校に行けなくなり、昼夜逆転の生活を送るようになりました。中学校時代の仲間と再び付き合うようになり、夜遊びが始まり、明らかに荒れた生活を送るようになりました。その頃には、母親に対しても激しく反発するようになり、母親はお手上げの状態になり、全く注意することもできなくなっていました。父親に対しては恐怖感を持っていたため父親を極端に避け、たまに出会ったときには、怒る父親に激しく反発して怒鳴り合い、すぐに飛び出してしまうという状況でした。
事件は、このようなAの生活環境の中で起こったものでした。
3 「過プレッシャー型」というキーワード
このような家族環境や養育歴を見たとき、Aのしんどさは明らかでした。乗り越えることが難しい高学歴で社会的地位も備えた親と優秀な兄姉の存在。親からの高い期待。これらはいずれもAに対して、幼い時から強いプレッシャーとしてのしかかっていたと思われます。子どもは親の愛情を求め、「親の期待に応えたい」、「親に評価されたい」と強く思っています。Aも小学校時代は、まさに、この期待に応えて努力していたのですが、中学受験の失敗、公立中学での学力の伸び悩み等の挫折体験、親が感じたであろう失望感やAに対する評価の変化、プレッシャーのみがかかり続ける環境の中で、Aはどんどんしんどくなっていったのだと思われます。極端にプレッシャーが強い親子関係では、子どもはいつも親の顔色や評価を気にしなければならず、身体的虐待やネグレクト環境と同様に、安心して過ごすことができません。子どもは、親の期待やプレッシャーに応えて頑張ろうとしますが、そのプロセスよりも、とにかく結果を求められ、評価に晒されることになります。また、自発的な動機による努力や成果ではないため結果が出ていても、必ずしも自信につながりません。その結果、本当の意味での「自尊感情•自己有用感」や「人への基本的信頼感」が育ちにくくなるのです。それでも、子どもが親の期待や要求に応えることができている間は、問題は顕在化しにくいのですが、Aのように大きな挫折体験や挫折体験が重なって子どもの自尊感情が低下したところに、強いプレッシャーがかかり続けると、子どもは逃げ場のないしんどさの中で、親の愛情への疑問や不信感を抱くようになります。そして、自尊感情の低下や基本的信頼感の低下が強まることによって、ストレスの爆発や愛情要求の裏返しとしての激しい反発や攻撃、抑うつ的な症状等を示すことにつながっていくのです。親自身も乗り越えにくい存在であったことや、常に比較の対象とされる優秀な兄姉の存在、愛情を感じにくい極端に厳しい父親の対応などは、Aにとっては、期待に応えることが難しくなったときには、いずれも「自分だけが愛されていない」、「邪魔な存在だと思われている」等の思いを抱きやすく、Aの家庭環境は、特に自尊感情や基本的信頼感が育ちにくい環境にあったものと思われます。
いわゆる格差社会化が進む中で、家庭環境も「ネグレクト•放任型の家族」と「過保護•過干渉•過プレッシャー型の家族」に両極化してきていると言われています。どちらも、親子の愛着問題を生みやすく、結果として、子どもの自尊感情や人への基本的信頼感が育ちにくい環境を作ってしまうのです。
 子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
清水克之(著), 佐藤拓代(著), 峯本耕治(著), 村井美紀(著), 山野良一(著), 松本伊智朗(編集) / 明石書店 / 2010年2月5日
<内容>
子ども虐待と貧困との関係を乳幼児期から青年期までの子どものライフステージに沿って明らかにする。執筆者のまなざしは、親の生活困難に向けられ、子どもと家族の社会的援助の必要性を説き、温かい。貴重なデータも多数掲載している。
 子どもの貧困: 子ども時代のしあわせ平等のために
子どもの貧困: 子ども時代のしあわせ平等のために
浅井春夫(編集), 湯澤直美(編集), 松本伊智朗(編集) / 明石書店 / 2008年3月28日
<内容>
子ども時代に貧困であるということは、その子の人生にとってどんな意味をもたらすのでしょうか。貧困•格差問題のなかでも、貧困という視点からの研究がもっとも遅れているのが「子どもの貧困」です。本書は、福祉現場から「子どもの貧困」の実相をとらえ、家族との関係を解き明かします。世界的な研究を紹介するとともに、政策的提言をめざします。
 子どもの貧困: 日本の不公平を考える (岩波新書)
子どもの貧困: 日本の不公平を考える (岩波新書)
阿部彩(著) / 岩波書店 /2008年11月20日
<内容>
健康、学力、そして将来…。大人になっても続く、人生のスタートラインにおける「不利」。OECD諸国の中で第二位という日本の貧困の現実を前に、子どもの貧困の定義、測定方法、そして、さまざまな「不利」と貧困の関係を、豊富なデータをもとに検証する。貧困の世代間連鎖を断つために本当に必要な「子ども対策」とは何か。
 子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
小林美智子(著), 松本伊智朗(著) / 明石書店 / 2007年12月6日
<内容>
公権力の介入を求めるまで深刻化した子ども虐待。だが介入は虐待防止の切り札といえるのか。2005年の日本子ども虐待防止学会シンポジウムの記録を基に編まれた本書は、日英の経験をふまえ、虐待を防ぐために本当に必要な「ケアする社会」を構想する。
 スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
山野則子(編集), 峯本耕治(編集) / ミネルヴァ書房 / 2007年8月1日
<内容>
はじまったばかりのスクールソーシャルワーカーの活躍を描く。スクールカウンセラーや養護教諭とともに様々な問題に悩む親子に、社会的問題を含めて解決にあたる事例を紹介します。今までにない児童生徒へのアプローチに非常な関心がもたれています。
 子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
峯本耕治(編集) / 明石書店 / 2001年12月12日
<内容>
先進的なシステムをもつイギリスの児童虐待防止制度の詳細と、実際の運用状況を具体的に紹介する。ライン等も示し、問題点にも触れる。
Sponsored Link