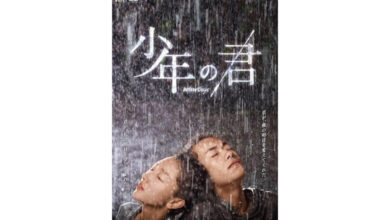勝手にシネマ『私はフェリシテ』
塩見 正道
『私はフェリシテ』(原題:Félicité / 2007年 / フランス, ベルギーほか合作)
監督・脚本 アラン・ゴミス
この映画の魅力は言葉ではちょっと言い表せない。だからここで書こうということ自体矛盾しているのだが、やはり凄い。なにを凄いと感じたのか、そのことを伝えたい。
まず、ドラマの重要な構成要素であるストーリーがない。とは言っても、ストーリーらしきものはある。主人公フェリシテはコンゴの首都キンシャサのスラムの酒場で歌っている女性。息子が交通事故で病院に担ぎ込まれたという連絡が入り、あわてて駆けつけるが、息子はなんの手当てもされずにベッドにほったらかしにされている。治療を受けるにはお金を先に払いなさいと言われ、お金の無心に、別れた夫や兄や母を訪ねて嫌がられる。そのうち息子は壊疽を起し、無断で足を切断される。
簡単に社会批判か感動物語に仕上げられるこの素材を、この映画はそうは扱わない。近代以後のドラマでは意思をもつ主人公の行動が葛藤を生み、それがドラマの推進力となる。しかしこの映画では、彼女を取り巻き、拘束している環境は主人公の意思と無関係に存在する。現代建築が立ち並ぶ都会のなかにある未舗装の道路とバラック。その無感情な対置。その圧倒的非対称が無言で語りかける。主人公の心情を表す言葉はいっさいない。
フェリシテはコンゴの民族音楽の歌い手で、毎夜、打楽器のリズムにあわせて歌っている。このカサイ・オールスターズによるワールド・ミュージックとキンバンギスト・オーケストラによるアルヴォ・ペルトのシンフォニーがこれまた互いに関係なく演奏されていく。
主役は音楽と環境である。音楽が彼女の内面を、環境が現実を表現する。人間世界の分裂をこれほどシャープに表現した映画を私は知らない。
この現実のなかで、彼女は歌い続け、男と女は愛を交わし、息子は杖をついて歩き始める。ここには、嘆きすらも突き抜けた人間の生の逞しさがある。
監督はアラン・ゴミス。1972年、フランス生まれのセネガル系フランス人で、本作が長編4作目といわれるが、他の作品を私は見ていない。
フェリシテFélicitéという原題は「至福」を意味するフランス語だが、映画のなかで、母が初めの名前は違っていたが、幼いころに死んで埋葬しようとしていたときに生き返ったので、フェリシテと名前をつけたと語っている。この逸話からすると、どこか(復活)を暗示させる。アルヴォ・ペルトの曲は受難曲のような響きであり、この映画自体が壮大な宇宙を感じさせるが、にもかかわらず、ほとばしるような生命力の力強さが私には心地よかった。