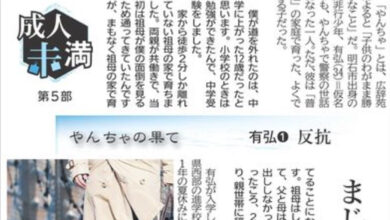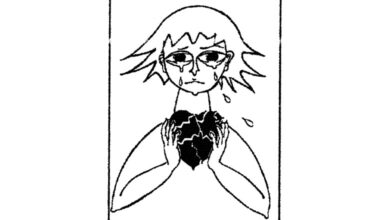少年の冤罪
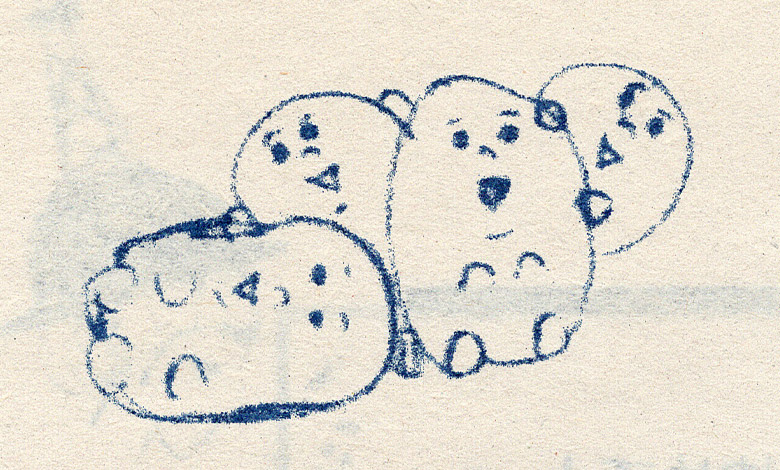
弁護士 野口善國
1 はじめに
冤罪事件の原稿をと依頼を受けて少々困りました。
というのも、私が冤罪事件と思う事件を受任したのは、おそらくこれまで10件になるかならないかで、それもほとんどが少年事件だからです。
私は、今回、少年の冤罪事件を中心に述べさせていただきます。
冤罪とは、無実の人が罪に問われることを言います。統計によれば、裁判所の刑事事件のうち1000件に2件か3件の事件について無罪が言い渡されています。1人の被告が何件か起訴され、そのうちの1件だけが無罪という場合も多いので、被告人が全く罪に問われなかったという「完全無罪」はもっと少ないと言えます。しかし、実際、冤罪の人が見過ごされて有罪になってしまう人の数は「完全無罪」を得られた人よりももっともっといるのではないかというのが私の実感です。
2 少年事件におけるいくつかの冤罪の事例
特に少年は、弁解する能力が低かったり、大人を信用していなかったりで、捜査員に真実を伝えられないままとなることがあり、少年事件の捜査は成人と比べると不十分なことが多く、少年は成人よりも冤罪に陥る危険が大きいと言えます。
少年が冤罪に陥りやすい理由をいくつかの事例を挙げて説明してみようと思います。
① 八王子暴走族事件
Aという暴走族の少年たちが暴走行為で逮捕されました。少年たちは、他にも暴走行為をしていた少年はいないかと聞かれ、対立関係にあったBというグループの少年たちの名を挙げました。Aグループの少年たちは日頃からBグループの少年たちが暴走しているのをよく目撃していました。従って、走っている順番、オートバイの特徴などを非常によくおぼえており、とてもリアルに説明しました。警察官たちはその説明を信じ込みました。そこでBグループの少年たちが次々に逮捕されていきました。Xという少年はBグループの中心人物でした。Xは家が貧しく、弁護士に頼む費用がないということで、弁護士にも相談せず、とうとう泣く泣く少年院に送致されました。YもBグループのメンバーであり、逮捕こそされなかったけれど全く覚えのない暴走行為で家裁に送致されました。我々はYの付添人になりました。私たち付添人は家裁の裁判官に事情を説明に行きました。すると裁判官が真っ赤になって、机の上の書類を叩いて、こう言ったのです。
「こんなに証拠が揃っているのに、あなた方は何を言っているのですか」
また少年の話を一言も聞いていないのに、裁判官はこのような予断を持っていたのです。
かなりの刑事裁判官は検察官の捜査や起訴には間違いがないと信じ込んでいます。全くの無罪事件が1000に1つか2つしかないとするならば、裁判官生活の間に、一度も無罪判決を書かない裁判官も多いと思われます。
また、地方裁判所における刑事事件においては、起訴状1本主義といって、第1回期日までに裁判官は一切証拠を見ることはできません。更に第1回期日以降にも、原則として、弁護人が同意した書面を除いて、検察側の証拠書類の裁判所への提出は厳しく制限されます。勿論その逆も然りです。
ところが、家裁の少年審判では、裁判官は審判が始まる前に裁判官が全ての書類を見ることができます。家裁の裁判官は通常の刑事裁判官よりもずっと予断を持ちやすいのです。
Yは取り調べ中に警察官から脅迫を受けていました。暴走行為をしていないとYが言うと、取り調べの警察官は道場へ連れて行って痛めつけるとか、逮捕するなどと脅かしていました。このことを付添人が裁判官に話しても、裁判官は全く取り合ってくれませんでした。しかし、Yはこの取り調べをこっそり録音しており、アリバイもあったので、「非行事実なし」(無罪)の審判を得ることができました。
② 草加女子中学生殺人事件
東京周辺の草加市というところで女子中学生が殺害される事件がおきました。この時逮捕されたCという少年は知的障害を持っていました。Cは無罪だったので逮捕当時はそう主張したのですが、取調官に威迫されて本当のことを言えなくなってしまいました。Cは大人全体に不信感を持ってしまい、何と弁護士にまで本当のことを言えませんでした。弁護士に本当のことを言えたのは、担当した弁護士が交代し、新たに弁護士がついてからのことでした。
少年が自白しているからと言って、それをそのまま鵜呑みにするには大変危険なのです。
③ ある窃盗
事件数年前、E、Fの2人の少年が自販機荒らしの疑いで逮捕されました。少年らの言い分を聞いてみると、かなりはっきりしたアリバイがありました。更に、少年らが取調官に述べた供述調書の内容も全く不自然なものでした。自販機の小銭は溝に捨てたということでしたが、捨てること自体が不自然ですし、溝から小銭は全く発見されませんでした。小銭の入ったケースは港に捨てたということでしたが、それも見つかりませんでした。その上、目撃者の証言も曖昧で、裁判所への出頭も拒んだのです。
この事件では、捜査の杜撰さが目立ちました。警察官の捜査は通常検事がチェックし、その上で家裁に送致することになっています。しかし、神戸程度の都会でも少年事件担当の検事は1人しかいません。通常の窃盗のような重大と言い難い事件についてまで、検事が細部までチェックすることは不可能です。警察署においても、成人の事件に比べてみれば、少年事件の捜査体制は手薄です。
④ 綾瀬母子殺し事件
東京の綾瀬というところで母と幼い子が殺害される事件が起きました。
Dという少年が犯人として逮捕されました。幸いにも付添人(弁護人)団の努力でアリバイの証人が見つかりました。ところが審判の前日、警察はその証人をホテルに軟禁してしまいました。付添人団は裁判所に対し、証人の人身保護命令を申立て、大々的にマスコミに報道させました。その結果、証人が出廷し、少年の無実が明らかになりました。
捜査機関はいったん「クロ」と思いこむと、いかなる手段を使ってもその主張を通そうとします。
3 冤罪と闘う
どうやって我々は冤罪をはらしてきたのか。
私が冤罪の証明に成功したのは、成人で1件ある他は全て少年で5件しかないので、他事件での教訓を含めて述べてみたいと思います。
① まず本人の言い分を徹底的に聞く
これは成人の事件でも同じでしょうが、少年の場合には特に曖昧な表現や不必要な話が多く出ます。それを辛抱強く聞いて、確かめていき、何が真実かを見極める作業が必要です。
② 現場100回
現場に何度も行き、捜査段階の供述調書と矛盾する状況はないか、少年の述べていることが裏付けされるか再々確認する必要があるのは、成人の冤罪事件と同じです。証拠物の点検も同様です。
③ 審判の準備
少年の審判は、鑑別所に入所してから4~8週間で行なわれます。1回限りに行なわれるのが通常です。
特別に2回以上審判を開いてもらうことは可能ですが、いずれにしろ短期間のうちに①、②のことをやり終えて審判に臨まねばなりません。そのためにはかなりの人数の付添人(弁護人)を揃えて手分けして作業をする必要も出てきますし、他の仕事もある程度犠牲にして集中的に取り組まねばなりません。
④ 尋問の工夫
刑事事件の尋問の仕方については、秋田先生たちの「実践! 刑事証人尋問技術」(現代人文社)をご覧になっていただきたいと思います。
少年に対する尋問は、緊張をほぐすようにした上で、わかりやすい言葉を使うなどという工夫が必要です。また、いくら練習したからと言って、少年が期待するように話してくれるとは限りません。審判期日前に、調査官によく説明し、納得してもらい、裁判官とのカンファレンスを十分にしておく必要があるでしょう。
刑事処分相当という家裁の判断がなされると、地方裁判所に起訴され、裁判員裁判を受ける可能性が高くなります。そうなると審理の実際の進み方は大人の刑事事件とあまり変わりありません。
4 冤罪をどうやって減らすのか
人間のやることですから常に誤りのない制度というものは現実には不可能と思われます。しかし、冤罪を今より減らすことは可能です。刑事訴訟法が厳格に守られているとすれば、冤罪がずっと少なくなるというのが弁護士の実感です。取り調べの可視化というのは一言でいえば捜査機関の被告人の権利に関する刑事訴訟法の規定を守らせるためです。
しかしそのことは法曹関係者の努力だけでは実現はなかなか難しいのです。
警察はよほど自己の過失が明白にならぬ限り冤罪が判明しても捜査の適正を言い立てています。検察庁もつい最近まで、違法捜査の抑制には積極的ではありませんでした。
これらのことに対し世論の批判はあるものの、その批判の声は国民全体の声とまでは言えないのではないでしょうか。それは、マスコミも含めて世の中の人々の多くは、逮捕された者は極めた怪しい人物と捉え、被告人ともなれば、自分たち善良な市民とは別の存在であると考えているからではないでしょうか。
犯罪者をとにかく見つけ出して厳罰にすることが世の中のためであり、自分たちのためでもあると多くの人々が信じ込んでいるのではないでしょうか。被疑者、被告人は自分たちとは無関係な存在である。犯罪者はまともな人間ではない。思想とも言えないこのプリミティブな人々の感覚こそが冤罪を生み出す遠因なのではないでしょうか。
犯罪者はそれ程特別な人たちではなく、被疑者や被告人には誰でもなり得るという感覚を人々がもつようになれば、捜査機関もより人権を尊重した捜査方法をとらざるを得なくなります。
マスコミは残虐な犯罪行為については、詳細に報道しても、その人となりや犯行の原因については突っ込みの浅い報道が目立ちます。私たちは罪を犯した人をモンスターではなく、1人の人間として理解するよう努めねばならないと思います。
以上
 実践! 刑事証人尋問技術ー事例から学ぶ尋問のダイヤモンドルール(DVD付) (GENJIN刑事弁護シリーズ(11))
実践! 刑事証人尋問技術ー事例から学ぶ尋問のダイヤモンドルール(DVD付) (GENJIN刑事弁護シリーズ(11))
ダイヤモンドルール研究会ワーキンググループ(著) / 現代人文社 / 2009年4月20日
<内容>
刑事尋問で成功するための「ダイヤモンドルール」を抽出して、解説する。付録DVDでは、ダイヤモンドルールを用いない場合と用いた場合をそれぞれ実演。本とDVDで学んで、あなたも尋問の達人に。
 親をせめるな: わが子の非行に悩む親たち、親を応援する人たちへのエール
親をせめるな: わが子の非行に悩む親たち、親を応援する人たちへのエール
野口善國(著) / 教育史料出版会 / 2009年6月1日
 歌を忘れたカナリヤたち―子どもは必ず立ち直る
歌を忘れたカナリヤたち―子どもは必ず立ち直る
野口善國(著) / 共同通信社 / 2005年12月25日
<内容>
少年法を改正し、厳罰化を進める動きが出る中、神戸連続児童殺傷事件で少年Aの弁護を担当した弁護士が、少年法再改正の動きに疑問を呈す。切り捨て社会へ警鐘を鳴らし、愛とゆとりのある社会と家庭の再建を訴える。
 それでも少年を罰しますか
それでも少年を罰しますか
野口善國(著) / 共同通信社 / 1998年12月1日
<内容>
神戸連続児童殺傷事件の弁護団長が初めて明かす「少年A」の実像。少年法の厳罰化では非行はなくならない。
 どうなる丸刈•校則 (ヒューマンブックレット9)
どうなる丸刈•校則 (ヒューマンブックレット9)
野口善國(著) / 兵庫人権問題研究所 / 1991年1月1日
 子どもが育つ家庭づくり: 弁護士とカウンセラー夫婦の子育て論
子どもが育つ家庭づくり: 弁護士とカウンセラー夫婦の子育て論
野口善國(著), 野口喜美子(著) / 教育史料出版会 / 1989年1月1日
<内容>
非行•いじめ•登校拒否…。現代の子育てには心配がいっぱい。子どもを健やかに育むために、少年問題の専門家夫婦がそれぞの立場から、豊富な事例にわが子の子育てのエピソードも交えて、子どもの自立の芽を育む家庭づくりを具体的にアドバイス。
 3訂版 個別労働紛争あっせん代理実務マニュアル
3訂版 個別労働紛争あっせん代理実務マニュアル
前田欣也(著), 野口善國(監修) / 日本法令;3訂版 / 2021年4月18日
<内容>
あっせん代理、補佐人業務に携わる専門家と紛争解決手続代理業務試験受験者が押さえておきたい申立書•答弁書の書き方、民事訴訟法の知識、必須判例をやさしく解説。
2016年5月の改訂版発行以降の新たな事例や、同一労働同一賃金、セクシュアル•ハラスメントにかかわる新たな判決などを解説に加えた3訂版。