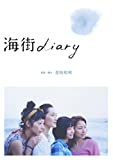勝手にシネマ『海街diary』
塩見 正道
『海街diary』(2015年 / 日本)
監督・脚本:是枝裕和
原作:吉田秋生『海街diary』(小学館)
出演:綾瀬はるか、長澤まさみ、夏帆、広瀬すず
是枝裕和監督の新作『海街 diary』は、父母が離婚し祖母に育てられた三姉妹が、父の死をきっかけに遺された腹違いの妹すず(広瀬すず)と一緒に暮らし始める物語です。お葬式に始まりお葬式に終わる一風変わった構成ですが、4人の新たな生活が始まる爽やかな余韻が残こる作品です。
爽やかさの最大の要因は、妹すずの真っ直ぐな性格にあります。そんな彼女の性格を見ただけで三姉妹を捨てた父がいい人であったことが分かります。それは他の三姉妹にも言えることで、この映画の主人公たちはいじけたところがありません。幼い時から大切に育てられたと思われます。北鎌倉の古い日本家屋を舞台に、四季の移り変わりとともに刻まれていく生活が丁寧に描かれます。死んだ父や祖母は登場せず、四姉妹の会話のなかで、直接的あるいは間接的に、各々の記憶あるいは顔つきや性格として、さりげなく浮かび上がるだけです。
この映画には原作(コミック)があります。ほゞ原作どおりですが、映画の方が長女(綾瀬はるか)の比重が重いです。ドラマチックな演出はいっさい排除されているので気づきにくいですが、この作品に埋め込まれている重要なテーマは「不倫の恋」です。
はじめ「不倫」は、父が母以外の女の人を好きになって家を出たという形で表れていますが、半ばで、長女の「秘密」が明らかにされます。長女は父を娘としてと同時に、反対側から、つまり妻のある男性を好きになった女性の側からも見ているわけです。彼女はその二重性による人格の分裂を封印して生きています。しかしすずと一緒に住むようになって、意識せざるを得なくなっていきます。
この物語の中で、長女は男性からの結婚の申し出を断り別れる決断をします。この決断を私たち観客は違和感なく受け容れてしまうのですが、そもそも彼女には男性との新生活を選ぶという自由はなかったのではないでしょうか。
もちろん「不倫」は望ましいものではありません。しかし、人間はそれほど自由ではありません。恋に落ちたとき、相手に配偶者がいるかいないか、あるいは異性かどうか、それは自由ではありません。
もし長女が男性との結婚を決意する展開だとしたらどうなっていたでしょう。彼女の「不倫」が明らかになり、妹たちの姉に対する絶対的ともいえる尊敬は消え去るでしょう。長女が家を出ることをきっかけに妹たちもやがて別々の生活へと向かうに違いありません。
そう推測するのは、すずの母が、この物語の中でただ一人「許されていない」からです。
長女は自分の性を肯定できません。私は、そこが悲しい。
ここにこの映画の盲点があるように思います。