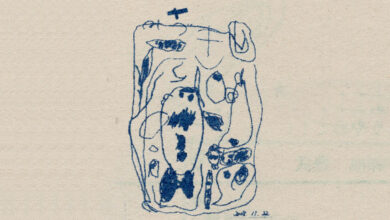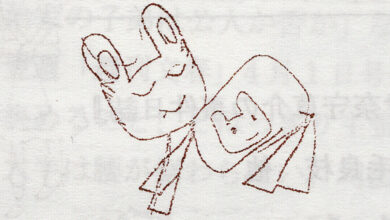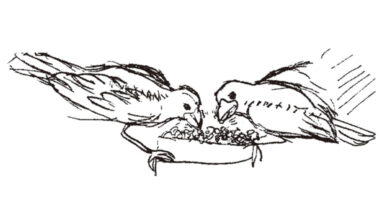子どもも学校もヘルプの声を!
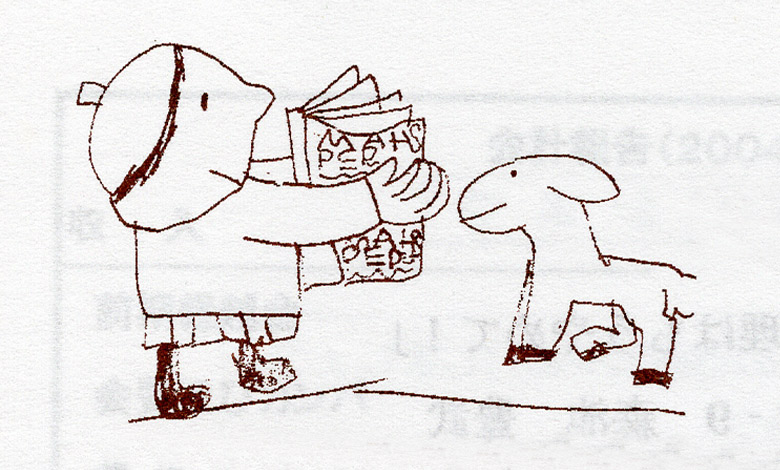
弁護士 峯本耕治
前2回は岸和田の児童虐待事件を取り上げましたが、今回も引き続いて、虐待ケースに取り組む上での学校の抱える困難さとサポートについて書きたいと思います。
日本の場合、就学年齢に達した子どもはほぼ全員学校に在籍していますし、実際に子どもたちは、家庭に次いで、時には家庭以上に長い時間を学校で過ごしています。必然的に、学校は虐待の発見機関として重要な役割を期待されています。発見だけでなく、発見された後の学校の役割も大変重要です。虐待というと、すぐに子どもが親から分離されるイメージがありますが、実際には、施設入所等により親子が分離されるのは10%以下で、多くは虐待が発見されても、在宅の支援が行われ、子どもは家庭での生活を続け、学校にも来続けます。ですから、学校には、普段の学校生活の中での子どもの安全のチェックや、居場所作り、自尊心の育成や情緒的な愛着関係の補充など、精神面でのケアにおいて大変重要な役割が期待されることになります。
しかし、岸和田事件でも明らかになったように、学校が、虐待の発見機関としての役割、子どものケア機関として役割を果たすことは、決して簡単なことではありません。
困難さの第1は、前回も紹介しましたようにシグナル発見の難しさです。虐待を受けている子どものシグナルは、多くの場合、「可哀想な症状」として現れるのではなく、「落ち着きがない」「切れやすい」「すぐパニックになる」「暴力的だ」等の問題行動として現れることが多いからです。そのために、どうしても、その厄介さに目が奪われ、問題行動への対応に追われ、その背景•原因にある虐待や不適切な養育環境の問題を意識できないことが多いのです。その結果、教師が対応を誤り、子どもがますます居場所を失い、問題行動がエスカレートしたり、非行につながっていってしまうことが少なくありません。最近、学校に呼ばれてケース会議に参加する機会が増えてきましたが、深刻な問題行動ケースの場合には、非常に高い確率で、虐待•ネグレクト、DV、極端な過保護•過干渉、過度な期待等による心理的支配等の不適切な養育環境の問題が背景に存在しています。理念的•情緒的にではなく、現実的な評価として、子どもたちの問題行動は、子どもたちのヘルプの声です。実際のケースに触れれば触れるほど、家庭環境や親子関係のあり方が子どもたちの行動や成長•発達に与える影響の大きさに本当に驚かされます。子どもの抱える問題の背景•原因をきちんと見極め、ケースの見立てを行うこと=子どもを理解すること=アセスメントすることの大切さを実感しますが、残念ながら、現在の学校現場には、このアセスメント力が十分にあるとは言えません。このアセスメント力を高めるためには、学校教育の中に、何らかの形で福祉的なサポートが必要になっています。
もう一つの困難さは、教職員が虐待の存在を疑っても、自信を持って行動できないことです。岸和田事件でもそうでしたように、教職員の中には、虐待やネグレクトの存在を疑い、「何とかしないといけない」と感じている方が少なくありません。しかし、いざ児童相談所に通告したり、他機関との連携を考えないといけないということになると、ほとんどの教職員が大きな躊躇を感じることになります。「これは虐待なのか、しつけの範囲なのか?」「このケースは、いったいどれくらい深刻なケースなのだろうか?通告しても、大した問題ではないと、相手にされなかったらどうしよう。」「通告した後、いったい、どんな風に展開していくのか?大ごとになったらどうしよう。」「子どもが親から切り離されてしまうのだろうか?」「学校から通告があったとわかったら、親は学校に対して激しく攻撃してくるのではないか」自分の判断に自信がもてず、また、見通しがもてないために、こんな心配や不安が頭の中で渦巻くのです。こんな心配や不安にとりつかれた時に、一人で抱え込んでいたら、絶対に積極的な行動を取ることはできません。その結果、岸和田事件でもそうであったように、担任教師や生徒指導教師が、子どもに会えないままに、大きな不安とストレスにさいなまれながら、いつまでも家庭訪問を繰り返してしまうというような事態が生じてしまうのです。そして、このような不安や心配は、決して特別なものではなく、ほとんどの教職員が程度の違いはあっても抱くものです。
こんな心配や不安を抱いたときに、学校•教職員が気軽に相談できる専門家のネットワークがあれば、たとえば、「これは深刻なケースの可能性がありますから、必ず、児童相談所に動いてもらってください」「学校の判断で良いと思いますよ」「こういうケースなら、こういう風に展開していく可能性があります」等のアドバイスを受けることができます。ちょっとしたアドバイスによって教職員は自信を持って行動することができ、そして、スキルを高めていくことができます。
今、学校現場には、こういうサポートシステムが本当に必要になっています。そのために、教職員自身が一人で抱え込むことなく、また、学校として抱え込むことなく、ヘルプの声を上げていくことが本当に必要になっています。
 子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
清水克之(著), 佐藤拓代(著), 峯本耕治(著), 村井美紀(著), 山野良一(著), 松本伊智朗(編集) / 明石書店 / 2010年2月5日
<内容>
子ども虐待と貧困との関係を乳幼児期から青年期までの子どものライフステージに沿って明らかにする。執筆者のまなざしは、親の生活困難に向けられ、子どもと家族の社会的援助の必要性を説き、温かい。貴重なデータも多数掲載している。
 子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
小林美智子(著), 松本伊智朗(著) / 明石書店 / 2007年12月6日
<内容>
公権力の介入を求めるまで深刻化した子ども虐待。だが介入は虐待防止の切り札といえるのか。2005年の日本子ども虐待防止学会シンポジウムの記録を基に編まれた本書は、日英の経験をふまえ、虐待を防ぐために本当に必要な「ケアする社会」を構想する。
 スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
山野則子(編集), 峯本耕治(編集) / ミネルヴァ書房 / 2007年8月1日
<内容>
はじまったばかりのスクールソーシャルワーカーの活躍を描く。スクールカウンセラーや養護教諭とともに様々な問題に悩む親子に、社会的問題を含めて解決にあたる事例を紹介します。今までにない児童生徒へのアプローチに非常な関心がもたれています。
 子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
峯本耕治(編集) / 明石書店 / 2001年12月12日
<内容>
先進的なシステムをもつイギリスの児童虐待防止制度の詳細と、実際の運用状況を具体的に紹介する。ライン等も示し、問題点にも触れる。