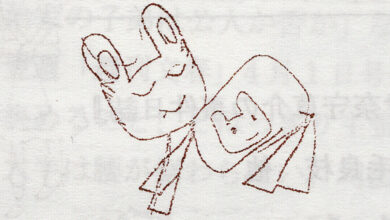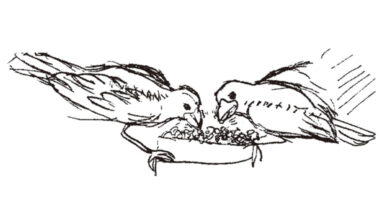「子どもの貧困と学校教育」についてもう少し考えてみると
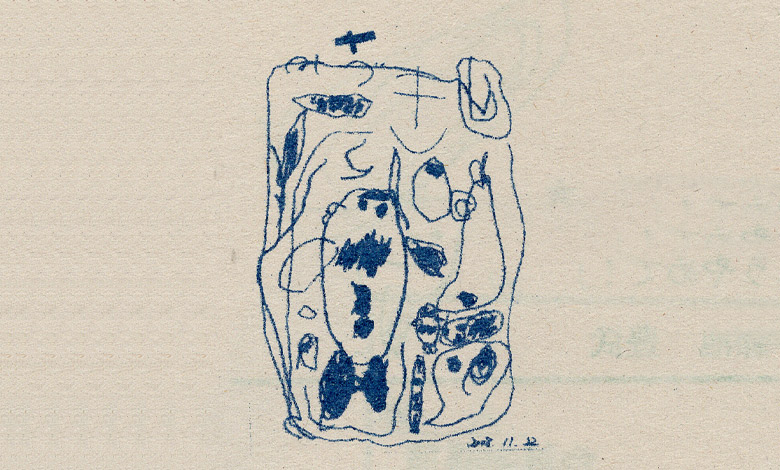
弁護士 峯本耕治
前号では、TPC教育サポートセンターで行った松本伊智朗(札幌学院大学教授)さんの講演内容を紹介しながら「子どもの貧困」について書きましたが、今回は前号に引き続いて、「子どもの貧困と学校教育」について、もう少し詳しく、考えて見たいと思います。
松本さんは、「日本における『子どもの貧困』問題が相当深刻な状況となっており、それが学校教育を通じて、子どもの成長発達に重大な影響を与える事態になっている」として、具体的な影響の一つとして、「教育費負担の家族依存立が高い中で、貧困が将来の選択肢を著しく狭め、格差の固定化につながっている」という点を挙げています。
文部科学省の調査によると、子どもを幼稚園から大学まで公立の学校に通わせた場合には818万円、すべて私立なら1563万円が必要になるという結果が出ています。また、保護者が支出した学習費総額は、年額で小学校は33万4134円、中学校は47万1752円に上っています。そのうち、学年集金額派、小学校で約10万円、中学校で約17万円となっています(文部科学省「データからみる日本の教育(2006年)」。
このような中で、日本の就学援助額は極めて不十分なものに止まっています。学用品費•通学用品費は、小学校で年間1万3720円、中学校で2万3870円となっています。実費補助とされている修学旅行費は「補助対象範囲」が定められ、給付額の上限を決めている市町村もあります。しかも、2005年からは就学援助費が、それまでの特定財源から、小泉内閣の「三位一体改革」により一般財源化されたことに伴い、市町村毎に認定基準の引き下げが始まっています(例えば、生活保護基準の1.5倍から1.3倍、1.0倍等へ)。
このように、国際的に見ると、大学まで授業料が無料である国も少なくない中で、日本の教育費は格段に高く、しかも、公的援助は極めて限られたものとなっているため、教育費負担の家族依存率が極端に高くなっているのです。
少しでも経済的に余裕のある家庭では、中学校受験、更には、幼稚園から塾に行かせて小学校受験すら、ごく当たり前のこととなっています。小学校から、塾や予備校に通うことは全く珍しくなく、逆に塾に通わなければ、私学受験はできないことはもちろん、学校においても良い成績を取ることが難しくなっています。貧困の問題を抱えた家庭では、塾費用等を負担することは不可能で、必然的に大学に進学することが難しい状況に置かれます。
それどころか、日本では、無償である義務教育は中学校までで、高校から入学金や授業料の負担が始まります。現代社会においては、「高卒」は最低限度必要な学歴と言って良いと思いますが、その費用さえ家族の負担となっているのです。そのため、実際に、経済的にしんどい家庭が増加する中で、学費負担ができずに高校進学を諦めざるを得なかったり、高校進学後も学費が払えずに退学したり、私学から公立への転校を余儀なくされている子どもが珍しくなくなっています。
このように貧困問題は、子どもの将来の選択肢を著しく狭めることになり、それが確実に格差の固定につながっていくことになります。
将来の選択肢が制限されることに加え、もう一つの大きな影響として、貧困の問題を抱えると、子どもの体験や経験の機会も大きく制限されることになります。基本的な教育費すら負担することが難しい状況では、家族の旅行や遊び、スポーツ等にお金を支出する余裕はありません。また、人との出会いの場も限られてしまいます。身近な遊び場所や自然環境が激減した今の日本では、自然やスポーツを楽しむのにも全てお金が必要です。また、ある程度の年齢になると、塾や習い事に行かなければ、学校が終わってから友達と触れあうことも難しい状況すら生まれています。それどころか、就学援助額が限られているため、修学旅行の支度や小遣い、体験学習費等にも相当の費用がかかるため、就学援助や生活保護を受けている家庭においても参加が困難となるなど、学校教育の中においてすら、経験や体験の機会が制限される事態が生じているのです。
以上書いてきました「将来の選択肢の制限」と「経験や体験の機会の制限」は、ある意味で、貧困問題が子どもの成長発達に与える「見えやすい影響」と言って良いと思います。
しかし、子どもの貧困には、もう一つ、子どもの成長•発達に重大な影響を与える「見えにくい影響」があります。それは、「児童虐待」というスリットを通すことによって見えてくる影響で、しかも、学校教育を通して、より増幅されて現れてくる危険性を持っているものです。
貧困と虐待との関係については、日本では直接的な調査は行われていないようですが、母子保健に関わる調査の中で、①貧困が、母子家庭を中心とする一人親家庭に多いこと、②虐待と貧困との間に有意な関係があること、③特にネグレクトとの間に顕著な関係が認められること等が明らかになっています。
一般的な感覚としても、経済的なストレスが極端に高くなると、家庭内の対人関係上のトラブルも増加しDVや虐待が起こりやすい環境になることや、たとえば、昼夜のダブルワークを余儀なくされることによって、家事や子どもの養育に向き合う時間的•精神的余裕が無くなるなど、ネグレクト環境が生じやすいこと等は容易に理解できることです。実際に、市町村の虐待防止ネットワークに上がってくる虐待ケースを見ていますと、その半分以上に経済的要因が関係しているように思われます。
では、「貧困」が「虐待」という形で現れた時に、子どもの成長発達にどのような影響を与えることになるのでしょうか。
もちろん程度の違いはありますが、虐待環境に置かれた子どもには、様々な形で親子の愛着上の問題(これを「愛着障害」と呼びます)が生じます。これまでも何度かご紹介してきましたが、家庭において愛着上の問題を抱えた子どもは、学校現場において、様々な情緒•行動面の問題や症状を示します。最も基本的な症状は、授業中に立ち歩いたり、先生にまとわりつくなどの落ち着きのなさです。これは愛情要求の裏返しで、いわゆる「見て見て行動」や「試し行動」なのですが、学校では必然的に、怒られたり、指導を受けたり、注意されたりすることが多くなっていきます。その結果として、子どもは、少しずつ自尊感情•自己有用感と教師を含む大人への基本的信頼感を低下させていきます。自尊感情と基本亭信頼感の低下は必然的に、教師に対する反発を生み、それが続くと攻撃性が出て、暴力の学びを伴うと暴力性が出て、最終的には、居場所を失わせ、不適応を招きます。これが、虐待がもたらす愛着障害から生じる問題行動のエスカレートパターンと言って良いものです。
そして、問題行動がエスカレートする過程で、同時に、子どもは「学力面での早い段階からのドロップアウト」をはじめとして、「授業に集中できない、持続力がない」「嫌なことからすぐ逃避してしまう」「感情のコントロールができず、すぐに切れる」「ストレスの発散方法として、暴力の学びをしてしまっている」「被害妄想的になりやすい」「自分の気持ちや感情を表現することが苦手で、ストレスを抱え込みやすい」など、対人関係能力をはじめとして様々な発達課題を抱えることになります。
その意味で、子どもたちの問題行動は、愛着障害を背景にして、「自尊感情•自己有用感の低さと基本的信頼感の低さの現れ」であると共に、「これらの発達課題の表現」に他ならないものです。
愛着障害を抱えた子どもが集団の中に入った時に愛情を求めて落ち着きがなくなり、それに対して教師が指導したり叱ったりすることが多くなってしまうこと、結果として、子どもが自尊感情や基本的信頼感を低下させてしまい、反発や攻撃性が出てきてしまうことは、ごく自然なことです。そのため、教師の側に、そのことについての知識や配慮、対応スキルがなければ、問題行動のエスカレートパターンにはまってしまう危険性が非常に高くなります。極端な言い方をすれば、愛着上の問題を抱えた子どもが10人いれば、10人とも、一歩間違えれば、問題のエスカレートパターンにはまってしまうのです。
私は、子どもたちの非行や学校における問題行動ケースに多数関わってきましたが、きちんとアセスメントをすると、ほとんど全てのケースの背景に、程度の違いやタイプの違いはあっても、何らかの愛着障害環境が存在し、しかも、その中の相当割合が経済的なしんどさを背景要因に持つものでした。
愛着障害を抱えた子どもに対しては、本来、学校•教師は、より積極的に愛着関係を築き、また、発達課題に適切に対応することによって、積極的に発達保障していく必要があるのですが、前述したような子どもの問題行動や症状の厄介さ(対応の難しさ)から、むしろ逆に、愛着関係が崩れやすく、悪循環にはまって発達保障ができなくなる、という大変皮肉な状況が存在するのです。
この「貧困→虐待(愛着障害環境)→学校における問題行動•症状→学校における愛着の崩れ→学校不適応」という悪循環が、子どもの発達に対し大きな悪影響を与えることになるのですが、私たちが、このつながりを具体的に意識することは余りありません。
しかし、この「見えにくい影響」が、前述した「見えやすい影響」と併さって、子どもに大きなハンディキャップを負わせることになり、自立を妨げ、ひいては格差を固定化していくことになっているのです。
貧困の問題の解決は容易ではありません。しかし、少なくとも、学校教育の現場において、これらの「見えやすい影響」と「見えにくい影響」の双方を最小限度にする取り組みは十分に可能なことです。逆に言うと、「家庭の不利」を「子どもの不利」につなげないための鍵を握るのは、やはり、学校教育であると思います。
 子どもの貧困: 子ども時代のしあわせ平等のために
子どもの貧困: 子ども時代のしあわせ平等のために
浅井春夫(編集), 湯澤直美(編集), 松本伊智朗(編集) / 明石書店 / 2008年3月28日
<内容>
子ども時代に貧困であるということは、その子の人生にとってどんな意味をもたらすのでしょうか。貧困•格差問題のなかでも、貧困という視点からの研究がもっとも遅れているのが「子どもの貧困」です。本書は、福祉現場から「子どもの貧困」の実相をとらえ、家族との関係を解き明かします。世界的な研究を紹介するとともに、政策的提言をめざします。
 子どもと家族の貧困: 学際的調査からみえてきたこと
子どもと家族の貧困: 学際的調査からみえてきたこと
松本伊智朗(編集, 著), 鳥山まどか (著), 関あゆみ (著), 川田学 (著) / 法律文化社 / 2022年12月25日
<内容>
札幌市•北海道と北大研究チームによる、子どもとその保護者を対象とした大規模調査から、子育て家族の実態を多面的に明らかにし、「問題の構図」を再考する。貧困研究の専門家や教育を軸とした社会学•心理学の専門家による協働作業から、年齢段階に即した議論と考察を行い、新たな知見を提示。
 子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
清水克之(著), 佐藤拓代(著), 峯本耕治(著), 村井美紀(著), 山野良一(著), 松本伊智朗(編集) / 明石書店 / 2010年2月5日
<内容>
子ども虐待と貧困との関係を乳幼児期から青年期までの子どものライフステージに沿って明らかにする。執筆者のまなざしは、親の生活困難に向けられ、子どもと家族の社会的援助の必要性を説き、温かい。貴重なデータも多数掲載している。
 子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
小林美智子(著), 松本伊智朗(著) / 明石書店 / 2007年12月6日
<内容>
公権力の介入を求めるまで深刻化した子ども虐待。だが介入は虐待防止の切り札といえるのか。2005年の日本子ども虐待防止学会シンポジウムの記録を基に編まれた本書は、日英の経験をふまえ、虐待を防ぐために本当に必要な「ケアする社会」を構想する。
 スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
山野則子(編集), 峯本耕治(編集) / ミネルヴァ書房 / 2007年8月1日
<内容>
はじまったばかりのスクールソーシャルワーカーの活躍を描く。スクールカウンセラーや養護教諭とともに様々な問題に悩む親子に、社会的問題を含めて解決にあたる事例を紹介します。今までにない児童生徒へのアプローチに非常な関心がもたれています。
 子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
峯本耕治(編集) / 明石書店 / 2001年12月12日
<内容>
先進的なシステムをもつイギリスの児童虐待防止制度の詳細と、実際の運用状況を具体的に紹介する。ライン等も示し、問題点にも触れる。