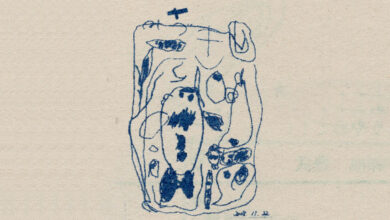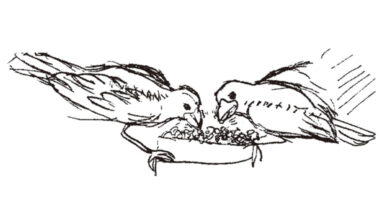岸和田児童虐待事件は、なぜ、起こったか? (2)
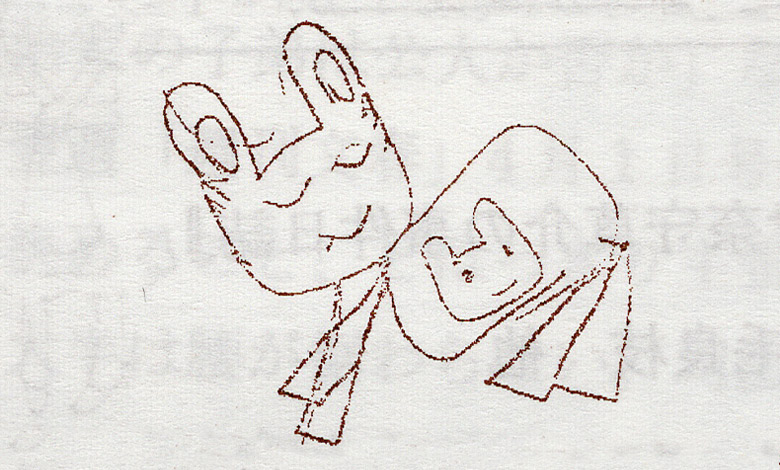
弁護士 峯本耕治
また、長崎でショッキングな事件が起こってしまいました。昨日、小学生の子どもを持つ保護者の方とお話をする機会があったのですが、「普通の、元気な、明るい、勉強もできる、子どもが、何のシグナルも見せないで、こんな事件を起こしてしまうのなら、本当に、子育てが不安で一杯になってしまう。」としみじみと話しておられたのが、大変、印象的でした。とりあえず、「詳しい事件を知れば、かならず、了解可能な背景•原因やプロセスがあります。シグナルも必ずあります。」と答えましたが、そうは言っても、こういう事件が続くと本当に不安になりますね。
少年事件だけでなく、児童虐待についても、岸和田事件以降、深刻な事件が続いています。警察が本気で立件し始めたことが、虐待事件が連日のようにマスコミを賑わしている一つの要因ですが、やはり事件自体も増えているのだと思います。もちろん、死亡事件等の重大事件は、氷山のほんの一角で、その裾野には、子どもの成長•発達に重大な影響を与えている虐待ケースが本当に多数存在しています。
今回はお約束したとおり、岸和田事件の背景にある構造的な要因について書きたいと思います。前回3つの要因を挙げましたので、それぞれについて簡単に説明します。
第1は、不登校の背景にある虐待の問題が想像以上に深刻な状況にあることです。
岸和田事件は、不登校の背景にある虐待の問題を、初めて大きくクローズアップさせることになりました。不登校というと、「学校でのいじめや体罰等が原因となって、行きたくても学校にいけない。親も何とか行ってもらいたいが、どうしても行けない」というタイプが典型的なものとして思いつきますが、他方で、家庭が原因となる不登校、特に、虐待が原因となった不登校が相当の割合で存在することが明らかになってきています。
文部科学省の調査によると、家庭に起因する不登校が約20%となっていますが、ある市町村の虐待防止ネットワークで行われた調査では30~40%に上っています。特に、ネグレクト(養育の怠慢•放棄•拒否)を広めにとらえると、その割合は、更に高くなると思われます。不登校のタイプの分類で見ると、遊び•非行型が中学生で急増するのですが(大阪府の調査では、小学校では1%の遊び非行型が中学校になると20%に急増)、問題行動や非行の背景に虐待があることが多いのと同様に、遊び•非行型不登校の大多数は、その背景に虐待•不適切な養育環境の問題を抱えていると考えられます。もちろん、中学校で、遊び•非行型が急増するのは、中学校になって突然問題が現れるわけではありません。小学校時代から不適切な養育環境が原因となって様々な問題症状を示しながらも、小学校には何とか登校できていた子どもが、中学校になって問題行動がエスカレートしたり、勉強のプレッシャーや生徒指導面のプレッシャーが強まる中で、学校での居場所を失い、外に出て非行につながってしまうことが原因だと考えられます。
岸和田事件の結果は特異なものですが、不登校の背景に虐待が存在することは決して珍しいことではありません。それにもかかわらず、これまで、社会的にも、学校においても、そのことが、ほとんどと言って良いほど認識されてこなかったことが岸和田事件の重要な背景となっています。
第2は、学校•教師にとって、虐待を背景に持つ不登校ケースへの対応が、一般的に困難であることです。
迅速な対応を余儀なくされる学校における問題行動と異なり、不登校は子どもが学校に来なくなり、教師の前から姿を消すわけですから、忙しい教師にとっては、どうしても、対応が後手に回りがちです。それでも、いじめ等の学校生活が原因となった不登校の場合には、親から何とかして欲しいという強い要請がありますので、教師は対応を求められることになりますが、虐待が原因となった不登校の場合には、親からの働きかけは、通常期待できません。それどころか、家庭訪問をしても、「子どもは会いたがっていない」などと親によって面会を拒否されることが珍しくありません。遊び•非行型の不登校の場合には、なおさら、教師の目も、子どもの問題の方ばかり向いてしまうので、親から「遊び回ってどうしようもない」などと言われてしまうと、それ以上つっこむことが難しくなってしまいます。
その結果、日常の教育活動に追われている教師としては、「虐待があり、早急な対応が必要である」という明確な認識を持てない限り、どうしても、対応が遅れてしまい、心配しながらも、そのままになってしまうということが珍しくありません。
岸和田事件でも、担任教師が繰り返し家庭訪問を行っていますが、結局、会えないままで終わってしまっています。
第3に、虐待の中でも特にネグレクト(養育の怠慢•拒否)については、学校•教師にとって特に対応が困難であり、児童相談所の体制も極めて不十分なものであることです。
以前にも紹介しましたが、ネグレクト(不適切な養育環境)の問題は大変深刻な状況にあり、平均すると一クラス2人程度はいると言われていますが、このネグレクトへの対応は、教師にとって、特に難しいものとなっています。
ネグレクトが疑われても、そのケースがどの程度の深刻さのものなのか、児童相談所に通告しないといけない程度のものなのか等の判断は、専門的な知識や経験のない教師にとって決して簡単なことではありません。また、通告したらどうなっていくのか等の見通しも持てないために、決断を躊躇してしまう事も少なくありません。しかも、いざ思い切って通告しても、児童相談所がすぐに動いてくれないということも少なくなく、そのような時にどう対応したら良いのかのノウハウも学校•教師は持っていません。
他方で児童相談所サイドから見ると、学校からネグレクトが疑われるケースが全て通告されることになると、児童相談所として到底対応できる人的体制にはありません。ソーシャルワーカーの数が欧米の10分の1から20分の1という数では、とてもネグレクトにまで手が回る状況にはないというのが実情です。
岸和田事件でも、虐待対応課への通告ではなかったとはいえ、相談が持ちかけられていたにもかかわらず、児童相談所が適切な対応ができなかった背景には、この人的体制の問題が間違いなくあります。
岸和田事件は、このような要因が重なって発生したものですが、もちろん、これらの要因は日本全国に共通するものです。その意味で、岸和田事件はどこで起こっても不思議でない事件です。
同じような事件が起きないようにするためにはどうしたら良いのか。次回は学校のサポートシステムの必要性という観点から、考えていることをお伝えしたいと思います。
 子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
清水克之(著), 佐藤拓代(著), 峯本耕治(著), 村井美紀(著), 山野良一(著), 松本伊智朗(編集) / 明石書店 / 2010年2月5日
<内容>
子ども虐待と貧困との関係を乳幼児期から青年期までの子どものライフステージに沿って明らかにする。執筆者のまなざしは、親の生活困難に向けられ、子どもと家族の社会的援助の必要性を説き、温かい。貴重なデータも多数掲載している。
 子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
小林美智子(著), 松本伊智朗(著) / 明石書店 / 2007年12月6日
<内容>
公権力の介入を求めるまで深刻化した子ども虐待。だが介入は虐待防止の切り札といえるのか。2005年の日本子ども虐待防止学会シンポジウムの記録を基に編まれた本書は、日英の経験をふまえ、虐待を防ぐために本当に必要な「ケアする社会」を構想する。
 スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
山野則子(編集), 峯本耕治(編集) / ミネルヴァ書房 / 2007年8月1日
<内容>
はじまったばかりのスクールソーシャルワーカーの活躍を描く。スクールカウンセラーや養護教諭とともに様々な問題に悩む親子に、社会的問題を含めて解決にあたる事例を紹介します。今までにない児童生徒へのアプローチに非常な関心がもたれています。
 子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
峯本耕治(編集) / 明石書店 / 2001年12月12日
<内容>
先進的なシステムをもつイギリスの児童虐待防止制度の詳細と、実際の運用状況を具体的に紹介する。ライン等も示し、問題点にも触れる。