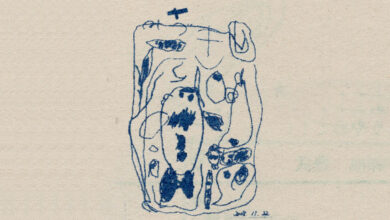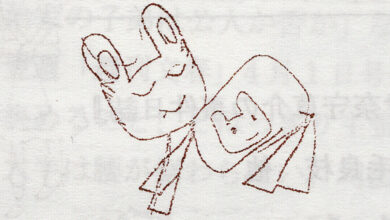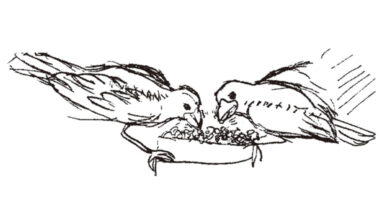なぜ、今、「子どもの貧困」が問題となるのか

弁護士 峯本耕治
前回少し触れたのですが、今年の春に「子どもの貧困」(浅井春夫, 松本伊智朗, 湯澤直美 共編著 明石書店)という書籍が出版されました。格差社会化が急速に進む中で、貧困の問題が再び議論されるようになってきていますが、その中でも、「子どもの貧困」に焦点を当てた初めてのものとして、今注目を集めています。私が代表をしているNPO法人TPC教育サポートセンターの9月例会に、代表編者の一人である松本伊智朗(札幌学院大学教授)さんに来てもらい、「子どもの貧困」についての講演会を持ちました。実は、松本さんは私のイギリス留学時代からの友人で、イギリスでは約1年にわたって児童虐待や教育問題を中心に、毎日のように一緒にリサーチに廻ったり、議論していた親しい友人です。今回は、この松本さんの講演内容の要旨を紹介したいと思います。
(1) 日本では、これまで貧困問題についてほとんど議論されてこなかった。日本は先進国の中でも、戦後、貧困についての関心を特に急速に減速させた国である。19世紀の貧困問題は「貧困から守られるべき」という理念もそのシステムも整備されていない中での貧困であったが、現代の貧困は理念とシステムの中で発生している貧困問題であり、それは国の社会政策の失敗を意味している。
(2) 今問題となっている貧困は相対的貧困の意味で、それぞれの社会において惨めな思いをしないで生きていける水準である。一般的には、生活保護世帯と同水準以下の消費水準の世帯をさしている。現在の日本は、OECD加盟国の中でも、アメリカと並んで、特に高い貧困率となっている。また、貧困は単なるお金の問題ではなく、不利の連鎖の問題である。
(3) 「子どもの貧困」の問題は、「ある人の人生の初期にどういう状態•環境の下に置かれているのか」という問題であり、貧困を家族単位で捉えるのではなく、子どもの人権、子どもの成長発達の権利の視点から捉える必要がある。それが、特に「子どもの貧困」を取り上げる意味である。
(4) 日本における「子どもの貧困」の現実としては、たとえば、次のような指標を挙げることができる。
①青少年の最初の職業が非正規雇用である割合が、80年代前半14%であったのに対し、2000年代前半には44%に達している。
②日本の子ども人口の14%が貧困水準以下の家庭で生活している。一クラス40人とすると5~6人が貧困水準以下の環境に置かれていることになる。
③就労一人親世帯の貧困率が極端に高く、就労率が高いのに貧困率が高いのが日本の特徴である。
④先進国の中でも、子ども•家族に対する公的な財政的措置が特に低い。子ども•家族分野への社会支出の対GDP比は0.75%で、イギリス、フランス、スウェーデン等のEU諸国の4分の1程度にすぎない。
⑤国の税制と社会保障制度は、所得の再分配機能により本来であれば貧困を減じる方向に働くものでなければならないが、日本ではむしろ子どもの貧困を増大させる逆機能をもってしまっている。
⑥世界的に見ても、日本では、子育てや教育負担の家族依存度が非常に高い。親が年間教育費に100万円以上支出しなければならないというのは世界的に稀である。
⑦早期教育•受験の低年齢化、塾利用の一般化など、子育ての商品化•市場主義化が進んでいる。子育ての市場主義化と前述した家族依存主義が結びつくと、親の経済力等が子どもの状態に簡単に結びついてしまい、貧困が容易に再生産されてしまう。
(5) 子どもの貧困が、子どもの成長発達に与える影響としては、①健康への悪影響、②学業達成の不利•教育機会の制限、③子どもらしい経験と活動の制限、④負の経験から回復の機会の制限(虐待や非行の経験、挫折の経験から立ち直る機会を持ち得るか?、たとえば、モデルとなる大人から適切なアドバイスを受けることができるか?、カウンセリング等の有償のサービスを受けることができるか?大学受験に失敗した時に浪人できる経済的余裕があるか?等)、⑤社会的自立の不利と困難(様々な不利•ハンディキャップが育ちの過程で、累積し、連鎖し、複合することは、結果として、社会的自立の困難を招く)等がある。
(6) 上記のとおり、子育ての家族依存の強さと市場主義が結びつく中で、貧困及び子どもの貧困が世代を越えて再生産される状況となっている。
この連鎖を断ち切るためには、①市場と資本への社会的規制(普通に働いたら普通の暮らしができる労働条件の最低限の引き上げ、子育てにそれほどお金がかからない社会にするための子育て資源の商品化への規制)、②子育てに関する家族支援(社会保障やソーシャルワークの充実)、③家族を経由しない、子どもの可能性を直接広げる取り組み(児童福祉と公的教育サービスの充実、学校に行けているか?友達と十分に遊べているか?、虐待や非行に巻き込まれているなど、不利に置かれていないか?、子どもは子どもらしい時間を持てているか?等の子どもの成長発達保証の視点からのサービスの充実)等が求められる。
松本さんのお話は、日本の子どもたちが置かれている厳しい環境をあらためて確認させられるお話でした。「子どもの貧困」の問題が、一般の「貧困」問題に止まらず、「親の貧困•不利が、子どもの成長発達上の不利•ハンディキャップにつながることを、いかにして防ぐか?」「親の貧困•不利が、子どものチャンスの制限につながることを、いかにして防ぐか?」「貧困の世代間連鎖をいかにして防ぐか」という問題であることが、良く判りました。
そして、この視点から見たとき、「子どもの貧困」を防止する上で、もっとも重要な公的システムが、学校教育ということになります。果たして、今の学校教育は、この視点を明確に持ち得ているでしょうか?
愛着障害をもたらす家庭環境が背景•原因となった問題行動等への理解(アセスメント)と適切な対応、学力保障と進路選択の保障、経験の多様化を図る取り組み、対人関係能力等のソーシャルスキルを高める取り組み、栄養面を含めた身体的発達の保障など、本当に様々な課題があります。「子どもの成長発達の保障」、「自立のために求められる能力•スキルを育てる」という視点を明確にもった取り組み、学校へのサポート体制を含め、地域•学校が一体となった取り組みが求められていると思います。
 子どもの貧困: 子ども時代のしあわせ平等のために
子どもの貧困: 子ども時代のしあわせ平等のために
浅井春夫(編集), 湯澤直美(編集), 松本伊智朗(編集) / 明石書店 / 2008年3月28日
<内容>
子ども時代に貧困であるということは、その子の人生にとってどんな意味をもたらすのでしょうか。貧困•格差問題のなかでも、貧困という視点からの研究がもっとも遅れているのが「子どもの貧困」です。本書は、福祉現場から「子どもの貧困」の実相をとらえ、家族との関係を解き明かします。世界的な研究を紹介するとともに、政策的提言をめざします。
 子どもと家族の貧困: 学際的調査からみえてきたこと
子どもと家族の貧困: 学際的調査からみえてきたこと
松本伊智朗(編集, 著), 鳥山まどか (著), 関あゆみ (著), 川田学 (著) / 法律文化社 / 2022年12月25日
<内容>
札幌市•北海道と北大研究チームによる、子どもとその保護者を対象とした大規模調査から、子育て家族の実態を多面的に明らかにし、「問題の構図」を再考する。貧困研究の専門家や教育を軸とした社会学•心理学の専門家による協働作業から、年齢段階に即した議論と考察を行い、新たな知見を提示。
 子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
清水克之(著), 佐藤拓代(著), 峯本耕治(著), 村井美紀(著), 山野良一(著), 松本伊智朗(編集) / 明石書店 / 2010年2月5日
<内容>
子ども虐待と貧困との関係を乳幼児期から青年期までの子どものライフステージに沿って明らかにする。執筆者のまなざしは、親の生活困難に向けられ、子どもと家族の社会的援助の必要性を説き、温かい。貴重なデータも多数掲載している。
 子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
小林美智子(著), 松本伊智朗(著) / 明石書店 / 2007年12月6日
<内容>
公権力の介入を求めるまで深刻化した子ども虐待。だが介入は虐待防止の切り札といえるのか。2005年の日本子ども虐待防止学会シンポジウムの記録を基に編まれた本書は、日英の経験をふまえ、虐待を防ぐために本当に必要な「ケアする社会」を構想する。
 スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
山野則子(編集), 峯本耕治(編集) / ミネルヴァ書房 / 2007年8月1日
<内容>
はじまったばかりのスクールソーシャルワーカーの活躍を描く。スクールカウンセラーや養護教諭とともに様々な問題に悩む親子に、社会的問題を含めて解決にあたる事例を紹介します。今までにない児童生徒へのアプローチに非常な関心がもたれています。
 子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
峯本耕治(編集) / 明石書店 / 2001年12月12日
<内容>
先進的なシステムをもつイギリスの児童虐待防止制度の詳細と、実際の運用状況を具体的に紹介する。ライン等も示し、問題点にも触れる。