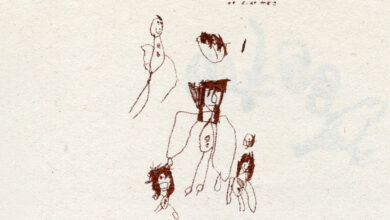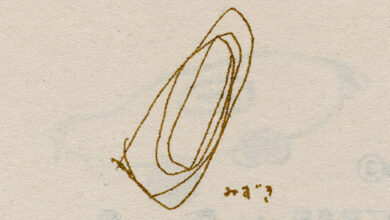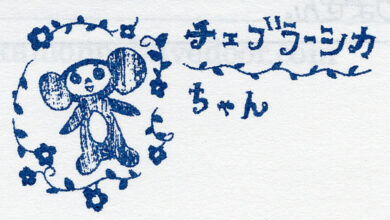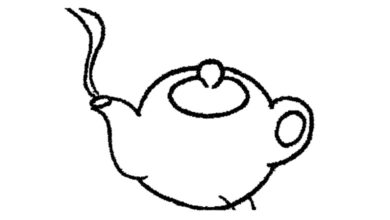Jリーグは日本型システム改革の突破口となり得るか?
前にも御紹介したと思いますが、イギリスをはじめとするヨーロッパのスポーツは地域のスポーツクラブによって支えられています。学校の中にも、スポーツクラブはありますが、スポーツを本当に楽しみたい、真剣にやりたいと考えている者は、地域のクラブチームに所属します。
たとえば、ラグビーでは、イギリス全体で2000以上のクラブチームがあります。サッカーはもとより、クリケット、テニスなど、ほとんど全てのスポーツが地域クラブによって支えられています。地域クラブは、メンバーの会費を中心に、試合ごとに地域の企業にスポンサーになってもらう等の方法で集めた寄付によって運営されています。まさに、スポーツを楽しみたいと考えている一人一人の市民によって支えられている草の根のスポーツクラブです。もちろん、プロ選手やトップチームも、この地域クラブの中から生まれてきます。
このような日本とイギリス(ヨーロッパ)のスポーツ体制の違いには、スポーツに限らず、日本型システムとヨーロッパ型システムの違いが非常に良く現れています。
日本型システムは、基本的に学校や企業、家族といった組織や集団をベースとして作られています。わかりやすいのが社会福祉制度です。
日本の社会福祉は、終身雇用制度を中心とする企業の力に大きく依存してきました。企業は終身雇用制度を採用することによって、長期間にわたって従業員の生活を保証する。退職金や企業年金によって、老後の保障も行なう。社宅制度や保養所に見られるように福利厚生も企業が行なう。その代わりに、国は、企業の競争力を高め・維持させるための経済政策を徹底して採用する。
日本型福祉制度を支えるもう一つの単位が家族です。家族が機能していれば、老人介護も家族内でやれる。障害者問題等も家族の問題として解決できる。だから、離婚等を少なくして、家族が崩壊しないようにする必要がある。配偶者控除等の税制は、家族制度を維持するための典型的な制度です。
子どもについても、できるだけ進学率を高める。そうすることによって、幼稚園・保育園から大学まで、大多数の子どもが、幼年期から成人に達するまで、学校制度の中に保護され、囲い込まれることになる。そうすることによって、ドロップアウトする子どもを最小限にすることができ、子どもの犯罪率は下がり、若年失業者の問題も生じない。
このような日本型社会福祉制度は、個人を対象として制度設計されているヨーロッパ型の社会福祉制度とは、根本的に異なっています。
私は、つい最近まで、このような違いは、「日本と欧米の文化の違いから自然に生まれてきたものかな」との印象を持っていましたが、実はそうではありませんでした。少し前に読んだ岩波新書によると、自民党の1960年代か70年代の政策綱領に「日本は、個人を対象とするスウェーデン型の福祉制度は採用しない」と明確にうたわれていました。日本は意図的に企業や家族、学校等をベースとする社会福祉制度を築き上げてきたのです。
このような日本型福祉制度は日本が経済成長を遂げている間は見事に機能してきました。しかし、ここ数年の状況を見ていると、経済のグローバル化に伴う企業競争の激化、終身雇用制度の崩壊、リストラの嵐、離婚率のアップ、児童虐待問題、ドメスティックバイオレンス、不登校・中途退学社の増大、学級崩壊問題など、日本型福祉制度の基盤を揺るがす問題が噴出しています。退職金や年金も期待できなくなっています。
組織や集団をベースとする日本型福祉制度は明らかに崩壊の危機にさらされています。
スポーツの話から全く離れてしまいましたが、最初に書いたような日本スポーツの危機的状況も、この日本型社会福祉制度の危機と同様の原因に基づくものです。組織や集団をベースとしたため、その組織や集団の基盤が崩れ始めたとき、どうしようもなくなってしまうのです。
この危機的状況を乗り越えるのは本当に大変ですが、やはり「個人の幸福」や「自立した個人」、「個人の集まりとしての組織」をベースとしたシステムに変えていくしかないのだと思います。
地域クラブを目指したJリーグの成功が、その第一歩になってくれれば良いのですが。