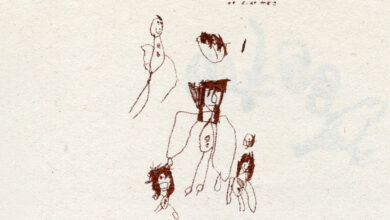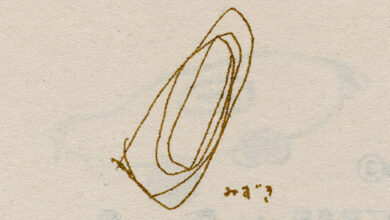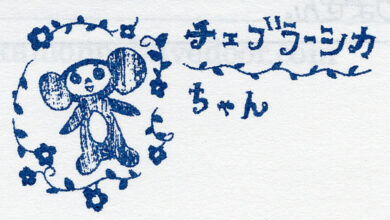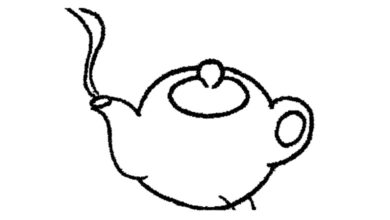「今どきの子ども、家族•••」ではなくて

弁護士 峯本耕治
まだ、間に合うでしょうか?所さんから、「原稿が遅れるのなら、先に題(テーマ)を知らせて欲しい」とのことでしたので、上のような題を連絡しましたが、突然、全く関係のない話を書きたくなりました。
先週の9月5日に東京の半蔵門にあるイギリス大使館に行ってきました。新聞報道などで御存知の方もいらっしゃると思いますが、俳優の真田広之さんがイギリスのエリザベス女王から名誉大英帝勲章第5位(MBE)を授与されることになり、イギリス大使館で、その叙勲式とパーティが行われたのです。何故、私が出席できることになったかと言いますと、私の高校時代からの親友が真田さんのマネージメント会社の代表をしていて、その会社の仕事をしたことがきっかけで個人的にも知り合いになり、これまでも、新しい公演等が始まる度に招待してくれるようになったのです。
叙勲の理由は、日英の文化交流への貢献です。彼が主演をつとめたハムレット(1999年)やリヤ王(2000年)のロンドン公演(蜷川幸雄演出)がきっかけとなり、シェークスピアの生誕地であるストラスフォード•アポン•エイボンを本拠地とする本場のシェークスピア劇団で半年以上にわたってリヤ王に出演したことが高く評価されたのです。もちろん、日本の俳優で大英勲章を受章したのは初めてのことで、41歳という若さの受賞はイギリスでも珍しいようです。日本で「叙勲」というと何となく抵抗を感じてしまうのですが、イギリスの場合に直に受け入れてしまうのは、単なる偏見でしょうか。
当日の叙勲式では、イギリス大使からメダルの授与と受賞理由の説明があった後、真田さんの挨拶がありました。この挨拶が、なかなか味わい深いものでした。彼にとって、本場のシェークスピア劇団に出演することは大変名誉なことであると同時に、非常にリスクの高いことでした。完璧な英語での芝居が求められますので、そのための準備•練習は大変なものです。成功したら国際俳優としての道が開かれる可能性がある反面、失敗すると(つまり、評価されないと)「やっぱり日本の役者はダメだ」ということになって、日本の演劇自体の評価が下がると共に、真田個人の日本での評価が大きく下がる可能性があります。
結果として、彼のチャレンジは成功し今回の受賞につながったわけですが、彼の挨拶には、その仕事を引き受ける際の悩みと決断、その後の苦労、サポートしてくれた様々な人々への感謝の気持ち等が自然に滲み出ていて感動的なものでした。
新聞報道によりますと、式後のマスコミからの取材に対しても、彼は「これに甘んじず、これからもリスキーな道を歩んでいきたい」と話していたようですが、彼の役者としてのプロ意識は、本当に素晴らしいと思います。皆さんも、是非、今後の真田広之に注目して応援してあげてください。
ちなみに、この叙勲式には、宮沢りえさんや山田洋次監督が出席していました。ミーハー気分で注目していたのですが、宮沢りえさんは、少し痩せすぎている感がありますが、女優としての輝きは、やはり、なかなかのものでした。それから、もう一つ、パーティー中にイギリス大使と直接会話を交わす機会があり、その時に、私が出版した本「子どもを虐待から守る制度と介入手法ーイギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題」をプレゼントしてきました。果たして、ちゃんと本棚に並べてもらえるでしょうか?
ところで、話は変わりますが、先週の芸能ニュースの一番は、やはり宇多田ヒカルの結婚です。家族や子どもの問題に関わっていると、ついつい、「なぜ、そんなに結婚を急ぐのかな」と思ってしまいますが、あの若さでトップを極めて、重い病気にもかかり、「孤独で、寂しいのだろうな」と思うと理解できるような気もします。
その宇多田ヒカルさんの結婚報道の中で、「できちゃっていない結婚」という表現がありましたが、実は、これは現代の若者の状況について考える上で非常に意味深(しん)な表現です。このような表現が自然に出てくるくらい、逆に、「できちゃった結婚」が増えているのです。数ヶ月前に新聞で報道されていた調査結果では(正確には忘れましたが)、10代20代の結婚の約40%が「できちゃった結婚」となっています。「あっ、そうなの」と通り過ぎてしまいそうですが、実は、この数字の中には、特に他の調査結果と併せて読むと、大変な社会問題が潜んでいます。
今回は真田の叙勲の話で紙面を取りすぎてしまい、これ以上書けませんので、次回にこの続きを書きたいと思います。これが今回書きたかった「今どきの子ども、家族•••」の話です。
蛇足ですが、もらっていた題名は『最近の心配。子ども、家族••』だったのです。確かにハイ!
イギリスの女王からの授与といえば、ショーン•コネリーの授与式を思い出しますね。アイルランドの民族衣装を(バックパイプの奏者が着るようなスカート)颯爽とあの巨体にまとって••あれほどタキシードの似合う人もいないのに、007の時よりも益々魅力的になっている彼です。 所
 子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
清水克之(著), 佐藤拓代(著), 峯本耕治(著), 村井美紀(著), 山野良一(著), 松本伊智朗(編集) / 明石書店 / 2010年2月5日
<内容>
子ども虐待と貧困との関係を乳幼児期から青年期までの子どものライフステージに沿って明らかにする。執筆者のまなざしは、親の生活困難に向けられ、子どもと家族の社会的援助の必要性を説き、温かい。貴重なデータも多数掲載している。
 子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
小林美智子(著), 松本伊智朗(著) / 明石書店 / 2007年12月6日
<内容>
公権力の介入を求めるまで深刻化した子ども虐待。だが介入は虐待防止の切り札といえるのか。2005年の日本子ども虐待防止学会シンポジウムの記録を基に編まれた本書は、日英の経験をふまえ、虐待を防ぐために本当に必要な「ケアする社会」を構想する。
 スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
山野則子(編集), 峯本耕治(編集) / ミネルヴァ書房 / 2007年8月1日
<内容>
はじまったばかりのスクールソーシャルワーカーの活躍を描く。スクールカウンセラーや養護教諭とともに様々な問題に悩む親子に、社会的問題を含めて解決にあたる事例を紹介します。今までにない児童生徒へのアプローチに非常な関心がもたれています。
 子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
峯本耕治(編集) / 明石書店 / 2001年12月12日
<内容>
先進的なシステムをもつイギリスの児童虐待防止制度の詳細と、実際の運用状況を具体的に紹介する。ライン等も示し、問題点にも触れる。