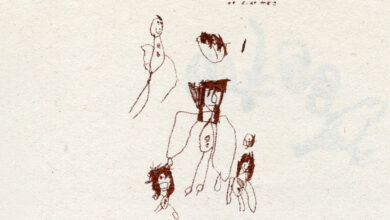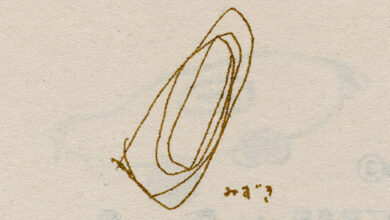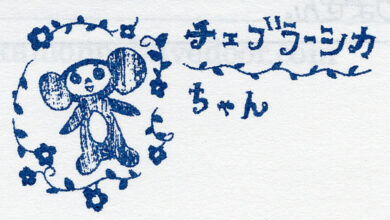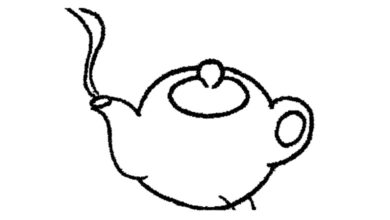イギリス報告(その2)イギリスのスポーツ文化を支える地域クラブ
9月から4月まで、毎週土曜日に、試合が行われます。年間30数試合程度にのぼり、かなりのハードスケジュールです。
しかも、各クラブには、1(ファースト)チームから6(シックスス)チームくらいまであって(16歳以下のチームもある)、各チームが原則として、毎週試合をするわけですから、イギリス全体で見ると、その試合の数は物凄い数にのぼります。ラグビーよりもクラブ数の多いサッカーやその他のスポーツを併せると、イギリス全体で毎週行われる試合の数は、とてつもない数になっています。
毎週、ファーストチーム同士の試合には、クラブOBをはじめとする地域の人々が、応援にやってきます。おじさん、おばさん、子どもまでが、ビールやらジュースを持って、プレーの度に、「カモン、フィンチリー」と叫んでいました(何故か、みんな「GO」ではなく、「カモン Come on」と言っている)。そして、試合が終われば、選手と一緒になって、応援に来た人たちも、パブで一緒にビールを飲んで楽しみます。
プロ選手がいるようなトップチーム同士の試合になると(これは、もちろん有料)、大きなスタジアムが、ほぼ満員になります。それでも、地域のクラブチームの延長にすぎませんから、その規模や範囲が大きくなるだけで、地域の人々が地元チームの応援に来るという形は変わりません。日本では、ラグビーやサッカーの試合を見に行くのは特別な事という印象がありますが、イギリスでは、土曜の午後に気楽に近所の試合を見に行くという感じで、完全に日常生活の一部になっています。
自宅から車で20分程度のところに、サラセンズというイングランドのトップチームのクラブがありました。その試合を初めて見に行ったときに、予定していた友人が来なかったために、チケットが余ってしまったことがありました。余った椅子席のチケットを、立ち見席のチケット(椅子席より安い)を買おうとしていたイギリス人に安い値段で買ってもらおうと思い、3人に声をかけましたが、3人ともに断られてしまいました。3人とも「椅子席ではなく、立ち見席で応援したい」というのが理由でした。スタジアムに入ってみると、実際に多くの人がゴールポスト裏の立ち見席で、ビールを片手に応援していました。これが、イギリス人の楽しみかたの一つだと、大変関心させられました。
応援の仕方も、地元チームであることや、ゲームを見る眼が肥えているせいもあって、良いプレー・悪いプレーに、見事に反応します。日本のようなまとまった応援は、ほとんどありませんが、ここの反応が共鳴しあって、なかなか楽しいものです。
国際試合などでは、イギリス代表チームが攻め込む場面になると、誰彼ともなく始まった歌がスタジアム中に広がり、スタジアムの銀傘にこだまして独特の雰囲気が生まれます。
また、ラグビーではそれほどでもありませんが、サッカーのトップリーグの試合の応援は、本当に熱狂的です。去年のサッカー・フランス・ワールドカップでは、イギリスの悪名高き「フーリガン」が相手チームの応援団と暴力事件を起こしましたが、観衆の熱狂ぶりを見ていると、何時、そうなってもおかしくないような雰囲気があります。
話が横道にそれてしまいましたが、いずれにしても、イギリス人にとって、スポーツは非常に身近なところにあり、生活に不可欠なものとなっています。
その基盤となっているのが、地域のスポーツクラブのシステムで、日本のJリーグはこの地域クラブシステムを目指していますが、イギリスを見る限り、地域クラブのシステムは、恵まれたスポーツ環境抜きには考えられないような気がする。そして、イギリスの恵まれたスポーツ環境は、そのまま、住環境の良好さを意味しています。
ロンドン駐在している日本人の友人が、「イギリス人の従業員は6時頃には皆帰ってしまい、残っているのは日本人だけ」と、ぼやいていましたが、仕事から戻って、良い自然環境の中で、地域の仲間や家族と共に、スポーツ(余暇)とビールを簡単に楽しむことができるのであれば「早く帰ろう」という気になるのが自然かもしれません。
「仕事以外の楽しみがたくさんあり、時間的にも費用的にも手軽に楽しめるのであれば、それ以上、無理して働く必要はない。しかも、階級社会だから、少々頑張っても、その壁を崩すのは難しいし、無理をしなくとも、ビールやスポーツは十分に楽しめる。」
少し単純化しすぎですが、ひょっとすると、イギリス人の中には、こんな感覚があるのかもしれません。