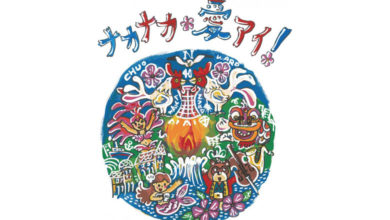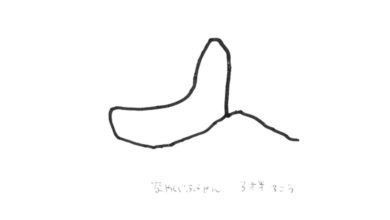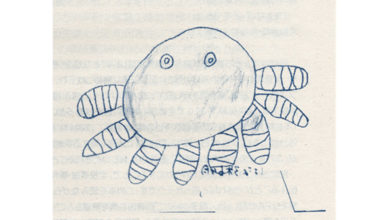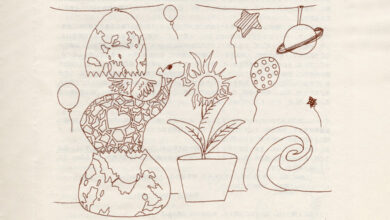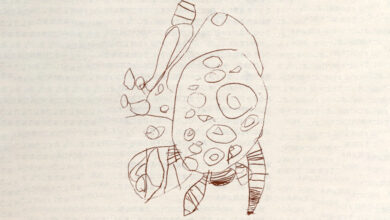粗食で生き返る

(1) 錯覚その①
一つ目は『肉を食べて筋肉モリモリ』という錯覚である。肉にはたんぱく質が含まれているが、それが即筋肉モリモリにはならない。
例えば、薄毛の人がわかめなどの海藻類をいくら懸命に食べても、毛が生えてくるわけではないことを知らねばならない。また、今でも赤ちゃんのためのお母さんの授乳教室で『おっぱいを良く出すためには牛乳をよく飲んでください』と言っているところがあるが、これも笑い話の類である。
私たちは食べ物を消化するわけだが、消化というのはまさに消して化けるということである。ご飯にはおっぱいを作る成分があり、身体の中で様々な食べ物を消化しおっぱいを作るのであって牛乳を飲めばそのまま母乳の成分になって出てくるわけではない。
だから、昔のある年齢以上の人はおっぱいを出すのに“餅”や“鯉”、“味噌汁”などを経験的に勧めていた。これらの食品を母乳の出ない人に勧める例が全国的に多かったことが分かっている。
もしレバーを食べて貧血が治るのなら、レバーより血を飲んだ方がずっと手っ取り早いが、身体はそんな風には出来ていない。いろいろな食品から身体に必要なものをつくり上げていることを知らねばならない。
(2) 錯覚その②
二つ目は『欧米型の食生活が日本食より優れている』という錯覚である。
アトピーの患者は若い人が多いので、そんな患者やお母さんに『朝は、ご飯とみそ汁に漬物ですよ』と言うと、『えっ?』と驚く人もいる。パンとコーヒーと牛乳にサラダ、それが普通の朝食だと思っている人が多い。でも欧米の食生活をまねた結果、一番大きく変化したのは主食より副食を多く食べるようになったということである。
つまり、欧米の食生活を理想だと勘違いした結果、ご飯をしっかり食べることは貧しいことだ思い込んでしまったのである。欧米の場合は、パンを主食とは呼ばないが、日本ではご飯を主食と言っている。これはなぜか。
日本の栄養学は、明治時代にドイツから学んだのが始まりで、ドイツの考えが基本になっている。ドイツという国は、北海道よりも少し北にあり、寒くて食物が育ちにくい環境にある。したがって、パンで腹一杯にするほど小麦が育たなかった上に、一度小麦を畑で作ると米と違って畑がやせて毎年同じ量の小麦を生産できないという欠点がある。米の場合、水田は今年100俵、来年も100俵と毎年同じように取れ、生産力が落ちないという素晴らしい性質がある。
だから、ドイツでは小麦つまりパンで腹一杯にするというのは難しかったのであり、ここにパンを主食とよべない理由がある。小麦が不足するドイツの人たちは秋になると大量に豚を殺して保存し、冬にはそれを食べて過ごしてきた。なぜ牛や馬ではなく豚を殺したかというと、牛や馬は草を食べさせておけば良いが、豚は人と同じものを食べるからである。
秋から冬と長期間豚肉を保存するため、最初は塩漬けにしていたが、そのうち、腸に肉を詰めてソーセイジやハムにし、さらに塩だけでなくコショウを加えて味の向上などが図られるようになる。
以上述べたように、日本でご飯をたくさん食べてきたのは、自然が豊かで米の収穫量が毎年変わらず豊かであったからで、決して貧しいからではない。
(3) 錯覚その③
三つ目は『栄養素を考えて食事をすることが科学的で正しい』という錯覚である。これは、Ⅰの序でも述べたように極寒に住むイヌイットは肉しか食べないし、ニューギニア高地人は肉や魚は食べずタロイモが主な食べ物であるが極めて不思議なことに、筋肉隆々としていることなどからも、栄養素食事は錯覚であることが理解できる。
例えば、ビタミンCが壊れるから生野菜しか食べないとか、カルシウムが大事だから毎日煮干しを食べるとか、蛋白質が豊富だから卵をたくさん食べるとか栄養素を考えていろんな説が出てきたが、これらはそれに反する説が出てくると、直ぐに変わる。TVの人気番組か何かでベータカロチンという高い抗酸化作用を持つビタミンは脂溶性ビタミンだから油で炒めた方が吸収がいいと言われると、今度は急に生野菜を止めて炒めて食べるようになる。また、卵にはコレステロールが多いから良くない面もあるという説が流れると、途端に卵を食べなくなり、卵の売れ行きが減るという具合である。
これらの三つの錯覚と戦後の食生活近代化論や栄養改善普及活動によって、日本の食生活は大きく次のように変わったのである。
- 食生活の急激な欧米化によるご飯の減少
- 農薬や食品添加物などの化学物質の急激な増加
これにより何が起きたかというと、子供のアトピーや鼻炎、喘息などの疾患が増大し、同時に若い人の乳がんが急激に増えている。
幕内秀夫が病院で接する患者の中で乳がんの患者が一番多く、年間何百人と接するが、これらの乳がん患者の特徴は、ご飯をほとんど食べなかった人ばかりである旨書いている。
それではどうしたら良いか以下に述べる。