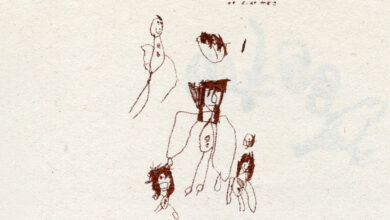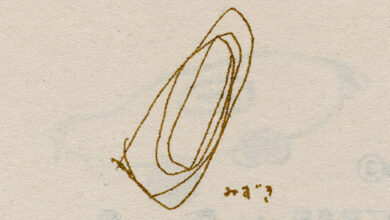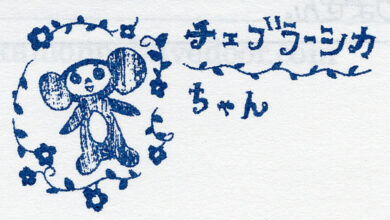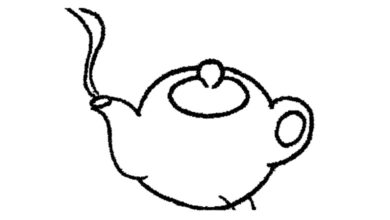イギリスでの電車乗り越しには気をつけよう
このようなイギリスやヨーロッパのやり方は、日本とは大きく違っています。日本の場合は、改札のチェックをほぼ確実に行う代わりに、有効な乗車券を持っていなくても、清算さえすれば、罰金を課せられることは、ほとんどありません。これに対し、イギリス・ヨーロッパ式は、改札のチェックは緩やかな代わりに、みつかった時に有効な乗車券を持っていなければ、どんな理由があろうとも、一律・形式的に罰金が課せられるわけです。
国民性や文化の違いと言ってよいでしょうが、評価は別にしても、少し乱暴に整理すれば、ルールに対する考え方の違いと、コストに対する意識の違いが、よく現れています。
日本では、いわゆる「本音と建前」の文化で、ルールが決まっても、抜け穴がもうけられていることが少なくありませんが、イギリスでは、一旦決められたルールは厳格に適用されます(もちろん、程度の問題ですが)。
例えば、日本では学校教育法11条で、教師の体罰が明確に禁止されています。しかし、実際には、現在でも、体罰を用いる教師が少なからずいます。依然、一部に体罰容認の雰囲気が残っていて、体罰教師に対するペナルティーも軽いものに止まっています。
イギリスでは、1980年代まで、教師の体罰は禁止されていませんでした。イギリスの学校での体罰は伝統的なもので、日本で言う体罰とは少し異なりますが、禁止が決定された時にも、体罰の必要性等について激しい議論が闘わされました。禁止される以前にも、多数の体罰ケースが裁判所に持ち込まれたのですが、イギリスの裁判所は、伝統的な方法に従った体罰については、これは適法であるとの判断を下していました。ところが、イギリスの国内裁判所で適法とされた体罰ケースが、次々とヨーロッパ人権裁判所に持ち込まれ、多くのケースについて、体罰が子どもの人権侵害にあたるとして、学校を管理する国側に損害賠償が命ぜられていきました。当初、イギリス政府は、このヨーロッパ人権裁判所の判断に抵抗を示していたのですが、多数のケースがヨーロッパ人権裁判所に持ち込まれるようになったため、損害賠償の金額も無視できないものとなり、これが決定的なものとなって、公立学校での体罰が禁止されたわけです。そして、一旦、禁止されると、それが厳格に適用されました。体罰禁止に違反した教師に対しては、解雇等の厳しい処分が科せられましたので、その後、公立学校における体罰は全くと言ってよいほど姿を消しています。
このように、一旦ルールが作られると、それが厳しいペナルティー付で厳格に適用されるというのは、イギリスのやり方の大きな特徴です。