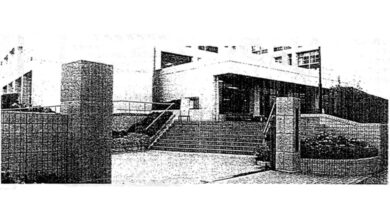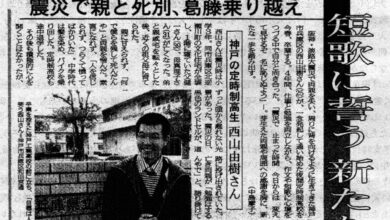保育•教育
「生命体」を育む保育・教育を今こそ

田中 英雄
スエーデンのシュタイナー病院を訪れた事がある。廊下はまるで画廊の様に患者の描いた絵が並び、各棟ごとにオイリュトミーを踊る部屋があり、病室の窓はまるで日本の石庭の様な自然の庭がベッドから見えるように低く設計され、治療道具は患者本人に見えないようベッドの上側、白布をかぶして置かれていた。何よりも病人の「生命体」を恢復することに力がそそがれているのがすごく伝わって来た。
幼児の時期の保育目標は「生命体」の育ちに力が注がれる。例えば「いじめ」が問題にされる場合、いじめている者の心の状況が感じられることが肝要。いじめで自殺者が出た学校の校長が「生命の大事さ」を生徒に説教することがあるが、日頃は生徒を競争させて「生命体」傷つけながら自殺者が出た段階で誠えている事の何と愚かしいことか!「生命が大事」というのは単なる「知」にすぎない。
「生命体」が育つ事に力を注ぐのは「意志」が育つ為である。「知」識偏重の教育を重視してきた日本の教育が、日本が国際的にも国内的にも権力に弱く、経済的グローバリズムに流される状況を作り出している
シュタイナー幼稚園では自然の木片や羊毛などが豊かに用意されている。そのような環境の中で育った子は化繊の布などを触覚的にすぐにわかるという。世界を変えるために教育施設だけでなく、利息の原理ではなく友愛の精神をベースにした「銀行」まで創ろうとした意思を育むシュタイナー教育に「今」こそ学ぶことは多い。