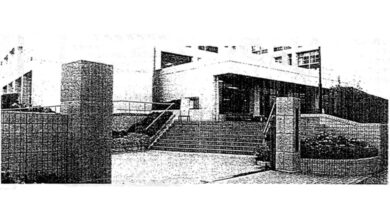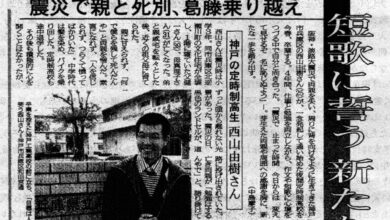イギリスの子ども達は自信満々
もうひとつ、大きな特徴として、イギリスの小中学校では、自分の意見や思いを表現するということが、非常に重視され、色々な場面で奨励されています。言葉での表現はもちろん、音楽や芸術を手段とする表現活動も同様に大切なものと考えられています。
ですから、授業の中で、子どもたちが意見を発表する機会が多く、また、日常的に、子どもたちは、教師や友達と、本当によく喋っています。それも、教師と子どもが一対一で話をする場面が多いから可能になるものです。
このようにイギリスの学校教育では、日本と比較すると、はるかに個々の子どもに着目した教育、個々の子どもとのつながりを重視する教育が行なわれています。
もちろん、その反面として、イギリスの授業は、決して効率的なものとは言えません。現実には、子どもたちの間にはかなりの学力差があると思われます。しかし、少なくとも言えることは、子どもたちが、いわゆる「落ちこぼれ感」「取り残され感」を持たずに済みやすい教育になっているという点です。
このことが、最初の調査結果に現れている、子どもたちの自尊心の高さを生んでいる大きな要因になっていると思われます。
本来、学校教育には、「集団教育」の側面と、「個々の子どもに着目した教育」の両面があり、どの国の学校教育制度も、両者のバランスの中で形づくられています。「集団教育」がもたらす弊害を、「個々の子どもに着目した教育」をうまく取り入れることによって是正しているという意味で、後者は前者を補うものと言ってよいかも知れません。
日本の学校教育は、「集団教育」の方向に、大きく偏ったものとなっています。そして、多数の子どもたちを集団として扱うことを重視した場合には、必然的に管理的要素が強くなります。
この集団・管理的側面を重視した教育の結果として、日本の学校のクラスの中には、「授業が面白くない」「授業がわからない」「自分が評価されていない」と感じている子どもや、先生との関係が悪い子どもなど、クラスの中に自分の「居場所」を見つけることが困難な子どもの割合が、非常に高くなっています。
教師の一般的権威・抽象的権威が失われ、子どもたちの気質が変化してきた中で、「居場所」のない子どもたちが、自分の「居場所」を求めて勝手に動き始めたというのが、今の「学級崩壊」現象ではないかと、私は感じています(もちろん、それ以外にも、様々な要因が複合的に重なって生まれてきているのでしょうが)。
その意味で、「集団教育」と「個々の子どもに着目した教育」の適正なバランスを、どのように実現していくかが、これから日本の学校教育の大きな課題ではないかと考えています。
「そのために、弁護士として、何か、やれることはないか」と考えている、今日この頃です。