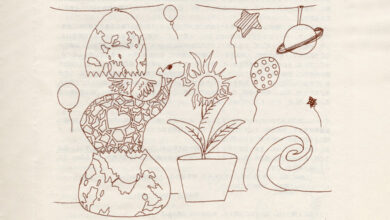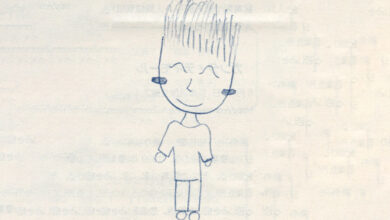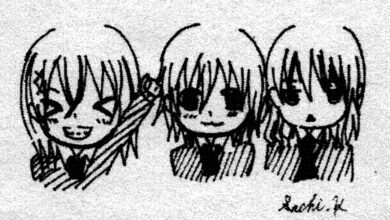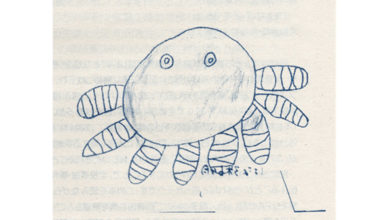学校の安全と開放は矛盾する?
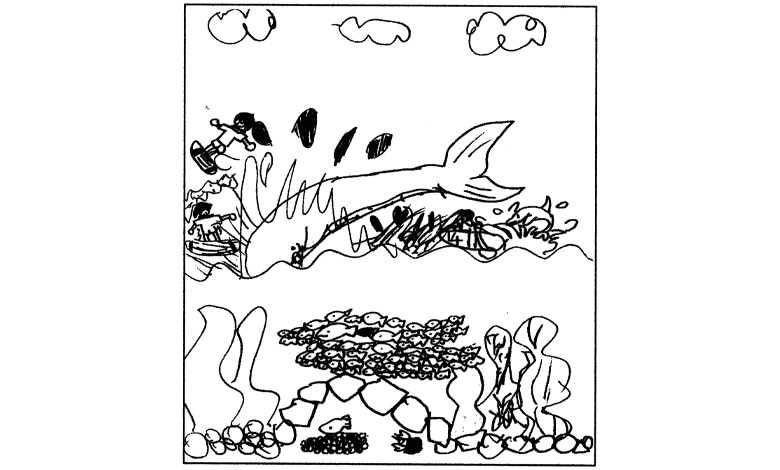
弁護士 峯本耕治
池田小学校事件は、本当にショッキングでした。この事件は、日本の精神医療体制の問題や刑事責任についての考え方など様々な問題を投げかけることになりましたが、その中でも、学校における子どもの安全管理のあり方が正面から問われることになった初めての事件と言って良いかも知れません。あまり知られていないことですが、学校への不審者等の侵入事件は決して珍しいことではありません。夜中に窓ガラスが割られたり、子どもたちが世話をしている動物が殺されたりするなどの事件は、日本全国でみると、たえず発生しています。今年の初めには、京都の日野小学校の事件もありました。そういうことを考えると、これまでにも、学校における子どもの安全管理をきちんと考えるチャンスはあったわけで、「過去の教訓が生かされなかった」という批判はあたっていないわけではありません。
それでも、今回の事件は、やはり異常でした。私の中にも、学校は、少なくとも、外部に対する関係では安全な場所というイメージがありましたので、どうしても、「安全管理を怠った学校•教師に今回の事件の責任がある」とは言い切れない気がしてしまいます。日本でも時折報道されていますが、アメリカでは、学校の中で殺傷事件が多数発生しています。そのため、アメリカでは、州によっては、警察官(スクールポリス)が学校に配置されているなど、安全管理意識が徹底されています。イギリスでも、アメリカほどではありませんが、日本よりは、学校の安全管理が意識されています。たとえば、私がイギリスの小学校をみた時に、最初に驚いたことは、親が登下校の送り迎えを義務づけられている点でした。親が送迎できない場合には、友人に頼むなどして、送迎を確保しなければならないことになっています。学校に来た子どもたちは、すぐには教室に入らず、始業時間まで校庭にいますが、その間の監督者もきちんと決められています。始業時間になると、子どもたちは、一旦、校庭にクラスごとに並んで、各クラスの教師に確実に引き継がれます。休み時間も同様で、教職員や親のボランティア等が校庭で遊んでいる子どもたちを見守っています。日本の学校の安全管理意識とは、相当隔たりがあります。逆に言えば、日本は、学校における安全管理を特別意識しないでも良い安全な社会(少なくとも、そう思いこめる社会)だったのです。高塚高校の事件の時に、「門扉は管理教育の象徴である。そもそも、校門を閉める必要はない」と主張していたように記憶しています。それは、それで正しいのですが、やはり、あのときには、学校における子どもたちの安全が、今回の事件のような形で脅かされるとは全く考えていませんでした。今回の事件は、日本社会と学校の安全神話を完全位葬り去る事件となりました。
同時に、というか、その結果として、この事件は、近年の「学校の開放」という方向性にも大きな影響を与えることになりました。過去数年の間に、全国各地で、「学校の開放」の取組みが急激に進んできました。たとえば、土日の校庭開放はもちろんのこと、平日の昼間にも空教室を提供するなど地域のコミュニティーセンター化を図ろうとしている学校•地域、保護者の授業参観だけでなく、地域の人が自由に授業参観をできるという取り組みをしている学校もあります。管理教育に対する反発や学校の閉鎖性が批判される中で、「学校の開放」の必要性が強調されるようになってきたのです。池田小学校事件は、「学校の開放」に向けて積極的な取り組みを行ってきた、これらの学校や地域に、大きな混乱と戸惑いを生じさせる結果となりました。
今、学校の「安全」と「開放」の関係をきちんと整理しておかないと、極端な反応になってしまう可能性があります。その整理は簡単ではありませんが、「学校の開放」には、①学校教育の開放と②学校施設の開放という2つの側面があり、両者を分けて考えることが、基本になると思います。①の学校教育の開放は、学校教育を教師だけに委ねるのではなく、親や子どもの学校教育への積極的な参加、様々な職種の社会人による授業、スクールカウンセラー等の専門職を学校に配置する取り組み等を意味しています。まさに、教師の聖域とされてきた学校教育に新しいエネルギーを取り込むもので、日本の管理教育•閉鎖教育を打破する重要な意味を持つものです。当然のことながら、この意味での「学校の開放」は、学校の安全管理と全く矛盾しません。今回の事件によって、この面での学校の開放化にブレーキをかける必要は全くありません。問題は②の学校施設の開放です。地域のコミュニティーセンター化はたいへん魅力的な構想ですが、他方で、地域の人が自由に学校に出入りできることをイメージすると、どうしても、学校の安全管理と矛盾する側面が出てきます。この点に関しては、やはり学校の安全管理の要請とのバランスを考えなければなりません。このバランスを考えたとき、やはり、学校が子ども達の教育の場であるということが最優先に考えられなければなりません。地域の状況にもよるのでしょうが、授業中に校門を閉め、入校者の管理を常識的な方法によって行うことは、やむを得ないということになるように思われます。悲しいことですが、日本も、学校の安全管理を本気で意識しなければならない危険な社会になってきたということです。ただ、いずれにしても、「学校の開放」の意味をきちんと議論し、極端な対応にならないようにしなければなりません。
 子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
清水克之(著), 佐藤拓代(著), 峯本耕治(著), 村井美紀(著), 山野良一(著), 松本伊智朗(編集) / 明石書店 / 2010年2月5日
<内容>
子ども虐待と貧困との関係を乳幼児期から青年期までの子どものライフステージに沿って明らかにする。執筆者のまなざしは、親の生活困難に向けられ、子どもと家族の社会的援助の必要性を説き、温かい。貴重なデータも多数掲載している。
 子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
小林美智子(著), 松本伊智朗(著) / 明石書店 / 2007年12月6日
<内容>
公権力の介入を求めるまで深刻化した子ども虐待。だが介入は虐待防止の切り札といえるのか。2005年の日本子ども虐待防止学会シンポジウムの記録を基に編まれた本書は、日英の経験をふまえ、虐待を防ぐために本当に必要な「ケアする社会」を構想する。
 スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
山野則子(編集), 峯本耕治(編集) / ミネルヴァ書房 / 2007年8月1日
<内容>
はじまったばかりのスクールソーシャルワーカーの活躍を描く。スクールカウンセラーや養護教諭とともに様々な問題に悩む親子に、社会的問題を含めて解決にあたる事例を紹介します。今までにない児童生徒へのアプローチに非常な関心がもたれています。
 子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
峯本耕治(編集) / 明石書店 / 2001年12月12日
<内容>
先進的なシステムをもつイギリスの児童虐待防止制度の詳細と、実際の運用状況を具体的に紹介する。ライン等も示し、問題点にも触れる。