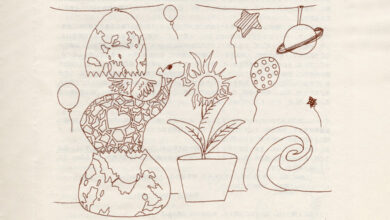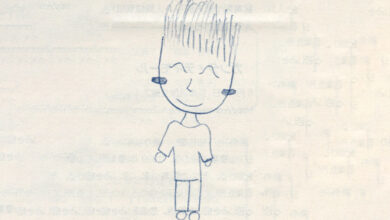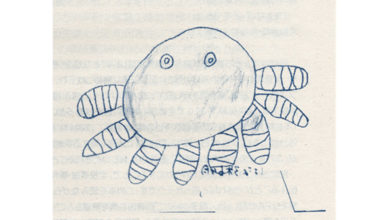心のケアと安心•安全環境
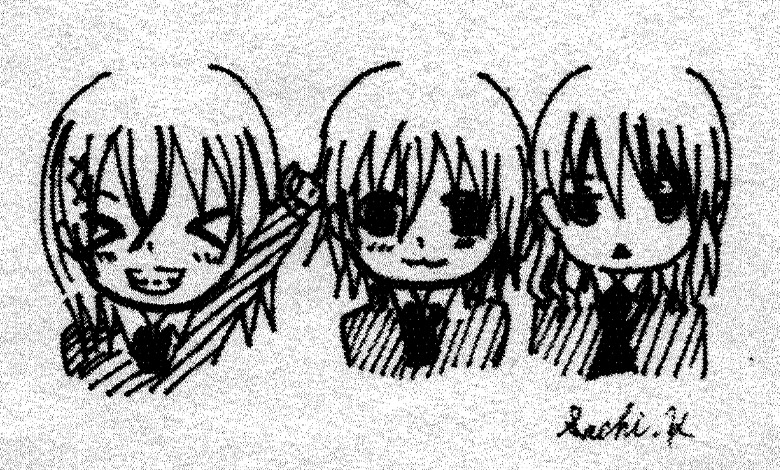
弁護士 峯本耕治
東北大震災から3ヶ月が経過しましたが、原発•放射能問題が収束しない限り現在進行形の被害が発生しつづけるために、現実的にも、精神的にも、本格的な復興の段階に入ることができず、本当に辛いですね。子どもたちにとっても、一日も早く安定した日常が回復されると良いのですが、何もできないことに歯がゆさを感じています。
大きな災害や事件が発生すると、子どもの心のケアの必要性が叫ばれます。突然、家族を失い、生まれ育った家を流され、友達を失う等の被害を受けた子どもたちが心に大きな傷を負い、時にトラウマ(PTSD)と呼ばれる深刻な精神的外傷を抱えることになるのは、ある意味で避けられないことであり、そのような重大な心の傷を抱えた子どもたちに心のケアの必要性があることは言うまでもありません。ただ、そのことは当然として理解しつつも、正直なところ、心のケアの必要性を一般的に強調する今の風潮には賛成できない思いを持っています。子どもにとって、より大切なのは、傷ついた心に直接手を入れケアすることよりも、現在の生活において安心•安全な環境を少しでも回復していくことにあって、過剰に心のケアを強調することは、逆に、子どもの心の傷を不必要に症状化させ、深刻化させ、慢性化させ、固定化させる危険性があると感じるからです。子どもは、大人以上に「今を生きる存在」です。たとえ、心の傷を負ったとしても、親をはじめとする信頼できる大人、愛されていると感じることができる大人に支えられ、安心して、食べ、眠り、遊び、学ぶことができる環境を確保していくことができれば、子どもは確実に元気を回復していきます。今の生活が安心できるものであれば、また、今の生活が少しでも楽しいと感じることができるものであれば、子どもは元気になっていくのです。もちろん、今回のような余りにも深刻な被害になると、それ自体が難しいことなのですが、たとえ、避難所の生活というような限界的な環境の中でも、親や周囲の大人が、子どもに対しては安心できる落ち着いた態度で接し、「大丈夫だ」、「心配ないよ」、「あなたが悪いわけでは無いよ」等のメッセージを伝え、少しでもベターな、安心できる雰囲気の下で、規則正しい食事の場を確保し、安心して眠れる環境を作り、友達との集団の遊びや学びの場を回復することなどを心がけていけば、ほとんどの子どもは、少しずつでも着実に元気を回復していきます。今が安心できるものであれば、しんどい出来事が、少しずつ過去の記憶になっていくのです。大きな災害や事件が発生したときの危機対応として、このような「子どもにとっての安心•安全環境の回復•確保」という視点をより重視する必要があると思っています。
新聞でも大きく取り上げられていましたがこの6月8日は、児童8人が死亡し、教師2人を含む15人が重軽傷を負った大阪教育大附属池田小学校の児童殺傷事件から丸10年にあたる日でした。私自身も、この間、この事件によって深刻なトラウマを抱えることになった一人の子ども(Aさん)のサポートに関わってきました。Aさんは、休み時間に友人6人と教室で一緒に話をしていたところ、一人でトイレに行ったほんの僅かの瞬間に事件が発生し、教室に戻った時には教室が血の海となっていて一緒にいた友人5人が全て目前で亡くなっていくという悲惨な体験をした子どもです。余りにも悲惨で過酷な体験であるため、いわゆる急性期のPTSD症状は避けられなかったと思われますが、学校は事件後のクラス運営において、たとえば、「朝の出欠の際に5人の子どもの名前を呼び続ける」、「給食時には5人の給食をお供えする」、「全員で教室を出るときには5人の写真を持って出る」、「5人の通知表をクラス全員で作成する」など、あたかも事件によって亡くなった子どもたちがその後も生きているかのごとく扱うことを子どもたちに求めたり、被害児童ら自身が参列しなければならない慰霊の行事をその後も頻繁に企画し続けるなど余りにも極端な対応が繰り返されました。その結果、Aさんは、極めて激しいPTSD症状を深刻化•慢性化させていきました。いうまでもなく、このようなクラス運営は、自我等が十分に確立されていない小学校低学年の子どもたちに精神的な混乱をもたらす危険性が極めて高いもので、特に、自分ひとりが生き残ったことによって強い無力感や孤立感、罪障感を抱いていたAさんにとっては、心の傷を激しく刺激し続ける対応(まさに傷を上からこすり続けること)になってしまったものです。心的外傷を負った子どもへのケアのあり方として余りにも不適切なものであり、Aさんは、その後、激しいパニック症状を示し続け、長期間の不登校に陥りました。ただ、その後は、学校の適切な支援が得られるようになり、私自身も入って学校•教員と保護者が一緒になって月1回のケース会議を開催するようになり、互いに子どもの状況についての理解を深め様々なサポートを提供する中で、Aさんは少しずつ回復し、学校にも行けるようになりました。様々な課題やしんどさは抱えているものの、現在は、高校2年生となり、落ち着いた学校生活を送っています。
事件後にAさんが置かれていた学校環境は、まさに、前述した安心•安全環境とは、正反対の環境であったわけです。学校は、亡くなった児童の遺族の思いに配慮し、また、クラスの子どもたちにとっても、亡くなった仲間を同じように扱うことが心のケアにつながるものと考えたのでしょうが、率直にいって、心的外傷を負った子どもへのケアのあり方として余りにも不適切なものであったと思います。
附属池田小学校事件は、学校等において大きな事件や災害が発生した際の、危機対応としての子どものケアのあり方についても、大きな教訓を含んだ事件であったと思います。
 子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
清水克之(著), 佐藤拓代(著), 峯本耕治(著), 村井美紀(著), 山野良一(著), 松本伊智朗(編集) / 明石書店 / 2010年2月5日
<内容>
子ども虐待と貧困との関係を乳幼児期から青年期までの子どものライフステージに沿って明らかにする。執筆者のまなざしは、親の生活困難に向けられ、子どもと家族の社会的援助の必要性を説き、温かい。貴重なデータも多数掲載している。
 子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
小林美智子(著), 松本伊智朗(著) / 明石書店 / 2007年12月6日
<内容>
公権力の介入を求めるまで深刻化した子ども虐待。だが介入は虐待防止の切り札といえるのか。2005年の日本子ども虐待防止学会シンポジウムの記録を基に編まれた本書は、日英の経験をふまえ、虐待を防ぐために本当に必要な「ケアする社会」を構想する。
 スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
山野則子(編集), 峯本耕治(編集) / ミネルヴァ書房 / 2007年8月1日
<内容>
はじまったばかりのスクールソーシャルワーカーの活躍を描く。スクールカウンセラーや養護教諭とともに様々な問題に悩む親子に、社会的問題を含めて解決にあたる事例を紹介します。今までにない児童生徒へのアプローチに非常な関心がもたれています。
 子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
峯本耕治(編集) / 明石書店 / 2001年12月12日
<内容>
先進的なシステムをもつイギリスの児童虐待防止制度の詳細と、実際の運用状況を具体的に紹介する。ライン等も示し、問題点にも触れる。