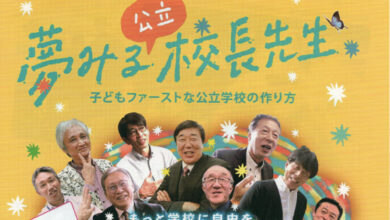脱学校原論① 「学校信仰」の解体

堀蓮慈
まず、「登」校いう言葉を問題にしたい。なんで学校に「登る」んか?「お上」の作った学校の方が「下々」の民衆より上にある、いうことを前提にしとるからや。つまり、日本人の骨にしみ込んだ官尊民卑の伝統の表れで、民主主義の時代にこんな言葉が生き残っとること自体、恥やと思わんならん。大袈裟な、て思うかもしれんけど、言葉いうんは意識に大きな影響を与えるもんや。
ほならどない言うか?学校いうんは図書館や公民館や公共交通機関と同じで、行政のサーヴィスなんやから「利用」でええねん。学校に行くんも図書館に行くんも同じレヴェルでとらえた時に、学校の権威主義、集団主義、成績による差別主義の異常さ、おぞましさが浮き彫りになってくる。みんな学校を通過してきたもんやから、その異常さに対する感覚がマヒしとるんや。税金で学校を維持しとる主権者および利用者として、現状を放置しとくことは未来に対する犯罪や、と言うてもええやろう。
わかりやすいように、バスにたとえてみる。学校バスに乗ると、なるほど移動速度は速いが、行き先はどこやねん?さんざん遠回りしたあげく、とんでもないところに連れて来られて、「これやったら歩いた方がよかった」いうことになる可能性は十分にある。しかもバスは、停留所のたびに客を選別して次に乗るバスを決める、いうとんでもなく無礼なシステムやから(金を払とるんはわしらやぞ!て誰か怒れよ)、客は乗り換え競争のことで頭がいっぱいになってて、景色を見る余裕もない。「バスに乗り遅れるな!」いう熱に浮かされたような思考(バブルと同じで、こういう考え方をしてると後でえらい目に会う)をやめて、一つ冷静に損得を考えてみようやないか。
「学校に行かんと生活に必要なことが学べん」いうんは明らかにウソや。昔みたいに情報の乏しい時代ならいざしらず、今や学校外の方が豊富な情報に囲まれてるから、字さえ読めたら必要なことはいつでも学べる。字ぐらい、学校に行かんでも読めるようになるやろ(ぼく自身の体験では、マンガ雑誌は漢字にカナがふってあるから、学校に行く前に全部読めてたし、相撲見てかなりの数の漢字を覚えた)。学ぶ時期が早いか遅いかは関係ない。学びの原動力は好奇心やから、子どもが「知りたい」と思たら、素晴しいスピードで、しかも楽しく学べる。一方、興味のない知識を詰め込もうとすると、苦痛な上にすぐ忘れるし、何より悪いことに、「勉強」いうんはイヤなもんや、いう思い込みができてしまう。学校へ行ったばっかりに学びの喜びが感じられんようになったとしたら、これは一生を通して巨大な損失や。
もう一つの脅し文句として、「学校へ行けんようでは社会に適応できん」いうんがあるけど、実社会はバスの中やなしに外にある。同じ年齢の人間ばっかり詰め込まれて、いうんはどない考えても異常な社会で、大人やったら「ここは強制収容所か」いうて怒るべきところや。学級崩壊いうんは、今の学校システムが機能せんようになった、いうことの現われでな。民主的なルールがあったらそのルールに従うて改革もできるんやけど、子どもから主権者として権利を奪うてるために、秩序を崩壊させる方向へしか行かんわけよ。ぼくらみたいにフリースクールの運動してきた人間からみると、「自業自得」いう気がする。フリースクールの基本理念は、人権を守る、いうことで、具体的には、「自分の行動は自分で決める。みんなの問題はみんなで話し合って決める」いうだけのことや。それだけのことが日本の学校ではできてないんや。
 脱学校の社会 (現代社会科学叢書)
脱学校の社会 (現代社会科学叢書)
イヴァン•イリッチ(著), 東洋(翻訳), 小澤周三(翻訳) / 東京創元社 / 1977年10月20日
<内容>
現行の学校制度は、学歴偏重社会を生み、いまや社会全体が学校化されるに至っている。公教育の荒廃を根本から見つめなおし、人間的なみずみずしい作用を社会に及ぼす真の自主的な教育の在り方を問い直した問題の書。