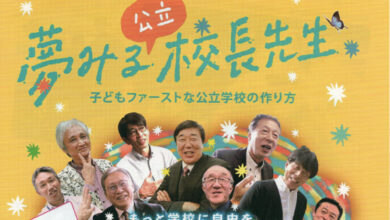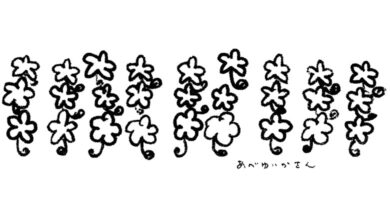脱学校原論⑤ 生きるのに必要な力とは

堀蓮慈
学校に行かんことで一番不安になるんは「学力」についてやけど、そもそも学力て何や?最近「学力低下」とかで問題にされてるんは、もっぱら知識の量やけど、それで学力を云々するんは、旧態依然とした知識信仰にすぎん。今や知識なんかデータベースからなんぼでも持ってこれるんやから、必要なんはそれを使いこなす思考力やろう。知識は食材、思考は料理、いうたとえがあるけど、使わん食材は腐るだけや。
人間の思考いうんは、型にはまったテストだけでは計り切れんもんや。今は、記憶力とか計算力とか、簡単に数値化できる能力だけを計って「学力」と称してるとしか思えん。そやとしたら、学力低下を言う学者の頭の中味の方こそ問題にせなあかんな。
言葉通りの意味で「学ぶ力」いうたら、知的好奇心、つまり「知りたい」と思う気持ちやないかな。それが低下しているとしたら、学校で与えられる食材および調理法に魅力がないからやろう。全員に同じメニューを同じ量だけ「食え」て強制して、食えんかったら怒られるんやから、生徒にしたらまさに食傷するわな。食欲もないのに食うたら、消化不良になるか、下痢するわ。それでも昔は、それをクリアしたら「将来の安定」いうご褒美がもらえたけど、今はそれが揺らいでいるわけやから「意欲低下」が起こっても当然や。
ほんまに生きる力を与えてくれる食物やったら、みんな喜んで食うやろう。今、多くの若者が生きる指針を求めてて、そういう飢餓感は折りにふれて感じる。ぼくの考えでは、生きる基礎になるんは哲学あるいはスピリチュアリティやと思うけど、それを学校に期待したって無理、というより危険や。権力に都合のええ道徳か「愛国心」を押しつけられるんが関の山やろう。安っぽいナショナリズムに中毒せんためにも、まともなもんを食わせる、それは本来家庭の責務やと思うで。
家庭だけでは限界があるから集団に求めるとしたら、多様な人間関係能力の育成や。これも生きる力の中で最大級のもんやが、今の多くの若者にはこれが育ってない(去年の峯本さんの講演報告 通信No.51参照)。学校は軍隊風の組織やから、人間関係のそれに適合したもんになる。器用な子は表面的な付き合いにとどめ、不器用な子はいじめられ、殻にこもってたまに爆発する。「引きこもり」と「キレる」んは裏表の現象やろう。そやから、学校はカリキュラムを根底的に組替えて、異質な個性を尊重しあうような人間を育てる、いうことに特化すべきや。それはタテマエの説教やなしに、そういう生活を実際に味わうことによってのみ実現する。フリースクールとはまさにそういう場を目指すもんや、とぼくは理解してる。
日本の教育がそういう風に変わる可能性は限りなくゼロに近い。多くの親も教師も、共同やなしに競争原理に生きてて、子どもをそういう方向に育てたがってるからな。となると、違う価値観に立つ家族は、そこから抜ける以外にないわけよ。
 脱学校の社会 (現代社会科学叢書)
脱学校の社会 (現代社会科学叢書)
イヴァン•イリッチ(著), 東洋(翻訳), 小澤周三(翻訳) / 東京創元社 / 1977年10月20日
<内容>
現行の学校制度は、学歴偏重社会を生み、いまや社会全体が学校化されるに至っている。公教育の荒廃を根本から見つめなおし、人間的なみずみずしい作用を社会に及ぼす真の自主的な教育の在り方を問い直した問題の書。