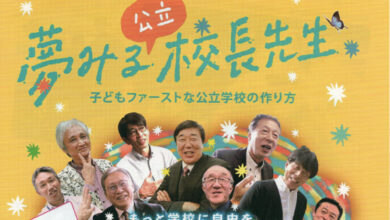高校の中退防止のために~ 子ども自立保障を明確に意識した高校教育
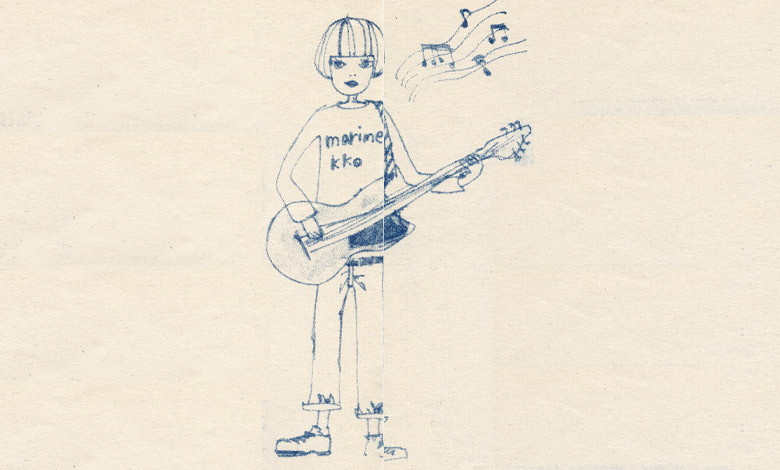
弁護士 峯本耕治
東北関東地方にとんでもない大地震が起こってしまいました。余りにも壊滅的な被害にショックを受けています。仙台、岩手•三陸海岸は昨年夏の家族旅行で訪問したばかりの場所ですので、あの地域で多くの人が亡くなり、あの美しい町並みや風景がほとんど全て失われてしまったと思うと、本当にいたたまれない気持ちになります。ほんの直前まで、こんなことが起こるとは想像すらしていない中での余りにも激烈な出来事に、あらためて世の無情さを感じています。
大地震が発生した3月11日の午後3時前頃、ちょうど私は、東京の霞ヶ関で、文部科学省の会議に出席していました。全国の教育委員会の指導主事が集まった連絡会議で、文部科学省が過去3年間実施してきた学校問題解決支援事業についての報告の会議でした。私は滋賀県教育委員会による「弁護士等の専門家と連携した学校問題解決支援事業」についての報告のために参加していたのですが、私たちの報告が終わって、しばらくして、私自身も経験したことがないほど激しい揺れに遭遇し、会議も途中で中止になりました。
ところで、この滋賀県の「弁護士等の専門家と連携した学校問題解決支援事業」の取り組みとは、具体的には、子どもの自殺事件などが発生したときに弁護士が緊急対応として学校や教育委員会に対し様々なアドバイスをしたり、1ヶ月に一回程度の割合で、子どもの問題行動や困難な保護者対応ケースなど、様々な学校問題についての個別の相談に応じる活動です。この相談活動の中で、高校ケースについての相談も多数あり、激しい問題行動を繰りかえしている生徒に対する退学処分の可否•手続についての相談や、逆に、中途退学をどのように防止していくのか等の相談もありました。一般的には知られていないことですが、現在、全国で年間約10万人の高校生が中途退学している現状にあります。10年で100万人の中途退学者を生んでいるわけで、実に多くの子どもたちが中退していっているのです。その背景としては、①経済状況•雇用環境の悪化、家庭の貧困•経済問題の深刻化により、子どもたちが希望を持ちにくい社会になってきている中で、学校の求心力は一般的に低下してきていること、②5教科中心、講義型中心の教育には限界があり、子どもたちにとっての学習意欲を持ちにくく、自尊感情•自己肯定感が満たされる「居場所」とはなりにくいこと、③家庭の愛着環境の悪化•教育力の低下•いじめ問題に象徴される友人関係のしんどさ、小•中学校におけるドロップアウトや「居場所」を見出しにくい学校環境の中で、自尊感情•自己肯定感が低い子どもたち、人への基本的信頼感が低い子どもが増加していること、④そのような育ちの環境の中で、対人関係能力•コミュニケーションスキルの低さ、感情コントロール力の低さ、暴力の学び、規範意識の低さ、主体性の低さ、他者共感性の低さ等の発達課題を抱えた子どもが増加しており、それが様々な問題行動として表現され、高校段階において、それが懲戒処分の対象となり、退学処分につながるリスクを高めていることなどが、挙げられると思います。
しかし、今の日本社会では、普通に仕事を得るためにも高校卒業資格は不可欠と言ってもいいものです。就職していく生徒にとっては、高校はまさに社会に出るための最後の準備期間ですし、大学等への進学者にとっても、いわゆるクラス制、担任制や生徒指導体制に基づいて丁寧に発達保障を行うことができる最後の機会です。その意味で、中途退学を減らしていくことは、子どもたちの自立保障、発達保障のために本当に大切なことです。
私自身は、中退を防止するためには学校の求心力を高めるしかなく、そのためには、何よりも、学校が、より明確な目的意識を持って、より積極的に子どもの社会的自立•自律力を育てることを目的とした教育を実践していく必要があると考えています。そして、そのことを、学校が子どもや保護者に対し積極的に提示していく必要があると考えています。
具体的には、少なくとも次のようは方策は効果的だと思うのですが、どうでしょうか?
- 入学時や学年初めの全体指導や個別の面談•オリエンテーションによって子どもの思いや希望、悩みや自分自身が考える課題を聞いた上で、学校として「子どもたちが社会的に自立•自律していくためにどのような能力やスキルを身につける必要があるか(例えば、自尊感情を高める、コミュニケーション力、他者共感力•尊重力•協調力、自己表現力•自己主張力、ルールの尊重力、規範意識、利害調停•紛争解決力、感情コントロール力•非暴力、情報リテラシー力、自己客観視能力等)」を積極的に提示し、「高校生活はそのトレーニングの場であること」、「学校•教師が全力でサポートしていくこと」「そのために、時に厳しい指導やルールの厳格な適用を行うこと」を明確に伝えること。
- その上で、教職員が、教科指導、生徒指導、クラス運営など、あらゆる教育場面で、これらの社会的自立力•スキルを育てることを明確に意識した教育や指導を行うこと。
- 講義型を可能な範囲で修正し、グループ単位で子どもたちが主体的にかつ協力して取り組める授業、作業•実践•実技型の授業、選択型授業等の積極的導入。
- 職業体験、社会人講師の招聘、ボランティア体験等による職業的自立を明確に意識した教育の定例的•継続的な導入。
- ケータイ•ネット教育、メディアリテラシー、対人関係スキル、食事や栄養に関する知識、金銭管理についての知識、消費者としての知識、労働の意義、性教育や男女関係に関する教育、DV防止や非暴力の教育、家族を持つことの意義や家事•育児のスキル、社会のルール、薬物の危険性に関する教育等、社会の構成員として生きていくための基本的な知識や情報の提供、様々なスキルを身につけるためのトレーニングの計画的•制度的な導入。
- 生徒会活動の活性化やピアサポート•メディエーション等による子どもたちの自治力、自律力を高める取組み、
- 外部人材•地域人材の活用等による部活動の活性化等、
- 高校卒業後においても、進路、仕事や生活上の悩み等を相談できる相談担当教員の配置などのアフターケア体制の整備等。
 子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
清水克之(著), 佐藤拓代(著), 峯本耕治(著), 村井美紀(著), 山野良一(著), 松本伊智朗(編集) / 明石書店 / 2010年2月5日
<内容>
子ども虐待と貧困との関係を乳幼児期から青年期までの子どものライフステージに沿って明らかにする。執筆者のまなざしは、親の生活困難に向けられ、子どもと家族の社会的援助の必要性を説き、温かい。貴重なデータも多数掲載している。
 子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
小林美智子(著), 松本伊智朗(著) / 明石書店 / 2007年12月6日
<内容>
公権力の介入を求めるまで深刻化した子ども虐待。だが介入は虐待防止の切り札といえるのか。2005年の日本子ども虐待防止学会シンポジウムの記録を基に編まれた本書は、日英の経験をふまえ、虐待を防ぐために本当に必要な「ケアする社会」を構想する。
 スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
山野則子(編集), 峯本耕治(編集) / ミネルヴァ書房 / 2007年8月1日
<内容>
はじまったばかりのスクールソーシャルワーカーの活躍を描く。スクールカウンセラーや養護教諭とともに様々な問題に悩む親子に、社会的問題を含めて解決にあたる事例を紹介します。今までにない児童生徒へのアプローチに非常な関心がもたれています。
 子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
峯本耕治(編集) / 明石書店 / 2001年12月12日
<内容>
先進的なシステムをもつイギリスの児童虐待防止制度の詳細と、実際の運用状況を具体的に紹介する。ライン等も示し、問題点にも触れる。