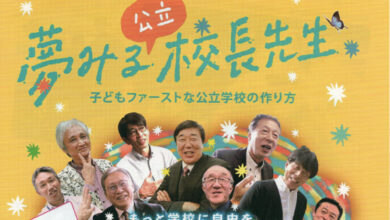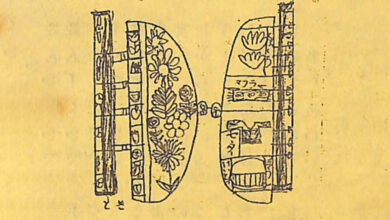本当の教育とは ー子供・親・教師ー
40年余の教師生活の懐古は悲喜こもごもである。飲酒・喫煙・暴走族・集団喧嘩・不倫等々。その度に処分の職員会議が夜遅くまで繰り返される。揚句には職員室、校長室が焼けた。
ただ昨今のナイフを所持して命を狙うような子供はいなかった。子供はスリルを楽しんでいるようで 教師にも余裕があった。これは当時と現代とのマスメディアの世界の違いであろうか、今のような不安感はなかった。
祖先崇拝から忠君愛国、戦後の民主教育から今また“日の丸・君が代”の法制化で現場の教師は押しつけられても拒否不能になってゆく。教育するという意義、内容が時代と社会事情を背景に推移する中で、本当の教育とは何なのか、子供の荒れ、子供の不登校、戦慄するような殺傷事件等々により 子供と親と教師が互いに責任を転嫁して対立させられている今、じっくりお互いの事情を受けとめ知恵を出しあって行くことだ。
私は喜寿も過ぎて振り返って教師をしたことを肯定するようになった。専門教科では無い総合学習として実践を重視する家庭科には常に不満と疑義があった。それをカバーするために私は文部省の指導要領を超えた今日的課題を授業に取り込む工夫をして、心の償いにしてきた経緯を憶う。幸いなことに大学進学の枠に填った学校ではなかったので他教科の教師の協力も得られた。文部省の役人が「生活者」という言葉さえ嫌悪していた時代に 男女共修の家庭科を主張し、「気狂いだ」と決めつけられたりした。
当時授業のモデルがあるわけではない。戸惑いながら試行錯誤し 生徒と一緒に泣き笑いながら続けた基礎学力の実践の場としての家庭科の総合学習が 生徒の人間形成にどれだけ役立ったかは分からない。
ただ 当時私が共に学んだ生徒たちが毎年正月に集ってもう40回に及ぶ。先生が生きている間は続けると聞けば教師名利につきるのである。
家庭科の教師として、私は父親の亡い子供を育てながら「家族の愛」を語り続けた。
教えるということは希望と夢を語ること学ぶということは 誠実を胸に刻むこと といったのは詩人アラゴンであった。
教師の一言が生徒の心に釘を刺したり、教師が生徒に励まされることも暫々だった。思うに人と人の触れあいの中に芽生える人間らしさが心を通じさせる。教育の原点は通じ合う心にある。この当たり前のことをしみじみ懐かしむ。
本当の教育とは 子供の感性が磨かれて 自分の力で考え感じ自立出来る誠実な人間を育成する仕事であり、教育された子供たちは日本の未来そのものになるだろうと願う。
2000年 2月16日