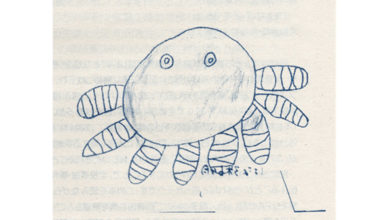それは何故なのか
曽我 陋
その瞬間のことをいまも時々思ってみることがある。90年7月6日の朝のことだ。その日、高塚高校では期末テスト期間に入っていた。
「急げ!」「遅刻だぞ!」グランドに沿った外の歩道に互いに距離をおいて2人の教師が立ち、登校する生徒に声をかけている。門の内ではコンクリート壁の内側の鉄製格子門扉の後部に手を当て、押し出す寸前の態勢で腕時計をにらみつつ、声をあげて秒読みし始めた教師がいる。その数メートル先の隙間を小走りに駆け込む生徒、わざとゆうゆうと通り抜ける生徒。門の後ろの大時計は8時29分をさしていた。
校門当番に向かう前にこの教師の腕時計は秒単位までおこたりなく確認してある。門扉に掛けた手と腕に力が入る。「9,8,7,…」大声でカウントダウンし始めた教師の脳裏に、過去に幾度かスカートやカバンを門扉で挟んだり、足や腰に当てたりしたことや、時には閉めた門扉を押し返されて「取り逃がした」生徒たちのことが浮かぶ。(クソッ、今日こそは定刻キッカリに門をしめてやる)「5,4,3…」
投手の振りかぶった腕からうなるような球が打者に向かってくる。グッとバットを握った打者の手指に力がはいり、その瞬間に向けて足と腰と肩とが回転運動にはいる。秒読みする教師はこの学校の野球部の指導者でもあった。その厳しい指導が、県大会でも上位進出するかたちで実りつつあった。以前の勤務校では熱心さが高じ、つい野球部員生徒に暴力をふるい、とがめを受けた前歴をもつ。しかし、この教師のいわゆる体感教育流のその熱心さは、かえって反抗する生徒を威圧し服従させる押しのきく教師として「評価」(利用)され、新設間もないこの高塚にひっぱられたのである。
そればかりか遅刻指導という名の時刻に合わせ門を閉じる「凶育」にも発揮されることになってしまった。しかもこの遅刻指導ゲームには野球にある肝心のルールが無い。ハイ!「一、ゼロ、GO!」教師は一気に全身で軽自動車なみの重量のある駒の付いた門扉を押し出した。
向かってくる白球を狙い違わず打ち返すためにバットは振り出されたのだ。開いていた門扉と外壁の間がみるみる狭くなる。そこへ1人の女生徒がつんのめるように頭を前にして飛び込んできた。そして◆◆◆。学校が最初にしたのは現場の血を洗い流すこと、そしてテストの実施だった。
「教育のかけら」もないこのような粗暴で滑稽な狂気の行為が公教育の現場で日常的に行なわれていた。だが、教師も生徒自身も、そして親たちも「社会」も死者の出るまで誰にも辞めさせられなかったのだ。そして類似の行為が今もやめさせられずにいる。
それは何故なのか! 僕はいまもそれを思いつづけている。