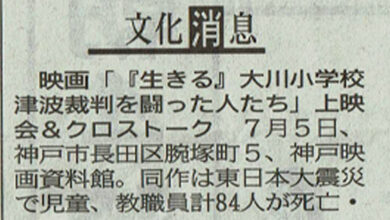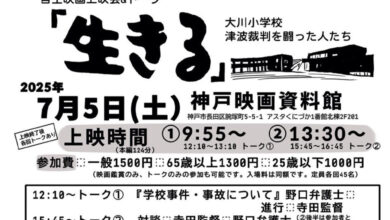新たな学びの場としてのフリースクール [講演]

神戸フリースクール 田辺克之
先ほど森池さんから紹介されましたようにー13年前というとちょうど私が明石でもともと冬夏舎という学習塾をやってたんですけれどもーその学習塾に不登校の子どもたちが何人かいて、保護者の方の依頼もあって明石フリースクール冬夏舎という名前に変えたのが1990年だったんですけれども、地震で全壊してしまって移ってちょうど6年目。13年間不登校の子どもたちと関わってきて学校の様子が見えてきたんですけど、石田さんが学校に潰されたというか、ちょうどフリースクールを始めたばっかりだったんで、その時に「学校がやばい。学校が病んでいる。」というふうにすごく感じたんです。
その後、龍野の内海平君ー小学校6年生が学校の先生に拒絶されて往復ビンタを食らって、その日に帰るなり裏山で自殺しました。平君のお父さんー内海さんには何回か私たちの講演に来ていただいていますけれども学校の先生です。お母さんも学校の先生です。おばあちゃんも学校の先生でした。そういう教育環境の中で育った平君は素敵な少年でした。でもお父さんー内海さんが何回か言われたことは、「平に『学校は休んでええもんやで。』ということをインプットしておけば良かった。」って漏らされたんですけれども。今、学校が子どもたちの上に覆い被さっているというか、「もし学校へ行けなかったら僕の明日はないんや。」と平君は考えたと思うんです。その数年後に須磨の快速電車に飛び込んで自殺した県商という垂水にある商業高校の1年生、私はお父さんから遺書を見せてもらったんですけれども、「私が死ぬからいじめんとって。もういじめんとって。」という2通の遺書と、「死ね」とか「ぐず」とかとにかく落書きされてあった学校のノート、そういう証拠を持ってお父さんは県商へ行ったんですけれども、校長は「学校にはいじめはありません。個人的なことじゃないですか。」というふうな形で学校は対応しなかったんですね。
その後、すぐにまた多紀郡今田町というところで中学2年生の男の子がクラブのコーチに拒絶されてその日に自殺しました。ちょうど石田さんが校門で潰されてから兵庫県内ではあちこちで子どもたちが自殺あるいは死亡するという事件がありました。
そして、少し離れていますけれども広島の三原というところで風の子学園という姫路の教育委員会なんかがお勧めの教育施設があって、そこではスパルタ教育というのがすごく流行っていたんですね。当時、15年程前は不登校を克服するっていうのは初期の克服がすごく大事で、絶対的にスパルタ教育っていうのがもてはやされたんですね。本人の問題だっていうふうに集約されていましたから。それで、そこの風の子学園というーきれいなきれいな小島にあるんですけれどもーそこでどういう教育が、あるいは学園の運営がやられていたかというと、まさに「体罰が教育や。」と園長は言ってるんですけれども、コンテナを二つ置きまして、何か罰則をするとそのコンテナー真っ暗なコンテナーに閉じ込めて、たまたま二人の少年が体罰を受けて入ってたんですけれども、園長が酒を飲んで彼らを入れてんのを忘れたんですね。コンテナの中っていうのは45度以上に真夏はなるんですよ。それで、園長が気付いた時には二人は熱死してたんです。二人とも肉が出るほど喉を掻きむしって死んでたんですね。それがやはり13、4年前の事件なんです。それで私たちは毎年ピースランという行事をやってます。神戸から三原まで約300kmあるんですけども、走って追悼をやろうという。最初はですね、新幹線で三原まで行ってたんですけれどもコンテナの前に立つと何か涼しい気持ちで来れないような思いがあって、「走って行こか。」って私が言い出したものですからーまあフリースクールの行事というのは誰か言い出しべえがいて、そしてそれが実行されていくわけですけれどもー言ったものの日が近づいて来るとどうも自信がなくて、私は来年60になるんですけれども51の頃で、言った限りはーというんで走る練習を始めたんです。明石公園の周りに剛ノ池という池があってその周りが約1kmあるんですけれども、とにかく1km走るとあへあへの状態で「これで広島まで行けるわけないわ。」と思ってたんですけど、まあ毎日5kmくらい走れるような状態になって、しかもどんどん記録が伸びていくんですよね。50になっても自分の肉体は捨てもんやないとその時すごく感動しました。だんだん衰えていくだけやと思っていた肉体がそうでもない。走り始めて腰痛が治りました。だから子どもたちと毎年広島まで行くことで体力を維持してるかなと思っているんですが、今年も8月4日から9日まで神戸から広島に向けて走ります。そのコンテナの前に立つと「ああ、また来てしまった。」と思うんですが、「ここで死んだんだよね。」って思うんですよ。子どもたちもその前で追悼会をやったりあるいはバンドをやったり毎年いろんなことをやるんですけども、不登校してて親が困ってしまって教育委員会に相談に行ったら「いい場所あるよ。」って薦められて連れて行った、それが風の子学園なんですね。「まさか自分の子どもがコンテナの中で殺されて亡くなって帰って来るとは思ってなかった。」と実際に亡くされたお父さんー姫路に住んでおられるんですがー数年前に話を聞きました。
「どうしていいかわからない。自分の子どもが不登校になったらどうしていいかわからない。」という状況が10年前にはすごくありました。実は私も別に不登校の専門家でもなければ、心理学とか教育学とかっていう学のつくのがすごく嫌で勉強したことも齧ったこともないんですけども、たまたま学習塾をやってて、親たちが不登校の子を抱えて昼間開けてくれないかというんで、まあ1日開け2日増えてというような感じでフリースクールが。でも当初は学校の真似事をしてたんですよ。とりあえず戻った時に子どもたちが楽になるようにということで、時間割を作ってですね、英数国理社みたいなものを教えるということにポイントを置いてたんです。数か月ほどして毎日通っていた女の子とそのすぐ後に入った女の子2人がパタンと来んようになったんです。それで彼女の家に「どうしたの?何日も来なくなったんでおかしい。」って電話したんですね。そしたらお母さんがバツが悪そうにですね、「もう行かないと言ってます。」と。「いや、何でですか?参考のために教えてください。」「『学校と一緒や。』って娘が言ってるんですよ。」僕はね、わからんかったんですよ、「学校と一緒やったら何であかんのや。」と。「学校へ戻るために塾してるんやから、学校と同じようやったら何であかんのや。」ということがわからんかったんですよ。それからね、「フリースクールというのは学校のミニチュアではあかんのや。学校の真似事してたらあかんのや。」ということを子どもたちが教えてくれたんですね。13年間フリースクールをやってきてどう変わってきたかというのは、私が変わってきたんですよ。大人がね、子どもに影響されて変わるっていうことがあるとは思ってなかったんです。子どもの話っていうのをちゃんと聞いたことがなかったと僕は思うんですね。また、私が少年の頃ちゃんと僕の言ったことを大人は聞いてくれなかった。「子どものくせに」とかですね、「半人前のくせに」って、こう育ってきた。そういう50年間っていうのはあまり日本では人権というふうなことに馴染まないというかね、最近ですよね。だから、きちっと自分の人権というふうな意識を持って生活してこなかった僕がですね、子どもの話をきちっと聞くということにも慣れてなかった。それからやっぱり変わってきました。しかもうちのおばあちゃんがですねー81歳になる母がこれはいつもよく言うんですけれど、「あんたな、他人の世話をするのはそりゃええこっちゃ。でもね、自分の息子を巻き込んでどうすんねん。あんた自信あるんか?」と。息子が小学校4年の時ー僕がフリースクール始めて2年目ぐらいですけれども、「おやじ、学校の数学の時間だるいわ。」「そうかだるいんか。どないすんねん?」「学校やめや。登校拒否宣言みんなの前でするで。」僕はね、ラッキーや思ったんです。上の30になる息子は学校大好きでサッカー少年でほとんど交流する時間がなくて、もし下の息子が学校行かんようになってフリースクールにおったら僕と時間をいっぱい共有できるわけですよね。仲良くなれるわけです。だから僕はラッキーやと思ったんです。それを見ておばあちゃんにですね、「あんたよう責任持てるんか?」って言われたんですね。実は自信がなかったんです。不登校してて他人の世話をしている限りはまあいいとして、自分の息子をね、「俺ちゃんとやっていけるんかな?」って。でも、まあその息子が今年で21になりますけれども今フリースクールを手伝ってくれているんですが、その生き方を10年間見てきて面白い。やっとね、おばあちゃんに「よかったわ、これでよかったわ。」とまあ言える。それぐらい不登校の生き方っていうのはーまあ何人かうちの子どもたちも来ていますけどもーむちゃくちゃ面白い。もし生まれ変わったら不登校さしてもらいたいと僕は思います。なぜかと言うと、学校へ行くことで大人のカリキュラムであるとか大人のセットしたものに子どもが乗っていく、あるいはその学習にしてもほとんど暗記であるとかーまあ言えばブロイラーみたいなもんですよね。餌を毎日きちっと与えられてそれをコツコツ食べていく。ところが不登校っていうのは地鶏みたいなもんで、自分で餌を探さなあかん。とてもたくましい。僕は今、フリースクールの中でお勉強っていうのはやってません。だから初めて来られたお母さんたちはちょっと不安になるんですね。「勉強しなくていいんですか?」っていうことです。学習に適齢期はないと思っているんです。高校ぐらいまでほとんど学校のお勉強をしなかった女の子が、今、栄養士になって沖縄へ行ってます。
私はものすごく教えたがりなんですよ。塾の教師をずっとやってましたから数学の教え方、英語の教え方のツボみたいなものを心得てて、いっぱい言いたいのね、いっぱい教えたいんですよ。でも子どもは拒絶するわけですよ。もううんざりしているわけ。学校のやらせ方に。あるいはその国語の百字帳であるとか算数のドリルであるとか、そういうのを繰り返しやらされている、そういう学び方にうんざりしてるわけですよね。だからそれを踏襲しない。どうするかというと子どもの意欲であるとか興味であるとか、それを大事にする。「子どもが主人公や。」とか「子どもが主体や。」なんて口では言うけど、そんな場所がこの日本のどこにある?子どもが決めて子どもがそれを実行して大人はそれをサポートする学びの場がどこにありますか?お題目だけなんですよ。多彩や個性やって学校では言ってるけど、それとは全然違うわけですよね。学校の出席なんか自由にすればいいじゃないですか。魅力ある授業があって魅力ある教師がいたら子どもたちは当然出かけていくわけですよ。魅力もない。だから管理する。門の扉を「せーの。」という感じで閉めてしまう。ゾロゾロまだ石田さんより他に何人も後についてたわけですよ。それで何で閉めるんですか、扉を。「おーい早く来いよ。」と声掛けしないの?今の教師は。
高塚高校の前でみんなが怒りを共有したと思うんですけど、それはすぐに風化するんですよね。だから僕らは広島までピースランっていうのを走ってますけども、まあかなりハードな炎天下を走りますんで、私もいっぺん自転車飛ばして鎖骨を折ったりしました。やはり熱射病に罹った人もおればちょっと危険も伴うんで「今年で止めよう」と思いながら、まあそれでも来て今年で10回目になるんですね。これは、風の子学園を忘れない。大人が良かれと思って閉じ込めた。そこで子どもが死んだんや。だからその時の不登校対策のまあ言うたらシンボルですよね。戸塚ヨットスクールもそうです。園長らはあれで良かったと思っているわけですよ。だから大人と子どもが対等じゃない世界に僕らは生きてるんですよね。
「共感する」と言いますけれども、不登校の子どもに共感できたら不登校の子どもたちはすごく楽です。でも周りの大人が、あるいは教師が共感するどころか指導するわけですね。指導するっていうのは上から下へっていう形なんです。「僕はしんどいねん。熱が出てお腹が痛くなって学校へ行くのがしんどいねん。」っていうのを身体で表現している子どもたちに、「そんなこと言うとってどないすんねん。」っていう形で子どもたちの声をあるいは信号を受け止めないで指導しちゃうわけですね。だからもっと身体の調子が悪くなって、とうとう行けなくなる。それでも親は不登校の子を車に乗せてまでして何とか連れて行こうとするんです。ある女の子は、階段の手すりに毎日へばりついて、それでもお父さんが無理矢理剥がすからすごい傷がいってるんですよ、人差し指に。手すりでついた傷なんですけど。フリースクールに来て見せてもらいました。「これあの時の傷やねん。」と。それを見せる度にお父さんは「悪かったな。」っていうふうなことを言うんですけれども、大人が子どものそういう信号をまともに受けるのに時間が掛かり過ぎるんですね。時間が掛かり過ぎる。
栃木県で2人の女の子が「もう疲れた。生きていくのに疲れた。」と言って団地の屋上から一緒に身投げしてるんです。最近も子どもの自殺がそんなに減っていません。そのほとんどが学校というものに対してなんですね。今、学校の先生たちが本当に学校が病んでると思ってるやろか?自分たちは競争に勝ち抜いて教師になり、昔に比べると豊かな条件でー給与にしろ年金にしろあるいは退職金にしろーそういう環境の中でその立場を維持するためにあんまり問題意識なく教師してるんちゃうか?与えられた環境を変えようっていう意識があまり働かないんじゃないか?たまたま私の妹も弟も教育委員会におりましてですね、意見をしょっちゅう交換するんですけども、やっぱり組織の一員というのは石田さんの頭を潰したあのロボットのような教師とあんまり変わらんですね。組織の一員であっても子どもの命を大事に思う教師が少しずつ何か変えていこうという意欲を出してくれたら学校は少し変わるかもわからない。けれどもすごいエネルギーがいるから良心的な教師は途中で断念してやめてしまうんですよね。でも先ほど言いました内海さん、平君が自殺してその後裁判を起こして教育委員会を相手取ってですね、しかも今まだ現役で内海さんは頑張ってますよね。そういう教師たちが増えてきたら日本の学校も少しは変わるかもわからない。
でも、やっぱり今13年間もフリースクールをやってきてもう大丈夫かなと思ったらそうではなくてですね、不登校の相談はやっぱり続いていて、子どもが動揺する前にお母さんたちがパニックになっていて神経科の受診がすごく増えてます。「神経科の治療ってほとんど投薬や。」ってうちに来てる神経科に通ってる人が話してましたけども。私のところにぜんさんという一人の中学の教師が来てるんですね。その人は登校拒否を4回してるんです。教壇に立つと生徒が怖いからって言うので廊下から教室へ入られへん先生なんです。生徒とトラブルがあってから自分は教師に向いてないと何回も言うんですけども、嫁さんがおり子どもが2人いるから何とか教師を続けようと言うんで、うちに今ウォーミングアップに週1回来てるんですね。それで子どもたちに混じっててもね、やっぱり薬でコントロールされてるからボーッとしてはるんですね。その人と時々話しするんですけども、大阪には登校拒否を起こしている教師たちのトレーニングセンターみたいなんが最近できて、その人は週2回そこに行ってるんです。教師たちも大変な時代だっていうのがすごくわかるんですけども、やっぱり学校がおかしい。だから教師たちが中で変えていくっていうのも一つだけど、もう少しフリースクール活動というかフリースクール運動を広めたらどうや?学校の存在がすごく大きくてその学校の比重を少し軽くするために不登校の文化ー先ほど言いましたようにブロイラーと地鶏の違いという、大人が全部セットしたやつを消化するようなやり方じゃなくて子どもたちが意欲を出して興味を持ったことを中心に考えて、それを大人がサポートしていくような新しい学び方ーそういう学びの場をもっとあちこちに作れば、そういう選択肢が子どもたちに与えられればと思います。
しかし、今、私とこに通っても通学扱いにはならないんですね。通学定期やったら半額なんですけれども。この間県とNPO協議会みたいなもんがあって、教育委員会が出前トークというか来はったんですけども、「たとえば公共機関ー体育館であるとかあるいは青少年科学館であるとか、そういう公共機関を不登校の学童に無料開放して欲しい。」っていうようなことを頼んだんですけども、それは無理なんですね。だからフリースクールをやってて体育館を利用するんですが、その時は一般料金を払わないかんわけですね。だからね、不登校に対する考え方をね、もう少し変えて欲しい。どういうふうに変えたらいいかというと、追い詰めないようにする。不登校の子どもたちも学習権があるわけですから、しっかり保障して欲しいんですね。最近増えてきたのは適応教室、あるいは別室登校ですね。教室へ入らへんのやったら保健室あるいは相談室図書室も。例えば私とこのフリースクールの真っ直ぐ上にある山手中学というところは図書室を別室登校にしてます。ある所では運動場にプレハブを建ててるところがあります。「ここまでおいでー。」という感じですね。「ここまで来たら出席扱いになるよ。」と。加古川にいた男の子は門の前まで行くねんけれども、そこでお地蔵さんみたいに重くなるんですよ。誰が引っ張っても入れないんですよ。それをですね、お母さんもお父さんも必死になって「お前な、運動場に足つけたら出席なんねん。そやから足だけつけて帰ろう。」言うて。そないまで何でせなあかん。「学校って何やねん?」と思いませんか?学校というのは良かれと思って大人が作ってきたシステムであって、子どもが楽しく学べる場所を作ろうというんで今まで百何年間続いてるんですけども、もうかなりボロボロになって中身は崩れかかってるんですよね。
前はスクールカウンセラーの養成と適応教室の充実っていうことで、一生懸命文部科学省が45億円の予算を組みましたね。「もう、ええ加減にしたらどうですか。もう、民間施設を認めたらどうでしょう。」と思うんですが。そして、学校だけやない、学校へ行かなくても大人になれるし、学校へ行かなくってバイパスは色々あって、文部省もそういう大検であるとかあるいは通信高校であるとか定時制であるとかっていう普通のルートと別のルートもちゃんと備えてくれてますんで、まあいろんな生き方や選択がOKなんですけどもー。そういうふうに学びっていうものも全部大人が決めてしまって、行けない人は適応教室でトレーニングさせる。「適応」っていう言葉も、あるいは「登校」っていう言葉も皆お上的な発想なんですよね。そんなん頭にくるのよね、子どもたちは言わないけども。「『適応』って何やねん。坂本龍馬が『適応』したんか。『適応』せえへんかったから時代が動いたんちゃうんか!」と子どもたちは言いたいと思うねんね。大人は良かれと思って腐ったようなシステムを子どもたちに提供して、それに適応できひんから「適応教室」。アホかっちゅうねん。そういう平気で不登校できる子どもを育てたいっていうのが僕の信念なんですよ。
学校の存在を軽くしよう!バカみたいに「子どもが学校へ行くのが当たり前」やと思ってる頭の固い大人たちを砕いていくために、「学校も一つの選択肢やで。行ってもええけど、行かなくたって俺はちゃんと生きてるで!」っていうのをうちの卒業生らが証明してくれてます。だから学校に潰された石田さん、あるいは風の子学園の子どもたち、あるいは平君ーたくさんの若くして亡くなった子どもたちの声が「もうええ加減にしてよ!あんたらもっと考えたらどうやのん!」と叫んでいるように思うんですね。この日を境にまた今年一年間学校とがっぷり四つになって学校の問題を考えて行きたいし、あるいはフリースクールっていうものをもっと楽しい場所にしていけたらと思っています。