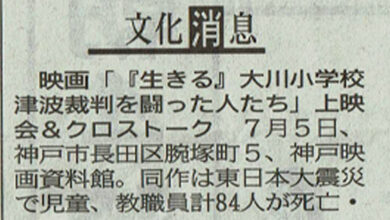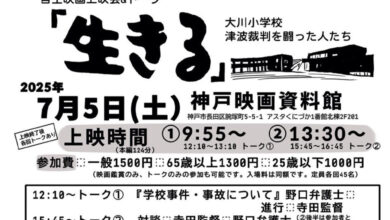質疑応答記録

質問 1
虐待を受けたなど原因が100%本人にあると考えられない少年犯罪ー少年犯罪でも本人の責任だけじゃなくて虐待ということがその背景にあるーでも全ての罪が本人にあるような判断ばかりが日本ではなされているように思います。アメリカなどでは原因をきちんと調べた上で過去に本人に対して虐待をした人が例え何年経っても逮捕されることがあると聞きました。どうして日本では原因を調べてきちんと判断しないのでしょうね。唯、面倒なだけではないのでしょうかね。
いろんな原因があると思うんですけれども、マスコミなんかの報道で見るとですね、やはり何か「こういうことをやった。」という行為の内容については非常に詳しく報道しています。「こんな酷いことをしているじゃないか。被害者がこんな目に遭っているじゃないか。」ということは報道されるんですけれども、どうしてこういうことになったかということはあまり報道されない。そういう報道の仕方にも一つの問題があるとは思いますが、それから虐待の問題などについても、親が虐待をしたことについてーまあ親とは限りませんけれどもー周りの大人が虐待している場合にどうしてあまり罰せられないのかという質問なんですが、一つは日本人の考え方の中に「子どもというのは親の言うことは聞くもんだ。」という極端に言えば親の所有物と言いますかね、そういう考え方を感じますね。日本ほど親子心中ー子どもを殺して親も死ぬーということが多い国はないと思います。警察の人もこういう考え方に影響されているのか、親が子どもを痛めてもあまり取り上げない。実際よほど酷い場合ー死んでしまった場合は別ですけれどもーなかなか取り上げない。唯、アメリカなんかの場合だと親が子どもを虐待するとかの事例には非常に厳しく対処しているのでー笑い話みたいなものなんですけれど、学校の先生が子どもを殴ったらあまり日本では問題にならないんですが、例えばアメリカに修学旅行に行きますよね、生徒がホテルの集合時刻に遅れて来たので先生がぶん殴ったんですね。すぐ警察が来て先生は連れて行かれちゃったんですね。だからそういうふうに感覚が全然違うんです。例えば最近大分状況が変わってきましてですね、警察も大分取り上げてくれるようになってきましたし、また周りの人もかなり敏感に警察あるいは相談機関に申し出るようにはなってきていますので今後大分変わっていくのではないかとこういうふうに思います。
[野口先生]
少年院にいる子どもたちの半数以上が虐待の経験者だと先ほどの話でも言いましたけれども、その少年院にいる子どもたちは1回で入るわけじゃなくて何回か警察に補導されたり捕まったりして何回目かに入ってくるわけですので、そうするとそういうことにほとんど気が付かなかったんですね、警察の方が。つまり、虐待を受けつつ人を殴ったりとか物を盗んだりだとかいうことで言わば警察のお世話になる。そして家庭裁判所でも少年院に行かせようといった話になったプロセスの中に現在進行形で彼は被害者でもあるという事実が宿っていたケースというのがあるかもしれませんね。しかし、そういう複合的な目で見ないで一括りに非行少年ー「非行を何でやろうとしたか?」「欲しかったからだ。」とかね、「誰かの影響を受けたから。」という程度の見方しかしてこなかったではないかと。そして児童虐待防止法という法律を更にきめ細かくしていった時に、学校の先生が警察ではその少年は犯罪の容疑者としてあるいは非行少年として調べられているんだけれども、同時に被害者かもしれないという視点で見ていくということはこれから大いに進められることではないかなと思います。
[保坂先生]
親が子どもを叩くというのが当たり前みたいな環境ってあると思うんですよ。塾をやっている時にーわりと騒がしい塾だったんですよ。そしたら子どもが手を挙げて「何で先生、叩かへん?」と言うんですね。「君はこういう時に家では叩かれるの?」と。そういう「騒いだら叩く。」っていう発想が子どもの中にすごい染み通ってて、学校で叩かれても当たり前みたいになっているんじゃないかっていう。私、キリスト教を破門されるまではずっと修道院にいたんですけれども、その修道院でよく日曜学校で話をするのに、内村鑑三っていうのは自分の息子がちょっと悪いことをした時に子どもをぶっ叩かんと自分を殴ったらしいんですね。バットが折れるまで叩いたいうて牧師が一生懸命「それが愛やねん。」とか言うて教えてもろたのを印象的に覚えているんですが。「その子を育てた責任は自分にあるんや。子ども殴ってどうすんねん。」というふうなことを何故か忘れられなくてですね、怒り方が日本人はおかしいんちゃうかというーそれは宣教師から聞いたんです。
[田辺先生]
児童虐待防止法というのがありますけれども、それは家庭だけのものを対象としている法律だろうと思うんですけれどもーそうじゃないかもわかりません。唯、先ほどの野口先生の話ではアメリカなんかでは修学旅行の引率教師が逮捕されるということですから、児童に対する虐待ということで言えば当然のことながら家庭それから学校でも虐待されています。クラブでも虐待されています。いろんなところで虐待されて大変だと思うんですけれどもね。そういう形で犯罪とリンクするような状態についてデーター化し、あるいは専門家ソーシャルワーカーというような人を配置することによってそういうふうなことが少しずつ明らかになるのじゃないでしょうか。
[森池さん]
質問 2
西区の一部の親たちはーこれは私たち自身の生き方にも関わるんですけれどもー高塚高校の偏差値がそれほど高くないので、この事件は起こったので、そうならない為に勉強を頑張って上の学校へ行けという教育をしていると聞きます。このような環境の中で人間性を失わず生きていくための心の持ち様を教えてください。
高塚高校が偏差値が低かったからという話は僕も聞きますよ。当時森安九段の事件で取材に来ていた時に。堂々と言っていた方もいますね。ですから関東と関西とを比べた時に、よく関西は本音の文化って言われますけれども、その本音がわかりやすいんで困るんですけれども(笑)。「石田さんの分まで点を稼ごう!」というのも本音なんでしょうね。教師のね。そして「そうだ!」と思う生徒たちもいたかもしれない。こういう事件が起きるとですね、やっぱり嫌なものですから非常に公言を控えるようになりますね。自分の在り方を問うのはみんな嫌ですから特殊化しちゃうんですね。あれはあの学校のことで、うちでは起きないと特殊化しちゃう。あるいはその子が特別な子だったんだと後でその事件を特殊化してしまう。やはり我がこととして考えればそういう言い方は出来ないと思うんですけれども。ですから良い本音を是非持って頂きたいなというふうに思います。
[保坂先生]
高塚高校の偏差値が云々という話の中にですね、例えば「神戸高校ではそんな校則なんかないですよ。」というふうな形のですね、何か一つ優越感と、それから歪んだようなものがあって、そして「皆そこへ行け。それ以外は落ちこぼれだ。」という階層行動みたいなものがあるので、そういうものがやっぱり日本の教育をダメにしているのじゃないかと思いますので、こういうことにつきましては、またフロアの方から後でも何かご意見があったらお願いしたいと思います。
[森池さん]
質問 3
フリースクールに通う子どもたちや、何か罪を犯した子どもたちなど、立ち直った子どもたちの例が挙げられることがよくありますが、その陰には長い時間掛かっても未だ立ち直っていないという子はいないのでしょうか。また、その子どもたちがお二人の手元を離れてからは、どう対応されているのですか。
確かに様々な形で抑圧を受け、そしてストレスを受けて自己否定を続けさせられて、それらの中で立ち直っていく子どももいるけれども、むしろそういう状況に置かれれば立ち直れない子どもも多いんじゃないかと。私、実は私の従兄弟ですけれどもー今56歳ですけどもー未だに座敷牢みたいな所に居ります。大学受験に失敗して、それからずーっと閉じこもっております。その間に大事にしていたお祖父さんは亡くなりました。お父さんも亡くなりましたので、一体後どうなるのかなと思っていますが。そのような大変悲惨は事例もあります。
[森池さん]
引きこもりがテーマの「home」という映画を見られた方も何人かいると思うんですけども、その7年間引きこもっていた彼を呼んで話をして、彼がね、「台風でも起こらんかなあ。」っていうふうに思ったわけです。「家が吹っ飛んでくれたら俺出れるよなぁ。」とか、それぐらい自分からは出るということは考えられなかったし、人が刺激したところで出なかった。だから大変苦しいんであって、「家が吹っ飛んでくれたらいいのにな。」っていうことをその人は考えていたわけでありましたけれども。一旦引きこもると、自分からはなかなか出られないし、それをしっかりと固めている我々周囲の責任もあるんじゃないかなと思います。立ち直るとか立ち直らないとか、不登校の場合は僕はそうは思わないんで、新しい選択やと思っていますんでー私の所のフリースクールは卒業がないんです。卒業は自分で決めるわけですから。「もうええわ。」というか十分納得できたら辞めていくわけです。その後どうなったかというのは、時々遊びに来ますから情報は聞きますけど。
[田辺先生]
引きこもりのことは私はあまり知らないのでよくわからないんですが、非行少年と接しててですね、全て私は神様みたいに私と接した子が100%全部良い人間になってますというーそういうつもりは勿論無いわけだし、いろんな事件、家庭の状況とか考えて、この少年が現在置かれている社会の状況がー例えば私のせいで明日から急に立派になるというーそういうものでも無いしですね、具体的に現実なかなか手を焼いている子どももいますし、またどっかへ行ってしまって行方もわからない子もいます。唯、だからと言って自分が何もしないでいるのかというのではなくて、自分は一体その子の為に何が出来るのかと。一旦は裏切られたように思えても、やっぱりその子の為になっているということはあるわけですね。私は保護司もしてますが、ある少年を何とか私が引き受けて、少年院に行くのを近くの保護司さんに頼んで仕事を世話して貰ってアパートも確保して貰って働かしたら、一週間したら家に逃げ帰っちゃったんですね。その時は非常にがっかりはしたんですけれどね、今から思えばそれまで友だちと一緒にいたのにですね、一人で寂しく一週間見ないで放っていたのが悪かったなという気がしてるんですけれども。唯、その後も接触し続けて、その子なんかは今もう27歳。「結婚して元気でやっています。」という葉書をくれたりして。まあそれは良かったから。それからシンナーやってた子がですね、ようやくシンナー止めてくれたと思ったら覚醒剤で捕まりまして、少年院に行く時に保護観察の反省文を書いていまして、「保護司さんには一緒に潮干狩りやら魚釣りに連れて行って貰って一生懸命やって貰った。」と。「自分がまた悪いことをしてしまって申し訳ないと思う。」と。自分の力が万能であるとかですね、そういったことは少しも思いませんけれど、やっぱり何かしら自分が出来ることをやってみたい。それが思いの外ですね、そういう子どもがそうやって成長してくれるということが一つの成功体験というのでしょうか喜びとなっているわけです。山でも登山してですね、必ず全部登れるとは限らんわけで、ところが登れた時の嬉しさを味わいたいが為に山に登って行くじゃないですか。まあそういう気持ちでやっています。
[野口先生]
先ほど会場で引きこもりの問題について取り組みたいということを述べておられた若い方からお話があったんですが、立ち直るという言葉に私もちょっとこだわって考えてみたいと思います。「保坂さん、立ち直ったんですね。」なんて言われることはあまりありませんけれども。それじゃあ立ち直ったということは、どっかで捻じ曲がっていたということなのかなぁというふうにも思いますけれどもね。例えば行為障害ということが言われましたね、あの事件で。まあ、さる国の大統領や政治指導者でですね、ありもしないことで戦争を起こすということもまあどうなのかなとも思いますね。何かをやればいい。何かをやっていればーつまりお仕事をして金銭を得ていればOKというふうに本当に言えるんだろうか。どうでしょう?人を自殺に追い込んだりー年間3万人死んでいますよね。その中に間接的に殺しているという闇金の取り立てがあるじゃないですか。「早く出せ。命を出せ。」と言って脅しまくってですね、そして取り上げると。引越し先も全部追い回してですね、それも仕事ですよね。それでそこから立ち直って引きこもると。こういうことってあるんじゃないだろうかと。つまり金銭を対価として得る労働が無条件に善とされる社会は終わったというふうに私は思っていますよ。これだけ無駄の多い、これだけ暴走も多い、これだけ人をむしろ殺めていく仕事も実はある。社会の中で自分という殻に一度籠って葛藤するーそして、その中で自分自身のリズムを見い出していく。しかし、見い出せない場合もあるでしょうね。これは非常に難しい問題でー例えば自室に籠って15年絵を描いている人って全然問題ないですね。そういう人もいますよ。陶芸家とかー引きこもりと言えば引きこもりかもしれないと。自分としか向き合っていないじゃないか。しかし、それはそれなんですね。何故、やはり引きこもりが問題っていうふうに言われるかというと、やっぱり本人がとても苦しい、死にたい。自分を自分として認められない。何を認められないのかというと、先ほど言った社会ー「闇金だって何だって働いている人は立派でしょ。」「みんな学校を出てるでしょ。あんた何で出てないの?何であんたドロップアウトしちゃったの?」と。自分で自分を責めるんですよ。それが猛烈に苦しいんですと言うんですね。ですから先ほどの自分いじめの話とも絡むんですが、そうやって苦しんで葛藤すると、今度は暴力となって自分の親にー地獄図になると。確かに社会問題ですね。ここから二つのアプローチがあって、「引きこもりは病気なんです。」と平然と言い放つ人がいますよね。ですから、それこそ薬でも与えて注射でも打たなきゃどうしようもないんだと。まあ極論すればですよ。それじゃあ僕は無いと思うんです。やはり社会の中で人を癒す機能、もう一回再生を勝ち取っていく機能っていうものが恐ろしく衰えているんだと思うんです、日本の社会に。その中で敏感な若い人、あるいは嘗て若かったー長期間ー56歳まで葛藤している人もいらっしゃるということで、しかしその葛藤を私たちは大事にしようじゃないかと思います。少なくとも暴力的に切り捨てる社会、病気だとかあるいはそういう人間に価値は無いとか、働いていないから駄目だとか、そういう暴力性というのは実はこの社会がとても持っている、あの校門がバーっと閉まってくるのと同じなんですね。そこんとこを一緒に掘り下げていく議論がこれから本当に必要になるんじゃないでしょうか。
[保坂先生]
質問 4
「無業者(職業に就いていない)」という言葉をご存知ですか。先日息子ー高塚高校3年生の保護者会の説明会で知り、抗議しました。両親の自営業の自己破産ーそこから不動産の明け渡しとかあるいは撤去とかそういうことがありまして、息子の遠距離通学が起こりました。そのために遅刻することに対して、担任は改善できてないと指導しております。担任や学級主任に6月30日の月曜日に両親が抗議をしまして、学年主任からは神戸市進路指導主任会議というのがあるそうですけれども、そこで無業者という呼称を改めるよう提案すると書いておりました。講師の方はどう考えられますか。
無業者というのは進路指導の中で、大学、短大、専門学校行き、就職ーそれに当てはまらない人が無業者等というふうに分かれたんです。進路指導の方は「今年の3月は5%あったから0%にしたい。」という発言があったわけです。それで6月30日の話し合いの中では文部科学省と厚労省がこの言葉を調査報告書に書いているわけです。そういう言葉なんです。
まさに今、自身の生き方そのものに、あるいは価値観そのものの前提に対する抗議だということだと思うのですけれども、こういうことについてコメントがありましたらよろしくお願いします。
[森池さん]
無業者という言葉自体を私ちょっと知らなかったものだから、それがどういう感じかっていうのが、ちょっと自分ではよくわからないんですけれども。どうやら学校の方の感覚を敢えて推測してみると、先ほど保坂先生が仰ったように「生業に就いてる者は良いんや。そっからはみ出とる奴はちょっとおかしいんや。」と。言ったらそういうような雰囲気が伝わってくるんですよね。例えば、「学校に来るのが当たり前だから、学校にこない奴はおかしいんや。どっか問題があるやっちゃ。」と。まあ言ったら、そういうような感覚に見えるわけですよね。ところが、今、いじめの問題で研究なんかしている人が、前はいじめられる側に問題があったなんていう言い方をしていたわけだけれども、そういう集団自体に問題があるんじゃないかという見方をする方が今、研究者の間では定説になっていると思いますし、それから「社会の中でそういう人を包み込めるようなシステムのない、そういう社会のシステム自体が問題だ。」と考えずに、「今の社会の在り方自体が絶対に正しいんだ。そこからはみ出たのは全部おかしいんだ。」という発想に繋がっているような気がしますね。
[野口先生]
10年前と全く今違うのは、その当時高塚高校事件の時にはバブルの真っ盛りで、やっぱり歩いている人の速さももうちょっとこの辺も速かったかもしれないなという気がするんですね。この長期デフレ不況の中で、やはり学校の先生ーなかなか世間の風が当たらないんですよ、他の方に比べてね。特に教師同士で結婚されている場合ーその親も学校の先生だったりとかというケースもありましてですね、個人破産したりですとか、そういう極めて厳しいプロセスを歩む子どもさんの家にどういう苦労があるのかと、あるいは、そういう置かれている立場がどれほど厳しいのかというふうに思いを馳せる視線が全く無いっていうのに私は驚きましたね、今の例を聞いて。どうやったら分かるのかと言ったら、これは難しいですよ。こういうことをわからない人は、それこそ校門は閉めてないけれども、やっぱり生徒の魂を、まだ今でも、こう切り捨てているんだなあというふうに思います、今のお話を聞いて。
[保坂先生]
私も無業者なんですよ。一度も定職に就いたことが無いんですよ、今まで。大学の非常勤講師というのはプータローみたいなもんでですね、それをずっとやってきて、いつの間にか何か市会議員になれと言われて市会議員になってーこれも非常勤ですから。ー一度も私はー多分死ぬまで定職に就けないんじゃないかと。もう後残すところ少ないですけれども、どっか定職ありませんか?という話ですけれどもー(笑)。まあそれでもほんとに生きていけますので、あまり気になさらない方がいいんじゃないかというふうに思います。
[森池さん]
今日の話でですね、やはり基本的には子どもたちの置かれている状況というのは大変厳しいということが、いろんな先生のお話でわかったのではないかと思います。やっぱりそれに対して愛情であるとか、あるいはそれをフォローするシステムとか、あるいは基本的な私たちの生き方そのものの価値観ーそういったものを変えていかないと、この問題は、こういうことをしたので解決しますというような問題でも全くありませんのでね。大変複雑な問題を孕んでおり、教育問題というのは正に政治問題です。その政治家がですね、先ほど保坂さんの言葉で言う大変乱暴な、大変表面的なことを見て「ああ、犯罪があるんだったら、これを厳しくする。」とか、あるいは「もっとビシビシ殴ってくれる元気な先生が出る法案を作ろう。」とかですねーそんなのないでしょうけれどもーあるいは様々な形で今の本当に自分たちの歪んだそういうものを直視せずに、間違った方向にどんどん行ってしまうという可能性がありますので、こういう場合に「そうじゃないんだ。」と。もうちょっとちゃんと考えれば、ちゃんと情報を処理すればー物事を考えればーそんな危ない話はないんですけれどもーそういうことがまかり通っている世の中に対して異議申し立てをしなければいけませんし、考えていかなければならないということで、こういう会も開かせて頂いていますので、是非色んな意見を出して頂きたいと思います。
[森池さん]
質問 5
子ども会とか学校の文化祭もそうなんですけれども、父兄会でも子どもたちの行事を大人だけで全てすることに対して、テーマも子どもも一緒に検討出来る方法があれば教えて下さい。
時間になってしまったので先に失礼しますが、一つだけ言いますと、今、日本は有事法制とかイラク派遣法とかーああいうのを見ればですね、何か根本的に駄目な方向に行ってるなという気がする方も多いと思うんですが、しかしですね、まだまだ捨てたもんじゃないんです。実は、外交安保に関しては確かに国会の9割はそういうものに賛成するような状況にありますが、しかしだからと言って戦前の魂を国家が支配する社会ー所謂国家主義的社会ーそれを全ての方が志向しているようなところには来ていません。しかし、これはまだ今のところはという意味ですよ。それで、是非皆さんに今後やってもらいたいと思うのは、先ほど出た引きこもりの問題、あるいは児童虐待防止の問題、そしていじめや命を考えるという、そういう子どもの安全をサポートしていくという領域にはですね、まだ市民の側の主張というのが、これは強く反映されているんですよ。しかし、少なくとも今は反映されてますけれども、不登校の現場でもですね、「やっぱり登校拒否なんて認めるべきじゃない。文部省がこんなことを認めたから引きこもりが100万人になったんだ。」という意見が台頭してきています。今、とても重要な時期だと思うんですね。だからこそ市民の、その地域におけるいじめの問題でも虐待の問題でも引きこもりの問題についてもですね、どうやって可能性を引き出していくのか、生命を支え合っていくのかという地域での活動がとても意味を持ってくる時代ですので、是非頑張って下さい。
[保坂先生]
私も大変同感と思うんですけれども、学校とか親とかって待てないんですよね。常に何か形あるものを作らなきゃいかんというふうに思いがちなんで。もう少しじっくり待って、自発的に子どもたちが動けるように準備するには相当な時間が要ると思うんですよ。しかも今まで散々「あれせえ。これせえ。」って言ってやらしといてですよ、「ハイ、今から自由にやりなさい。」って急に言われても、それは出来ませんよね。それはかなりこちらが準備をして、誘い水も出しながら育てていかないかんので。「ハイ、じゃあ今日から貴方たち自主的にやりなさい。」なんてそれは出来ないに決まってますよね。そうすると「じゃあ出来ないから、ほとんどこちらで準備してやるから。」ということになるんですね。本当にやらせてみればいいんだけれども。そのプロセスこそも一つの教育なんでしょうね。
[野口先生]
要望
この集会に初めて寄してもらいました。簡単な話ですけれども、教育の問題を聞いていて、昔の明治維新の言葉で「富国強兵」というスローガンーそのために学校を軍隊のような形で利用するって言うのか運営するって言うのか、そういうような流れがずっと根付いとるんちゃうかな?と思いました。同じくスローガンに「ざん切り頭を叩いてみれば、文明開花の音がする。」というのがありましたが、日本ってまだまだ教育、政治、そして経済の問題で文明開花されてへんなあと思いました。その、本当の文明開花の為に、この集会を主催された実行団体とか会場を借りた方ーそういう人が中心になって兵庫県の大きな教育大運動が生まれるようにお願いしたいなあというふうに思います。