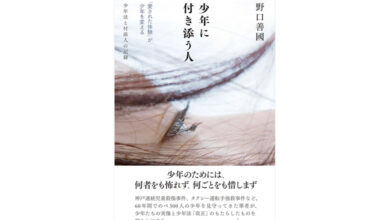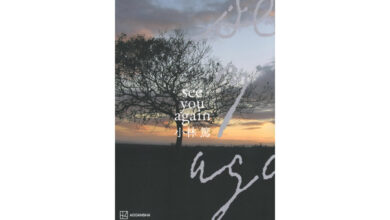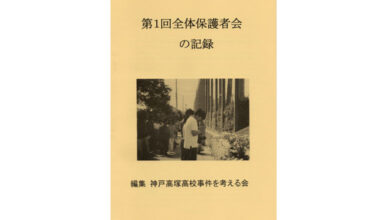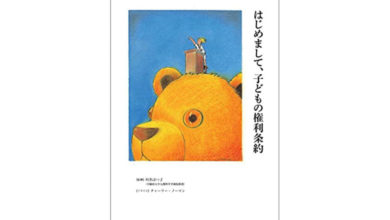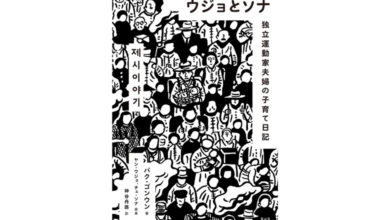ホンの紹介
ホンの紹介『相模原事件とヘイトクライム』他
『相模原事件とヘイトクライム』
保坂 展人 (著) 岩波書店 2016年刊 562円
<内容紹介>
2016年7月に起こった相模原事件は、重度の知的障害者が襲撃され、19名が亡くなるという戦後最悪の被害を出した。怒りと悲しみが渦巻くなかで、加害者の障害者抹殺論を肯定する声も聞かれている。
日本社会に蔓延する差別意識が最も残酷な形で現れたのが相模原事件だったのではないか。事件の本質を探り、障害者差別の根を断つ方途を考える。
『原発危機と「東大話法」―傍観者の論理・欺瞞の言語―』
安富 歩 (著) 明石書店 2012年刊 1,728円
<内容紹介>
戦前の日本と福島第一原発事故に共通する欺瞞的言語体系である「東大話法」を検証し、欺瞞的言語の悪質性を明らかにするとともに、欺瞞的言語を生み出す日本社会の構造を明らかにする。