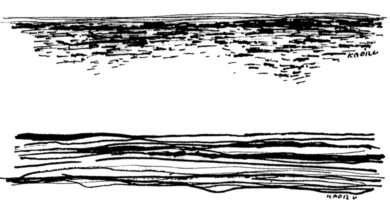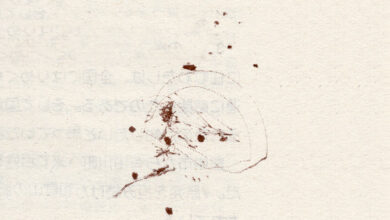石田僚子さん追悼10周年記念特集
 2000年7月8日 (土) 晴天 この日も朝から暑い日でした。11時頃から準備の人達が三々五々集まり、飛田さんが作ってくれた(毎年ありがとうございます。)『石田僚子さん追悼10周年記念』の垂れ幕を前に掲げたり、講演者の本を並べたりしました。会員の方はもとより、太陽の子保育園のもと保母さん保父さんに大変助けられました。予定では、その時からオルガンの音が鳴り響き、独唱者の声が教会に満ち溢れる・・だったらいいなあと思っていたのですが、実際は、オルガニストが結婚式場から10分遅れて駆けつけるというハプニングで始まりました。(会場に集まられた方々には、ご迷惑をお掛けしました。申し訳ありませんでした。)いつもの私でしたら、その場を取り繕うと何かかにか、おしゃべりしていたと思うのですが、この日はどういう訳か、そういう一切のものが、排除された感じでした。言い訳のように聞こえますが、石田僚子さんにすべて委ねられている感じがしました。
2000年7月8日 (土) 晴天 この日も朝から暑い日でした。11時頃から準備の人達が三々五々集まり、飛田さんが作ってくれた(毎年ありがとうございます。)『石田僚子さん追悼10周年記念』の垂れ幕を前に掲げたり、講演者の本を並べたりしました。会員の方はもとより、太陽の子保育園のもと保母さん保父さんに大変助けられました。予定では、その時からオルガンの音が鳴り響き、独唱者の声が教会に満ち溢れる・・だったらいいなあと思っていたのですが、実際は、オルガニストが結婚式場から10分遅れて駆けつけるというハプニングで始まりました。(会場に集まられた方々には、ご迷惑をお掛けしました。申し訳ありませんでした。)いつもの私でしたら、その場を取り繕うと何かかにか、おしゃべりしていたと思うのですが、この日はどういう訳か、そういう一切のものが、排除された感じでした。言い訳のように聞こえますが、石田僚子さんにすべて委ねられている感じがしました。
森池日佐子さんの独唱「流るるはあつき涙」の声が、豊かに深く会堂中にまた心に広がり、始まりました。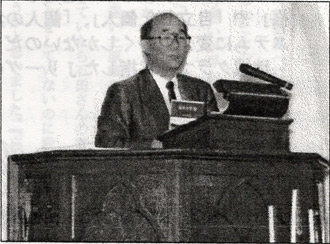 次に榎本栄治さん(敬和学園高校校長)によるお話。高校の中で出会ったひとり一人の学生たちとの体験談。とても走ることができないと思われていた学生が、完走することができ、それと前後する学生たちもお互いに励まされ喜びも倍増した話は、感動的でした。以前見たTV教育で、都立高校を中途退学した学生が、涙ながらに「子どもたちは、分からないのです。与えられたものがすべてなのです。」と訴えていましたが、たまたま出会った学校や、教師によって、大きく人生が左右されるとしたら、そのような立場にある大人たちは、余程そのことを心に留めておかなければならないでしょう。私たちは、大人というだけで、権力の側にいることをややもすると忘れがちになるのですが、ひとつ一つの言葉も(なかなかできるものでは、ありませんが)心をこめておくりたいものだと思いました。
次に榎本栄治さん(敬和学園高校校長)によるお話。高校の中で出会ったひとり一人の学生たちとの体験談。とても走ることができないと思われていた学生が、完走することができ、それと前後する学生たちもお互いに励まされ喜びも倍増した話は、感動的でした。以前見たTV教育で、都立高校を中途退学した学生が、涙ながらに「子どもたちは、分からないのです。与えられたものがすべてなのです。」と訴えていましたが、たまたま出会った学校や、教師によって、大きく人生が左右されるとしたら、そのような立場にある大人たちは、余程そのことを心に留めておかなければならないでしょう。私たちは、大人というだけで、権力の側にいることをややもすると忘れがちになるのですが、ひとつ一つの言葉も(なかなかできるものでは、ありませんが)心をこめておくりたいものだと思いました。
講演の最中、静かな会場の正面一番後ろに立った時に、(別紙・記念写真アルバムの右下)どこでもなく、ここ神戸バプテスト教会で開いた理由がわかった気がしました。去年の6月から会場をどこに決めるか探しました。障害のある人でも快く受け入れ、治療をされていた歯科医師の方が、建てられたシアターポシェット等も訪ねました。今は亡くなられた医師の奥様とお話したり、ビュッフェの絵がかけてあったりし、いい雰囲気だったのですが、三宮からかなり山手ということもあり決め兼ねました。どこかお寺か、教会。そこで会員でもあられる加藤牧師にお願いしました。 次に私たちの裁判の主任弁護士、金子武嗣さんのお話。今盛んに話題にされている少年問題を中心に、少年たちは、いくらでもこれから更生のチャンスがあるので、厳罰で処するのでなく、愛を持って時間をかけて対応することが大切と、今少年問題に取り組む弁護士たちを代表して語って下さいました。
次に私たちの裁判の主任弁護士、金子武嗣さんのお話。今盛んに話題にされている少年問題を中心に、少年たちは、いくらでもこれから更生のチャンスがあるので、厳罰で処するのでなく、愛を持って時間をかけて対応することが大切と、今少年問題に取り組む弁護士たちを代表して語って下さいました。
「見上げてごらん夜の星を」皆で歌い一部終了。缶ジュースで、喉を潤しながら歓談のひと時を持ちました。
二部は、齋藤次郎さん(子どもプラス編集長)によるお話。東海村で亡くなられた大内久さんのことを石田僚子さんにつなげて、ひとり一人の生命がかけがえのないことを、そして「いち少女」とは表現できないことを何時になく、しんみりとお話下さいました。 アンケートの中にもあったのですが、これだけ大物の方々ばかり、お一人ずつゆっくりお話を聴きたいのに、盛りだくさん過ぎたというご指摘、全くその通りだと思います。まったく、もったいない話です。中学や高校生の不登校の子どもさんを抱えた方、少年問題に興味を持っていらっしゃる方、学校教育そのものに疑問を持っている親や学生など等そのような多くの方々に集まって頂き、共有することが何よりも僚子さんの死を無駄にしないことだと考えたのですが、もうそれらすべてのことが削ぎとられ、『追悼』『魂の癒し』そのことだけに集中した集まりだったように思います。大変身勝手な解釈かもしれませんが、今思えば、三人の講師の方々おひとりお一人が、石田僚子さんのことを全国に講演に行かれたときに伝えるメッセンジャーとして選ばれたのではないかとそんな気がします。
アンケートの中にもあったのですが、これだけ大物の方々ばかり、お一人ずつゆっくりお話を聴きたいのに、盛りだくさん過ぎたというご指摘、全くその通りだと思います。まったく、もったいない話です。中学や高校生の不登校の子どもさんを抱えた方、少年問題に興味を持っていらっしゃる方、学校教育そのものに疑問を持っている親や学生など等そのような多くの方々に集まって頂き、共有することが何よりも僚子さんの死を無駄にしないことだと考えたのですが、もうそれらすべてのことが削ぎとられ、『追悼』『魂の癒し』そのことだけに集中した集まりだったように思います。大変身勝手な解釈かもしれませんが、今思えば、三人の講師の方々おひとりお一人が、石田僚子さんのことを全国に講演に行かれたときに伝えるメッセンジャーとして選ばれたのではないかとそんな気がします。
会場の中から、幾つかあった中で「自分の高3の息子が、学校をやめたいと言った時に、以前の自分だったらとうてい言えなかっただろうけど、そうか今までしんどかったな、よくやった。と言うことができた。石田さんによって成長させてもらった。石田さんありがとう」この話が印象的でした。
「サリマライズ」という亡くなった友を偲ぶ歌を皆で立って歌い、「石田僚子さん10周年記念会」の幕を閉じました。会のすべての行事を終えて、それぞれの所で、いろいろな方の『追悼』をされていることの意味が少しだけ分かった気がしました。例えば会員の飛田さんたちがされている「強制連行の人達の追悼」等です。ささやかでも、続けていくことが大切で、語り部とされていくことだと思いました。(所)