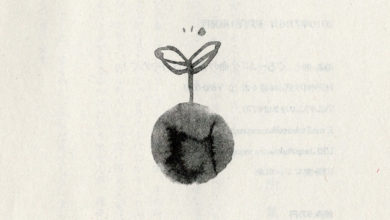石田僚子さん追悼20周年記念文集
家族のあり方とは

藤田 英美
石田僚子さんの死から20年がたち、当時15歳だった僚子さんは生きていると35歳ですね。この会とかかわった当時の私の年齢も25歳でした。僚子さんが生きていたら……と思うとやりきれません。私はこの会にかかわることで多くのことに気づかされ、また多くの人との出会いがありました。
20年を振り返れば、大人が子どもを監禁したり、子ども自身の自殺や、子どもが子どもを殺す事件が起こりました。現在では親がわが子を虐待して殺すという、悲惨なことが起こっています。子どもは親に守ってもらえなくなると最後です。今の社会、親が親に慣れない。それは親自身が愛されず自尊感情をもてなく育っていき、大人になっている親がいるということです。私たちが育った時代は言葉で表現しなくても、親は子どもを育てる中で貧しくとも、愛情一杯で家族にも祖父母もいて近所の人がいつも声をかけてくれていたように思います。私自身、子どもが小さい時、共働きで無我夢中で子育てをしてきました。大きくなるにつれ、節目にはわが子に、自分を重ねて、親がしてくれたことを思い出し感謝の気持ちで一杯になります。
今、世の中はお金がすべてとなり、物が溢れ返っています。子どもに、物とお金を与えることで愛情と思っている親がいると思います。しかし忘れてはならないのは、最も基本的な人間関係、それは「家族のふれあい」だと思います。私は「生命の管理はもうやめて!」の会をこれからも細〜く長〜く続けていければと思います。
(ふじた・えみ ぐるーぷ「生命の管理はもうやめて!」会計担当)