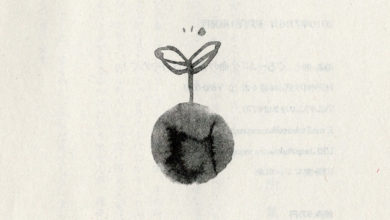石田僚子さん追悼20周年記念文集
石田僚子さんのこと
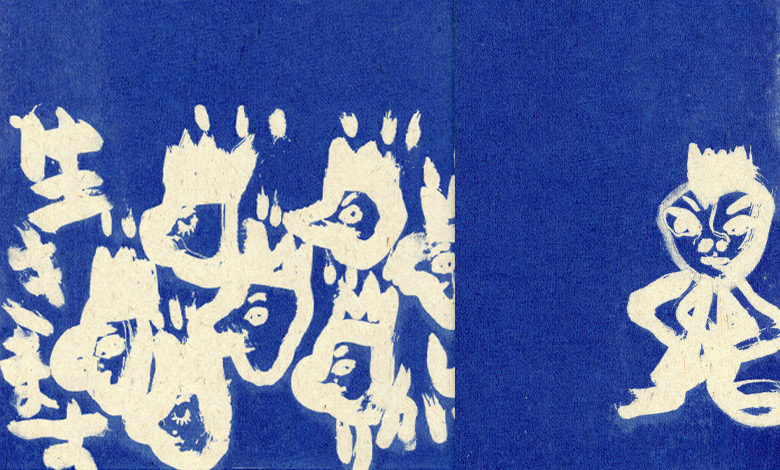
所 薫子
1990年7月6日、朝8時30分、兵庫県立神戸高塚高校の教師が閉めた校門の門扉に挟まれて石田僚子さんは圧死しました。その日すぐから後、多くの報道関係より報道され、しばらくはどこのチャンネルを回してもこの事件ばかりでした。
兵庫県では、「兵庫県立農業高校入試改ざん事件」「尼崎高校入学拒否事件」「風の子学園事件」など、教育に関する事件が次々に起こりました。
ちょうど同じ頃、神戸市立中学校では丸刈り強制が自由になった学校と「あと10年は無理」と言われる地域差が生じておりました。翌1991年には、全市的に強制が解かれ自由になりました。
教育を受ける権利をはなはだしく逸したこの事件は、世界の歴史を見てもまずありません。学校へ入ろうとして、教師によって閉められた門扉と門柱に挟まれて亡くなったのであれば、これは当然「殺人事件」です。けれど「事故」として扱われました。またその事件現場で水を流したりして証拠隠滅したにもかかわらず「校長の裁量範囲内」と裁判でも棄却されました。門扉は、耐用年数30年とされた県民の財産にもかかわらず、判決確定後に撤去、その日のうちに溶解させられ、それもこれも「校長の教育的配慮の裁量範囲内」で片付けられました。