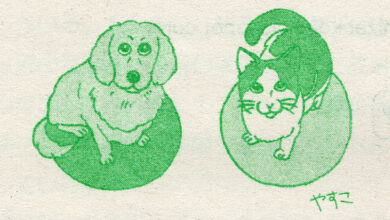いじめ問題の現状と特徴について
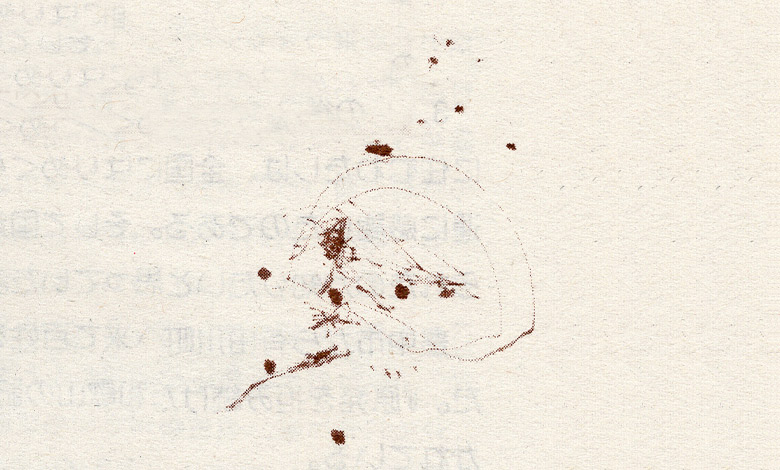
弁護士 峯本耕治
大津市の事件を契機に、まさに全国で「いじめ問題」の嵐が吹き荒れています。いじめ問題は、だいたい5年から10年くらいのサイクルで、自殺事件の裁判やマスコミ報道等を通じて社会問題化することを繰り返していて、そのたびに防止策等について議論されるのですが、その現状は、むしろ悪化してきているように感じます。
大津の事件については、現在行われている第三者調査委員会の検証結果等を踏まえて、あらためて振り返ることができればと思っていますが、今回は、いじめ問題の現状や現代的な特徴について、ごく簡単に紹介したいと思います。
一度紹介したことがあるかもしれませんが、数年前に大阪の寝屋川市で行われた調査で、子どもたちの「いじめた経験は、どの学校、どの学年においても50%以上、何度もいじめた経験が10%以上」「いじめられた経験についても45%以上、何度もいじめられた経験も10%以上」、更に、「何度もいじめられた生徒の、いじめた経験は60%以上、しかも、その約30%が、何度もいじめた経験がある」等の調査結果が出ています。
この調査結果から言えることは、加害、被害の双方を合わせると、ほとんど全ての子どもが、いじめを経験しているということ、「特定の子どもがいじめ加害者になり、特定の子どもがいじめ被害者になる」という単純な図式でなくなっているということです。ごく最近行われた調査でも、90%以上の子どもが、加害•被害は別にして、いじめを経験しているとの調査結果も出ており、子どもたちの世界では、もちろん程度は様々ですが、いじめは特別なことではなく、むしろ、普通に存在しているといっても良いと思います。
実際に、スクールソーシャルワーカー等として、学校のケースに関わっていると、小中高を問わず、子どもたちの人間関係•友人関係をめぐる未熟なトラブルが後を絶たず、ちょっとした言動によって傷つけ、傷つけられるというトラブルが日常的に発生していることが判ります。
特に、子どもたちにとっては(大人も同じですが)、クラスやグループの友人関係の中で、無視されたり、阻害されたりすることが一番辛いことなのですが、いじめの現代的な特徴の一つとして、同じクラスやグループの中で、些細な出来事をきっかけとして、いじめのターゲットがコロコロ変わっていくというような状況が起こりやすいため、身近な友人関係においても、安心できず、周囲の目を絶えず気にしないといけないという、不安の強い萎縮的な人間関係になりがちです。
もう一つの特徴としては、子どもたちのケータイ依存が進む中で、ほとんど全てのいじめケースに、ケータイ(メール)やスマホがからんでいるという点です。ケータイやスマホによるいじめの特徴は、以前のいじめでは、学校ではいじめられていても、家に帰れば解放されるという面があったのですが、メールは、いつでも、どこでもつながりますので、休みがなく、極端な言い方をすれば、24時間いじめられる、不安を感じ続けないといけない状況に置かれることになります。電源を切ったら切ったで、何かきているのではないかと不安になりますし、これまで来ていた友人からのメールが全くこなくなるというのも、また不安なことですので、メールからは、心理的に解放されることがないのです(実際に、特定の友人に対して、クラスの友人全員が、ある出来事をきっかけとして、ピタッとメールをしなくなるという形態のいじめも発生しています)。これは、本当にしんどいことです。
もう1つの特徴として、一見(いっけん)親しい、仲が良さそうに見える友人関係の中で、深刻ないじめが発生しているという点です。当たり前のことですが、それほど親しくない関係の中でいじめ的な出来事があったとしても、とりあえず、その関係から距離をとれば済むのですが、親しい友人関係においては、どうしても、その仲間からはずれたくないという心理が働きますから、その関係に固執してしまうことになります。大人も同じですが、色々な環境的要因が重なって寂しい時や孤立感を感じているような時は、特に身近な友人関係にこだわってしまいます。そんな中で、上下関係や支配的な関係が生まれてしまうと、離れにくい関係の中で、いじめが継続し、エスカレートしてしまうことになるのです。しかも、周りから見ると、いっけん仲が良さそうに映り、実際に対等にやり合っているような場面もあるので、表面的に見ていると、いじめに気付かず、また、多少気になることがあっても、積極的な関わりができないまま、深刻化•重大化してしまうということが起こりやすいのです。大津市の事件もそうですし、判例になっているような過去の重大ないじめ事件も、多くがこのパターンです。
もう1つ、私が一番気になっていることは、いじめることや、人間関係を力で支配したり、操作したりすることについて、また、それをされることについての、子どもたちの心理的な抵抗感や心理的な壁が低くなっているのではないかという点です。言い方を変えると、「いじめは良くないことだ」「人間関係を力や暴力で支配•コントロールすることは良くないことだ」等の素朴な正義感が、一般的に、失われつつある、低下しつつあるのではないかという点です。この素朴な正義感は、これまで、特に誰から教えられなくても、子どもたちが、その育ちの環境の中で自然に学び、身につけてきたものだと思われます。しかし、今の子どもたちを取り巻く環境を見ると、身近な世界において、そのような素朴な正義感をストレートに学ぶ場は減少する一方、テレビを中心とするメディアの世界においては、人の弱点や特徴的な部分をあげつらったり、いじったりすることが一般的に行われています。また、言葉による暴力を含めて、暴力的な情報が溢れています。私たちが意識しない中で、このような環境は、子どもたちの素朴な正義感を育ちにくくさせているのだと思います。
子どもたちが置かれている、このような状況は、学校や友人関係における愛情•安心•安全が脅かされた環境であり、児童虐待の増加をはじめとして家庭における愛着•安心•安全環境が悪化していることとと併せて、子どもたちの自尊感情•自己肯定感を低下させ、人への基本的信頼感を低下させ、子どもの成長•発達にたいへん深刻な影響を与えていると思います。
私は、これまで福祉や学校教育の現場に直接関わってきた中で、子どもたちの成長•発達にとって「愛情•安心•安全の環境」がどれほど大切であるかということを、いっそう強く感じるようになっています。
いじめ問題をはじめとする子どもたちの不安の強い萎縮的な人間関係は、子どもの成長発達を支える環境の重要な柱の一つである友人関係において、その「愛情•安心•安全環境」を脅かす、本当に深刻な問題です。
今回は、私が感じる、いじめ問題の現状や特徴を紹介するだけで終わってしまいましたが、次回以降、どのような取組が必要なのかを考えてみたいと思います。
 子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
清水克之(著), 佐藤拓代(著), 峯本耕治(著), 村井美紀(著), 山野良一(著), 松本伊智朗(編集) / 明石書店 / 2010年2月5日
<内容>
子ども虐待と貧困との関係を乳幼児期から青年期までの子どものライフステージに沿って明らかにする。執筆者のまなざしは、親の生活困難に向けられ、子どもと家族の社会的援助の必要性を説き、温かい。貴重なデータも多数掲載している。
 子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
小林美智子(著), 松本伊智朗(著) / 明石書店 / 2007年12月6日
<内容>
公権力の介入を求めるまで深刻化した子ども虐待。だが介入は虐待防止の切り札といえるのか。2005年の日本子ども虐待防止学会シンポジウムの記録を基に編まれた本書は、日英の経験をふまえ、虐待を防ぐために本当に必要な「ケアする社会」を構想する。
 スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
山野則子(編集), 峯本耕治(編集) / ミネルヴァ書房 / 2007年8月1日
<内容>
はじまったばかりのスクールソーシャルワーカーの活躍を描く。スクールカウンセラーや養護教諭とともに様々な問題に悩む親子に、社会的問題を含めて解決にあたる事例を紹介します。今までにない児童生徒へのアプローチに非常な関心がもたれています。
 子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
峯本耕治(編集) / 明石書店 / 2001年12月12日
<内容>
先進的なシステムをもつイギリスの児童虐待防止制度の詳細と、実際の運用状況を具体的に紹介する。ライン等も示し、問題点にも触れる。