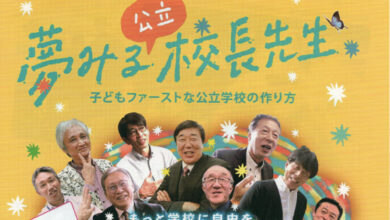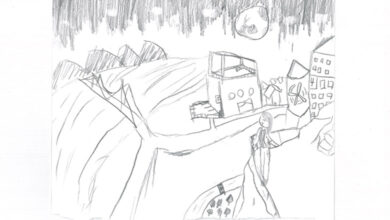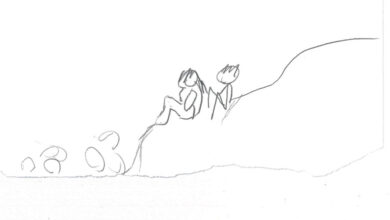家庭支援と学校支援
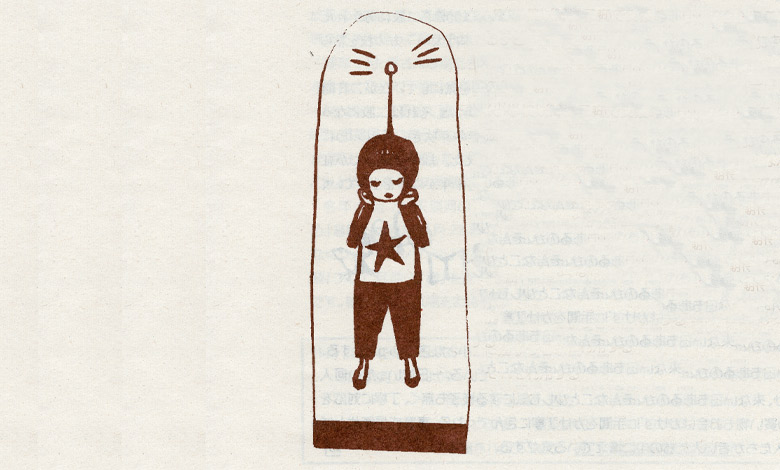
弁護士 峯本耕治
民主党政権の実現により、月額26,000円の子ども手当や高校教育の無償化という政策が現実的なものとなってきました。民主党マニフェストの目玉政策ですので、少なくとも一旦は実現される可能性が高いと思われます。
日本の子どもに対する公的支出は世界的に見て非常に少ないのが現状です。GDP比率で見ると、日本の家族への給付は、0.75%、スウェーデン3.54%、フランス3.02%、イギリス2.93%となっており、日本の数字は極端に低くなっています。この差は、現金給付(児童手当、児童扶養手当などお金で給付がされるもの)と現物給付(保育所、児童福祉サービス等)でも同様です。日本の子どもが減っていることを考慮しても、世界水準との差は余りにも歴然としています。今回の子ども手当については、「本当に子どものために使われることになるのか」、「所得制限を設けるべきではないか」等、色々な意見がありますが、この世界水準との差を少しは是正するものになることは間違いありません。また、教育への支出についても、日本の現状は、世界水準と比較して大変お寒いものです。日本の教育支出は、GDPの約3.5%であり、OECD(経済協力開発機構)平均の5%を大きく下回っています。OECD30カ国のうち、15カ国は大学教育が無償です。高校教育にいたっては、無償でない国は、OECD諸国の中では、日本、韓国、イタリア、ポルトガルの4カ国しかありません。今回の民主党が掲げている高校教育の実質的無償化は、この点においても、世界水準との差を意識したものであると言ってよいと思います。
これまでの日本の様々なシステムは、企業活動を保護することによって雇用が確保され、雇用が確保されることによって家庭が守られ、それによって、子どもの養育環境も守られるという考えを前提にしています。そして、学校教育も、当然のことですが、家庭に相当程度の養育能力があることを前提としていると言ってよいと思います。
しかし、今、その前提が大きく崩れてきています。終身雇用制度の崩壊と非正規雇用の増大、ひとり親家庭の増大等により貧困問題が本当に深刻になっています。以前にも紹介しましたが、OECD(経済協力開発機構)の基準によると、日本の子どもの貧困率は1980年代から2000年代にかけて約10%から約15%に上昇し、実に7人に1人という高い割合となっています。児童虐待も、全国の児童相談所への相談件数が過去20年にわたって増加し続け、1990年には1100件だったものが、2008年度には4万2000件を越えました。特にネグレクトが急増しています。また、経済的には恵まれた家庭においても、極端な過保護•過干渉や、子どもへのプレッシャーが極端に強いなど、子どもの成長発達にとってアンバランスな家庭環境が目立つようになっています。率直な印象として、日本の家族は全体として、ネグレクト•放任傾向の家族と過プレッシャー傾向の家族に両極化する傾向が見えてきています。背景にある親のしんどさも顕著になってきています。20年前の同様の調査結果と比較して、「子育てにおいて頼るところがない」、「誰にも相談できない」等の孤立感を抱えた親が約2倍、「子育てに自信がない」「イライラを感じる」と答えている親が約3倍に増加しているのです。過去20年~30年の間に日本の家庭の養育環境は悪化し、家庭の養育機能も大きく低下してきています。
そして、この家庭の養育機能の低下から生じる子どものしんどさや未熟さ(愛着関係の不足、発達の不足、負の学び等)が学校現場に直接表現されるようになっていて、それが、今の学校が抱える問題のかなりの部分を占めています。そのような背景を持つ子どもの問題行動や心配な症状等に対して、学校が適切•合理的な対応ができず、逆に、学校での愛着関係や発達環境も崩れてしまい、問題をより一層エスカレートさせてしまうという悪循環に陥ることが大変多くなっているのです。そして、もう一つ、子どもの発達を保障する重要な場として、子どもたちの友人関係がありますが、いじめ問題やケータイ文化に象徴されるように、この友人関係も非常に気遣いの多い萎縮的な人間関係になっており、子どもが安心して対人関係を学び、発達できる環境が失われてきています。
今の日本社会は、家庭環境の悪化•養育機能の低下をベースとして、友人関係環境、学校環境のいずれも厳しくなっており、全般的に見て、本当に子どもが発達しにくい環境になってきています。
そのような中で、学校や教員に対しては厳しい見方や批判の声が高まり、その限界を指摘する意見もありますが、私自身の思いとしては、子どもの成長発達を保障する上で、学校という公的システムと子どもに日々関わる教員の役割には本当に大きいものがあり、家庭の養育機能が低下している中で、これまで以上にその責任と役割が大きくなっていると感じています。
むしろ、「家庭に相当程度の養育機能があること」を前提とする、これまでの発想を転換して、家族の養育機能の低下を前提に、①家族の抱える問題から生じる子どもの発達への「不利」を防ぎ、学校現場において、より積極的に社会的自立に向けた発達保障を行う視点、②保育所が地域の子育て支援センターとして位置づけられているのと同様に、(小学校以降は子育て支援のための福祉システムがほとんど存在しない中で)、学校を窓口として、家庭への子育て支援を行う視点が求められる時代になってきているのではないかと感じています。もちろん、そのためには、学校教育関係費の実質的な無償化、少人数学級の実現、教員養成課程の研修制度の充実等を通じての教員のスキルアップ、教員以外の人的資源の投入や関係機関等によるサポート体制の整備など、相当のてこ入れが必要になります。
厳しい財政状況の中では、なかなか大きな期待は持てませんが、全ての子どもが小中学校に在籍し、約98%の子どもが高校に進学する状況を考えると、学校という公的システムを改善し、それを利用する方が、効率的だと思うのですが、どうでしょうか。
 子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
清水克之(著), 佐藤拓代(著), 峯本耕治(著), 村井美紀(著), 山野良一(著), 松本伊智朗(編集) / 明石書店 / 2010年2月5日
<内容>
子ども虐待と貧困との関係を乳幼児期から青年期までの子どものライフステージに沿って明らかにする。執筆者のまなざしは、親の生活困難に向けられ、子どもと家族の社会的援助の必要性を説き、温かい。貴重なデータも多数掲載している。
 子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
小林美智子(著), 松本伊智朗(著) / 明石書店 / 2007年12月6日
<内容>
公権力の介入を求めるまで深刻化した子ども虐待。だが介入は虐待防止の切り札といえるのか。2005年の日本子ども虐待防止学会シンポジウムの記録を基に編まれた本書は、日英の経験をふまえ、虐待を防ぐために本当に必要な「ケアする社会」を構想する。
 スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
山野則子(編集), 峯本耕治(編集) / ミネルヴァ書房 / 2007年8月1日
<内容>
はじまったばかりのスクールソーシャルワーカーの活躍を描く。スクールカウンセラーや養護教諭とともに様々な問題に悩む親子に、社会的問題を含めて解決にあたる事例を紹介します。今までにない児童生徒へのアプローチに非常な関心がもたれています。
 子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
峯本耕治(編集) / 明石書店 / 2001年12月12日
<内容>
先進的なシステムをもつイギリスの児童虐待防止制度の詳細と、実際の運用状況を具体的に紹介する。ライン等も示し、問題点にも触れる。