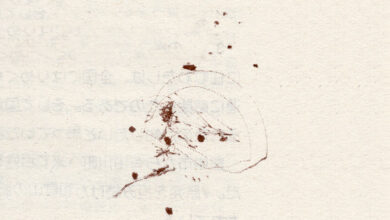いじめの現代的な特徴
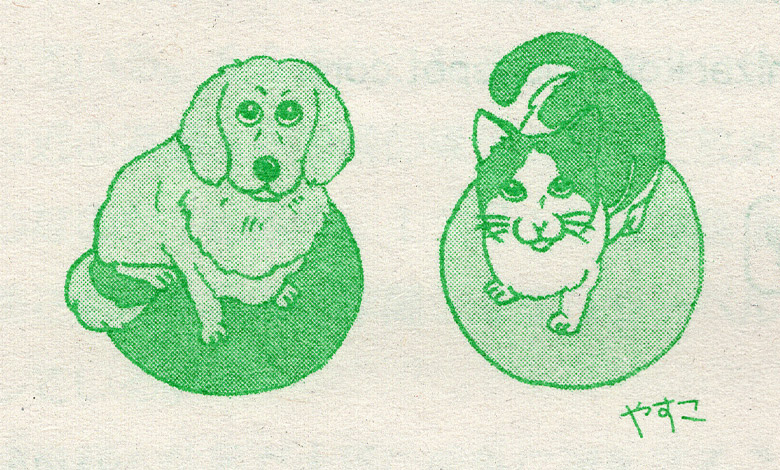
弁護士 峯本耕治
マスコミで比較的大きく取り上げられましたので御記憶がある方もいらっしゃると思いますが、昨年の後半、滋賀県で2件の深刻ないじめ事案が相次いで発生しました。うち一件は、子どもの自殺を契機に調査が行われ、いじめの事実が明らかになった事案でした。私自身、スクールソーシャルワーカーのスーパーバイザー等として、滋賀県にかかわっているので、たいへん辛い思いをした事案でした。
かなり前の高塚ニュースにも書きましたが、私たちの子ども時代と比較すると、今の子どもたちの友人関係は、全般的に気遣いの多い関係になっていて、その中で傷つけやすい•傷つきやすい、いじめ的な関係も生まれやすくなっています。たとえば、同じグループ内でも、誰かをターゲットにして、ちょっと無視したり、攻撃したりする、そのターゲットが2週間から1カ月ぐらいで変わっていくというようなことも珍しくありません。その結果、子どもたちは、自分がターゲットにされないように、みんなが気を遣いすぎて人間関係が萎縮したり、以前と比べると、自信を持てない、信頼•安心できない関係が生まれやすくなっているのです。
そのような関係の中で発生するいじめの現代的な特徴として、外からの見えにくさが増しているように思います。冒頭で紹介した2件の事案もそうだったのですが、いじめが、子どもたちが人間関係を求めあう中で、一見すると、仲の良い友人関係やグループの中で起こっていること、携帯メールを使ったいじめが一般的になっていること、子どもが以前より、先生や親にいじめを訴えにくくなっていること等が、その原因と思われます。
以前なら、学校でいじめられても家に帰れば「しんどい人間関係」から解放されました。しかし、携帯電話、特にメールが一般的になってからは、子どもたちは逃げ場を失い、24時間安心できなくなっています。メールが来たら「すぐに返事しなければ、無視される」等のプレッシャー下におかれます。また、たとえば、授業中の態度を理由に、一人の子どもが、一斉送信機能を使ってクラス全員に「あいつの態度、うざい」等のメールを送り、その直後から無視が始まり、その子のところにそれまで頻繁にやりとりされていたメールが全く来なくなるというようなケースも発生しています。
子どもが親や教師にいじめられていることを訴えにくくなっているという点についても、もともと、子どもは、それが自尊心に関わる問題であるため、いじめられていることを認めたくないという思いを持っていますし、「言っても解決が難しい。」「もっと悪くなるかもしれない」「心配を掛けたくない」等の不安感も強いですので、なかなか自分からは助けを求めてくれません。特に、最近の傾向として、前述しましたように、時間と共にいじめのターゲットが替わっていきますので、相談することで親や教師が何らかの対応をしてしまうと、逆にターゲットが自分のところで固定化されてしまい、もっといじめがエスカレートしてしまう可能性があるため、子どもたちは、より一層助けを求めにくくなっているのです。
このようにいじめが一見して見えにくくなっている中で、学校•教師がいじめを早期に発見して、深刻ないじめに発展することを防ぐためには、何よりも、どのクラスにもいじめ又はいじめ的な人間関係が存在すること(その可能性が高いこと)を、しっかりと意識しておく必要があります。様々な調査から、子どもたちが、非常に高い割合で、いじめ加害又は被害、その双方を経験していることが明らかになっており、確率的には、程度の軽重はあっても、どのクラスにもいじめ的な人間関係が存在すると言って良いと思われます。
その上で、普段から、クラスの子どもたちのキャラクターや人間関係、グループ内の関係性を把握し、いじめが起こりやすそうな関係やグループについて、ある程度、見立てをして、予想しておくことが非常に大切です。日々子どもたちに接している、担任教師にとっては、決して難しいことではありません。
このような見立てができていれば、ちょっと気になるいじめ的な言動があったときに、あっさりと注意することが可能ですし、被害シグナルへの気づきも早くなります。
そして、子どもにしんどいシグナルが認められたときには、きちんと、それを止めることができるところまで、そのことを確認できる状況まで、しっかりと踏み込んでかかわることが大切です。いじめによって、子どもがしんどくなれば、必ず何らかのシグナルや症状を示します。元気がなくなる。シグナルとしては、欠席が増える、成績が急に低下する、態度の変化など、様々なものがありますが、いじめの可能性を意識していれば、その発見は難しくありません。
もちろん、シグナルに気づき、教師が積極的にかかわろうとしても、子どもが「大丈夫だから」等と言って教師の介入を避けようとすることも少なくありません。自殺につながっているような深刻ないじめ事案においても、多くの事案で、そのような過程が存在しています。しかし、そのような子どもの反応は、不安の反映にほかなりませんので、子どもに「話しても大丈夫であること」「早い間にちゃんと介入することによって必ず楽になること」「絶対に悪くなることはないこと」「先生が最後までしっかりとかかわること」等の安心•安全を保証するメッセージをしっかりと伝えることによって、積極的に関わっていくことが重要です。
その際にもう一つ大切なことは、いじめへの対応は、担任教師が一人でするのではなく、学年等の教師集団によるチーム対応が大切であるということです。そのことが、被害を受けている子どもへの安心感につながり、また、いじめが大変大きな人権侵害であることを子どもたちに伝えるメッセージにもなります。いじめ事件の裁判例においても、担任教師等により仲直りさせる等の通り一遍の指導では、いじめの指導として不十分であり、チーム対応が必要であることが述べられています。
子どもの成長発達を支えるものは、家庭、学校における愛情を感じることができ、安心できる環境です。家庭における虐待と並んで、いじめは、この愛情•安心環境を脅かす最たるもので、子どもの自尊感情を低下させ、人への信頼感を失わせる、子どもの成長発達に深刻な影響を与えてしまいます。
いじめの防止は、子どもたちの人間関係が変化し、ケータイ文化が定着する中で、学校にとって、最大の日常的課題の一つになっていると言っても良いと思います。
 子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
子ども虐待と貧困―「忘れられた子ども」のいない社会をめざして
清水克之(著), 佐藤拓代(著), 峯本耕治(著), 村井美紀(著), 山野良一(著), 松本伊智朗(編集) / 明石書店 / 2010年2月5日
<内容>
子ども虐待と貧困との関係を乳幼児期から青年期までの子どものライフステージに沿って明らかにする。執筆者のまなざしは、親の生活困難に向けられ、子どもと家族の社会的援助の必要性を説き、温かい。貴重なデータも多数掲載している。
 子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
子ども虐待 介入と支援のはざまで: 「ケアする社会」の構築に向けて
小林美智子(著), 松本伊智朗(著) / 明石書店 / 2007年12月6日
<内容>
公権力の介入を求めるまで深刻化した子ども虐待。だが介入は虐待防止の切り札といえるのか。2005年の日本子ども虐待防止学会シンポジウムの記録を基に編まれた本書は、日英の経験をふまえ、虐待を防ぐために本当に必要な「ケアする社会」を構想する。
 スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
スクールソーシャルワークの可能性: 学校と福祉の協働•大阪からの発信
山野則子(編集), 峯本耕治(編集) / ミネルヴァ書房 / 2007年8月1日
<内容>
はじまったばかりのスクールソーシャルワーカーの活躍を描く。スクールカウンセラーや養護教諭とともに様々な問題に悩む親子に、社会的問題を含めて解決にあたる事例を紹介します。今までにない児童生徒へのアプローチに非常な関心がもたれています。
 子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
子どもを虐待から守る制度と介入手法―イギリス児童虐待防止制度から見た日本の課題
峯本耕治(編集) / 明石書店 / 2001年12月12日
<内容>
先進的なシステムをもつイギリスの児童虐待防止制度の詳細と、実際の運用状況を具体的に紹介する。ライン等も示し、問題点にも触れる。