少女・15歳から17歳・少年まで
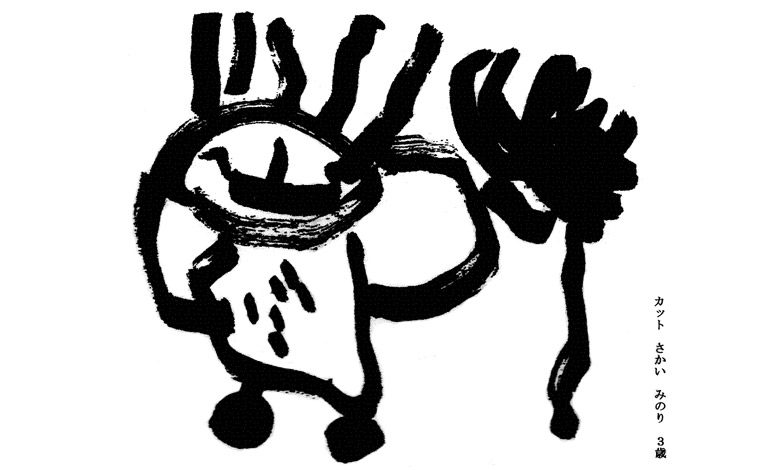
今日わたしたちは、愛知県豊川市の主婦殺人事件、佐賀のバスジャック事件に見られる17歳・少年の不条理な殺害衝動やそのような行動に向かわせる「心の闇」が如何なるものであったのか、日本の子どもたちがどのような世界に生きているのかという困難な問題に直面している。事件が衝撃的で、わたしたちの理解を超えたものであればあるほど、例外的・特異なものと考え、自分たちが傷つかない範囲で原因を特定し、個人の性格・精神障害・家庭の子育ての問題だとするやり方は、「校門圧死事件」は「一県の一高校の一教諭による単なる事故」として片づけようとした文部省の姿勢と通底している。少年法を改正(改悪)することによって凶悪事件が減少すると考えることは、校門を替えれば明るい学校生活が戻ってくると考える方と同根である。政治であれ経済であれ教育であれ、わたしたちの社会を形作っている制度を産み出すのは、他の誰でもないわたしたち自身の日々の営みである。「校門圧死事件」も「17歳の凶悪事件」もわたしたちが作りだしている社会空間のゆがみがもたらしたものであり、わたしたち自身に責任の一端があるとの認識を持たない限り何も変わらない。
「教育の危機」「学校の危機」「子どもの危機」はわたしたちの「社会の危機」であり、わたしたちに降りかかる「わたしたちの危機」である。「教育とは生き方をつたえるこころみである」とは鶴見俊輔のことばである。教育を学校に譲り渡してしまった時から、わたしたちは子どもに生き方をつたえることができなくなってしまったのではないか。いつ頃からわたしたちは今の学校制度に慣れ親しんでしまったのか、監獄のような校舎、黒板と教卓と40近く整然と並んだ机と椅子から構成される無機的な教室、制服を着用し教師の号令に従い「集合」「整列」の一斉行動を行う異常さ、受験競争を勝ち抜くために無味乾燥な知識を詰め込むことの空しさ、偏差値という数字によって輪切りにされ自らの相対的位置づけに一喜一憂する愚かさ、教師による理不尽な体罰や言葉による暴力への忍従、細かな校則と罰則による監視の視線の充満、このような空間で子どもたちが生き生きと個性豊かに育つことができないのは自明の理である。それにも関わらずわたしたちは子どもたちを学校に送り込み続けるのである。何故なら学校は社会を再生産する事業体であり、社会に参加するための正当化された唯一の通過機関であるとの信念が広く人々に受け入れられているからである。受験地獄の非人間的な残酷さにもかかわらず資本としての学歴を獲得しさえすれば競争社会に勝ち抜き、「より良い学校→より良い会社→より良い人生」という個人主義的幸福の達成が誰にでも可能であるとの幻想に囚われ、競争社会の再生産が繰り返される。問わねばならないのは、わたしたちの生き方である。偏差値による輪切りは学校を序列化し、上位校から底辺校までの格差を生みだし、個人の能力をも序列化する。大学によってランクづけ、会社によって差別化をはかり、上位の者にはゆがんだ優越感を、下位の者には根拠なき劣等感を持ち続けるような意識から解放されねばならない。わたしたちの生き方はこのような貧しいものでは無いはずである。




