高塚高校事件を回顧する
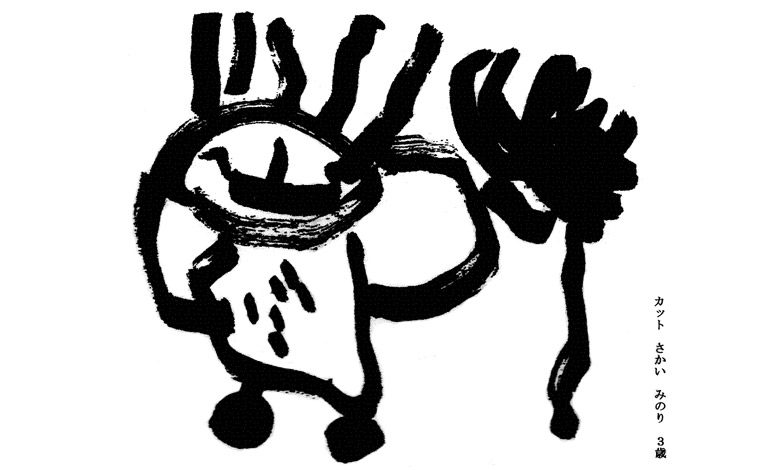
1. おかしかった校則
私の勤務した高校の生徒には「生徒手帳」が渡してありました。身分証明にもなるもので、常に携帯が義務づけられ、生徒の服装や起居動作について細かく定めた「生徒心得」などが入っていました。その内容は 各々、中、高校で多様でしたが してはいけないという禁止条項づくめでした。
学校生活内規には 靴下は白の無地、ワンポイント・ライン入りは禁止、天然パーマの生徒には証明書を発行。男・女とも制服を着用し マフラー・手袋は校門に入る前にとること 等々 この他にも帰宅時間の規制 映画館の入管制限、飲食店の出入り禁止等々 禁止事項が列記してありました。
これら校則の規定は、校内のみならず校外生活にまで及ぶもので厳しい アメリカのニューヨーク市でも ドイツのシュトウットガル市でもこんな規定はありません。
そもそも学校外のことは 親が責任と権限を持つのが当然でしょう。
しかもこの頭髪から靴まで文字通り頭の先から足の先まで、一挙手一投足に細かい気配りの禁止項目を並べた生徒手帳を、生徒はお守りとして所持していたわけです。
ここで問題の高塚高校の校則をみますと、(量が多いので 割愛します。)
◯ 上履きのスリッパで地面に降りないこと
◯ 男女交際は保護者の証人と指導のもとに高校生としての生活を逸脱しないものであること
◯ 上衣は授業中担当教諭の許可を得て脱ぐこと
◯ 靴下は男子は白無地ソックス、女子のストッキングは肌色のみ
◯ セーターの色は白、紺、グレーの無地・型はVネックの平織り
更に、右のような細目とは別に基本的心がまえが記載されていました。遅刻防止は基本的心がまえの第2番目にランクされており第1番目は服装の端正でした。
このような校則により生徒をがんじがらめにしていた管理主義こそ 校門圧死事件の真の原因というべきでしょう。管理主義は形式的、画一的な指導で生徒の判断力を育てないだけでなく、教師の判断力も奪ってしまったのです。
校門圧死事件を教訓に同校では生徒の自主性を育てる目的で生徒心得の改正が行われたとのことですが、文部省→教育委員会→校長の絶対的な管理体制が無くならない限り 教育現場の教師はロボット的存在なのです。
高塚高校校門撤去の日、それを阻止する人々を遮ったのは外でもない校長に召集されたPTAの役員でした。私はこのPTAの役員に肘で突かれた時 やむなく通用門から出ましたが つくづく思い知らされたことは 権力に肩入れする父母の組織が、教師の重圧にもなっているということでした。
忘れもしませんが頭上にはヘリコプターが低空を旋回し取材をしておりました。この時役員らしき母親は「邪魔やナー ウチの子が補習授業受けトンヤ」でした。




