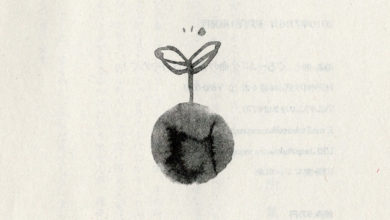石田僚子さん追悼20周年記念文集
ご遺族に代わって
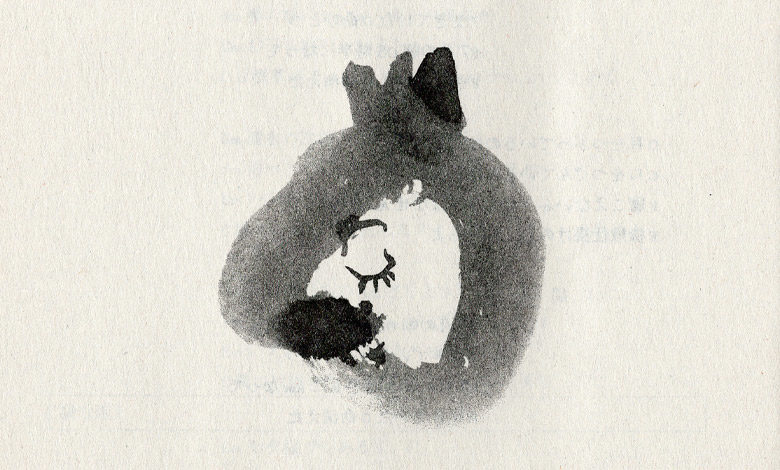
平栗勲
僚子さんのご遺族としては長いようで短い、あっという間の20年でした。
あの事件がなければ、今頃僚子さんは、得意な英語の先生になり、普通の女性として家庭を持ち、両親にとっても孫に囲まれた幸せな日々を過ごしていたことでしょう。
あの日以来家族の生活は一転し、いまだ僚子さんの死を受け入れられないトラウマが続いています。
JR福知山線脱線事故同様に残された家族のトラウマは永遠になくなることはないでしょう。
それどころか、自分の将来を託して真面目に勉強していた学舎で理不尽な事故により死亡した僚子さんの悔しさはもって行き場のないやりきれないものです。それが、当時の管理教育の犠牲であると主張してもせんないことです。
だからといって僚子さんは決して家族の元へ戻ってくることはないのですから。
(ひらくり・いさお 遺族代理弁護士)
「高塚門扉No.38 (2002年夏)」に掲載されました平栗勲弁護士の「校門圧死事件11周年に思うこと」も是非お読み下さい。