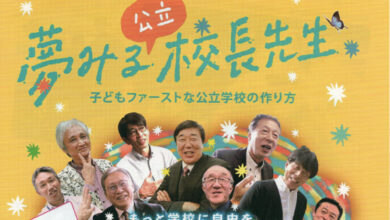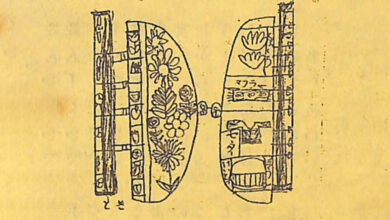最近の学校崩壊事情について
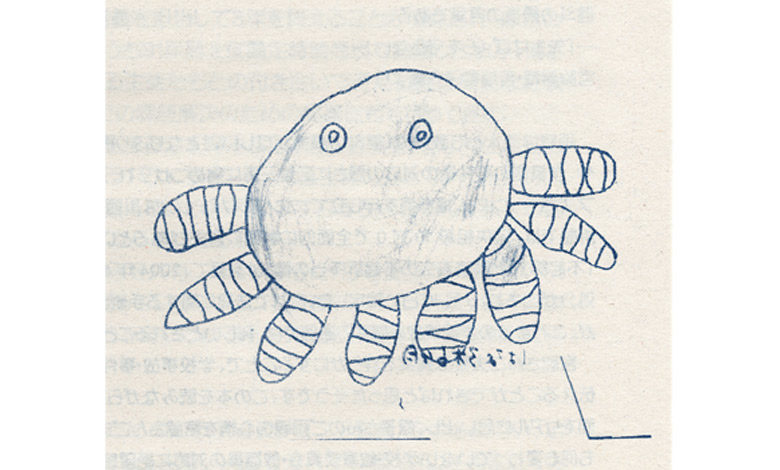
弁護士 峯本 耕治
理研の小保方さんのSTAP細胞問題はどういう結末を迎えるのでしょうか。論文に様々な問題があることが明らかになり、発表された2本の論文が全て撤回されることになるようですが、私たち市民の関心は、論文不正の問題はさておき、本当にSTAP細胞が発見されていたのかどうかという点に尽きるように思います。常識的な感覚としては、第三者が検証実験をすればすぐに判ることですから、さすがに「発見されていないものを、発見された」として、あれほど大々的に発表することは考えられないように思いますが(少なくとも、今も、そう思っていて、STAP細胞の存在が確認されることを期待しているのですが)、最近、「論文捏造(村松秀著、中公新書ラクレ)」という本を読んで、不安な気持ちになりました。同書では、科学界において重大な論文捏造・不正事件が相次いで発生していることが報告されているのですが、その中でも、2002年に判明した、科学の殿堂といわれているアメリカのベル研究所に所属していた、ノーベル賞に最も近いと言われていた若い研究者による史上空前の論文捏造事件が中心的に取り上げられています。世界的に有名な研究機関に所属し、権威ある学者が論文作成に密接に関与・協力している点、ネイチャーやサイエンスなどの権威ある雑誌に掲載されている点、ノーベル賞の有力候補となるような重大な発見である点、多数の検証実験が世界中で繰り返された点等において、今回のSTAP細胞問題と様々な類似性が認められる事件です。客観性が何よりも担保されているはずの科学界においても「常識では考えられない極端なことが起こりうる」というのが率直な感想です。現在の科学界、研究者らが置かれている状況が、それほどストレスの高い歪んだ環境にあることを示しているのだと思いますが、今回のSTAP細胞を巡る問題の行く末について、この本を読んで心配になってきました。また、機会があれば読んでみてください。
さて、今回、子どもに関わる問題について、どんなテーマで書こうかなと悩んでいたのですが、学級崩壊について簡単に書きたいと思います。学級崩壊は、最近は、いじめ問題等の陰に隠れて取り上げられることが少なくなっていたのですが、実は、小学校高学年の学級崩壊が増加しています。小学校高学年の学級崩壊は、最後は子どもたちによる担任教師に対する集団的ないじめのような状態に陥ってしまい、担任教師が精神的につぶれてしまい担任交替という事態に至ることも少なくありません。中には、1年間に担任が2回も交替したというような酷いケースもあります。どうして、そんな事態にまでなってしまうのでしょうか。もちろん色々なケースがあるのですが、小学校高学年の学級崩壊には一定の共通した特徴が認められます。たとえば、子どもたちの特徴としては、いわゆる親子の愛着障害(被虐待環境)等を背景に持つ、見てみて行動としての落ち着きのない行動や、教師への試し行動、学力面のしんどさ等、行動面・発達面の課題を抱えた数人の子どもの存在と、そのような子どもに影響を受けやすい数人の子どもの存在があります。教師の特徴としては、そのような特徴的な課題を抱えた子どもたちに対し、愛情要求の側面を持つ、見てみて行動、試し行動等に対する理解がないままに、愛情を感じにくい余裕のない指導を繰り返してしまう、クラスの規律・秩序等を重視しすぎて厳しすぎる指導や感情的な対応を繰り返してしまう、一部の子どもたちに自分は差別されている、愛されていないと感じさせる対応・指導となり、よい子・悪い子の分断化を生んでしまう、子どもの自尊感情を傷つける指導・言動を繰り返してしまうなどの特徴が認められます。このような子どもたちの特徴と教師の指導の特徴が重なり合う中で、一部の子どもたちは、自尊感情や教師に対する信頼感を一層低下させ、それが、より激しい反発を生み、クラス全体が混乱していきます。当初は落ち着いていた、それ以外の子どもたちも、問題をコントロールできない教師の対応に、次第に信頼感を失い、冷ややかな対応をするようになります。そうなると、クラスは完全に求心力を失い、最終段階では中心となっている子どもたちが、教師を攻撃し、困らせることに居場所を見いだすようになり、教師は完全に自信を失って、いじめ的な学級崩壊状況が生まれてしまうのです。このような学級崩壊の原因・特徴からみたとき、学級崩壊の本質的な原因は、教師が様々な課題を抱えた子どもたちの試し行動、見てみて行動等に振り回される中で、結果として、「子どもが教師の愛情を感じなくなること」、「大切にされているとの実感を持てなくなること」にあると言っても良いと思います。となると、学級崩壊を防ぐためには、子どもたちの抱える課題(特に、愛着障害を抱えた特別な支援を必要とする子どもの課題)についてのアセスメントに基づき、「愛情保障・愛情確認」、「自己肯定感を下げさせず、高める取り組み」、「学力面での落ちこぼれを防ぐ」等がキーワードになり、そのために、何をしたらよいかの視点が必要となります。愛情保障・愛情確認というと大変情緒的な感じがしますが、やはり、教育によって子どもの成長発達を保障するには、教師がスキルとして、子どもたちに愛情を伝えること(すくなくとも、それを感じさせること)が不可欠なのです。私たちの子ども時代と比較すると、学校の権威が低下し、子どもの抱える様々な課題が学校現場にストレートに表現されるリスクが高まり、愛着障害を抱えた子どもが増加している中で、いかに効果的に愛情を伝え、その上で、発達課題を見極めて指導ができるかが、本当に大きなポイントとなってきています。