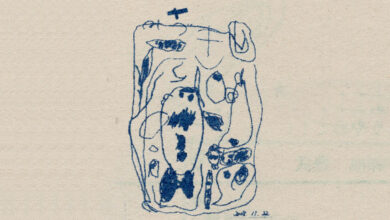2つの事件から見える子どもと家庭・親子
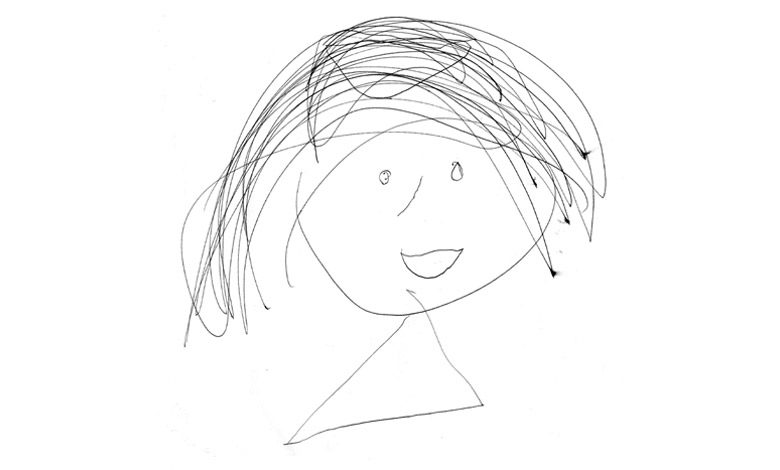
弁護士 峯本 耕治
今年も重大な児童虐待事件が後を絶ちませんでした。つい最近も、茨木市で悲惨な事件が起こってしまいました。新聞等で見られたと思いますが、難病を抱えた3才の女児が平均体重の半分にまで痩せ細って死亡し、司法解剖によって、腸内から、ロウソクのロウ、アルミ箔やタマネギの皮が発見されたという事案です。19才の母親と義父である22才の父親が殺人容疑で逮捕されました。辛すぎる事件ですが、なぜこのような状態になるまでシグナルを発見できず、福祉的支援の手が入らなかったのか、乳幼児検診時にシグナルは見えなかったのか、なぜ若年出産・ステップファミリーで難病を抱えた乳児について継続的な支援やモニタリングが行われていなかったのか、貧困問題が背景にあったのではないか、なぜ市の要保護児童対策地域協議会(虐待防止ネットワーク)に挙がっていなかったのか、なぜ異常・異変を感じた近所の人からも全く通告が行われなかったのか等、様々な疑問が湧いてきます。今後、警察の捜査に加え、福祉的な検証が行われていくことになると思いますが、私自身も児童虐待防止の現場に直接関わっている者として、茨木市という身近な、比較的進んだ虐待防止・子育て支援システムを持っている自治体で、このようなケースが発生したことに驚きを感じると共に、ショックを受けています。
児童虐待によって死亡した子どもは、明確に虐待が認定されているものだけでも、2013年3月までの過去10年間で546人に上っています。全国の児童相談所への虐待通告・相談件数は2013年度は約7万4000件に達し、増加の一途を辿っています。
家庭・親子関係が子どもにとって「愛情・安心・安全の基地」ではなくなってきているのではないかと大きな不安を感じる数字です。
今年を振り返ったとき、もう一つのショッキングな事件として、7月に発生した長崎県佐世保市の高校一年生の女子生徒による同級生殺害事件があります。父親が弁護士で地元の有力者、母親が市の教育委員、中高一貫校で成績優秀な娘など、外形的には、絵に描いたような幸福な親子・家庭に起こった事件ですが、既に報道されている情報によると、子どもは小学校卒業直前に友人の給食に洗剤・漂白剤を入れる事件を起こしています。2013年10月に母親が死亡し、父の再婚後には、猫を殺して解体したり、父親に対して金属バットによる激しい傷害事件を起こすなどの、病理的な症状といって良いほどの様々なシグナルを示しています。そのような中で、子ども1人の生活が始まり、高校入学後は不登校の状態が続いていたという状況の中で発生した親しい友人に対する殺害事件です。福祉的な視点からみると、自傷や他害の両面から重大ケースにつながるリスク要因が極めて高く認められたケースで、どのような事情があっても、子ども1人の生活には無理があったものと私は思います。小学校時代の事件(=子どものシグナル)の原因・意味がどう理解され、どう対応されたのか、中学時代はどうだったのか、母の死亡・父親の再婚という重大な家族環境の変化後の病理的な症状・シグナルに対して、どのような見立てが行われ、どのような支援・対応が行われたのか、それぞれの時点において、なぜ、積極的な福祉的・医療的・司法的介入ができなかったのか、学校は不登校の原因・背景をどう理解し、どう対応・支援していたのかなど、同様に、様々な疑問や課題が見えてきます。
前述した茨木市の虐待ケースとは外形は全く異なっていますが、ここでも、家庭・親子が「愛情・安心・安全の基地」ではなく、そして、学校教育もまた、明らかな課題を抱えた子どもの居場所となりえなかった現実が見えてきます。この事件についても、今後、教育・福祉の両面から検証が行われることになると思います。