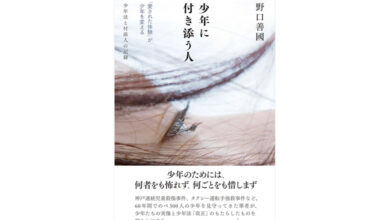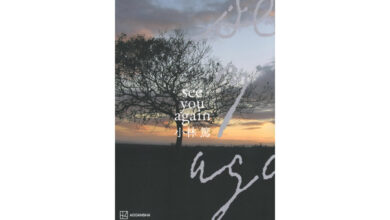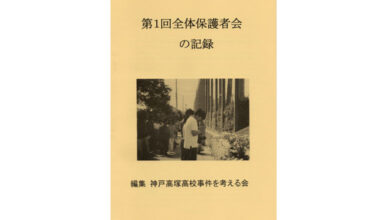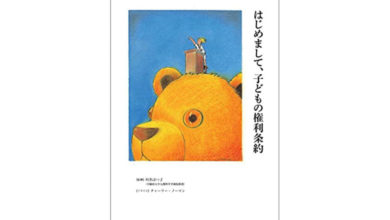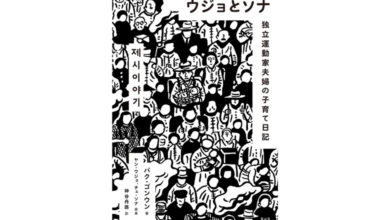ホンの紹介
ホンの紹介『貧困世代 社会の監獄に閉じ込められた若者たち』
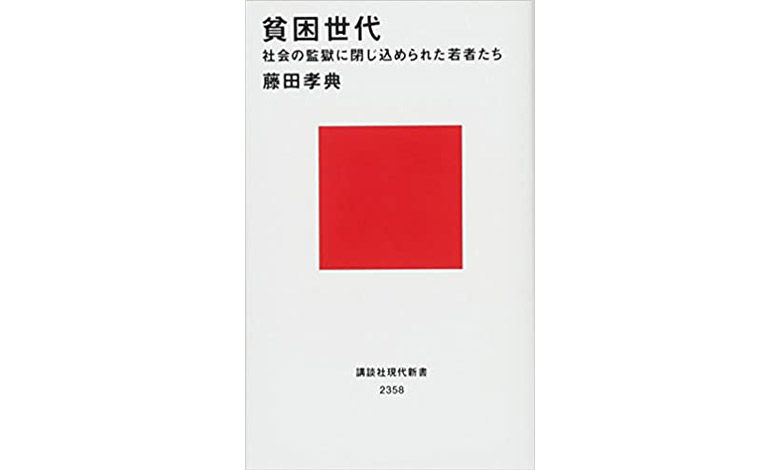
藤田 孝典 (著) 講談社現代新書 2016年刊 821円
<内容紹介>
「貧困世代(プア・ジェネレーション)」は下流老人よりも悲惨だ!
「現在の若者たちはもはや、ロスト・ジェネレーションのような一時的な就職難や一過性の困難に置かれているのではない。雇用環境の激変を一因とする、一生涯の貧困が宿命づけられている。
若者たちは何らかの政策や支援環境の再編がない限り、ワーキングプアから抜け出せないことも増えてきている。
ここでわたしは、現代の若者たちは一過性の困難に直面しているばかりではなく、その後も続く生活の様々な困難さや貧困を抱え続けてしまっている世代であると指摘したい。彼らは自力ではもはや避けようがない、日本社会から強いられた貧困に直面している。日本史上でも類を見ない、特異な世代である。
だからこそわたしは、彼らの世代を、『貧困世代(プア・ジェネレーション)』と総称することにした」
(「はじめに」より)