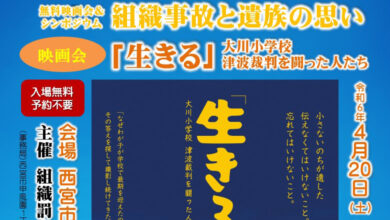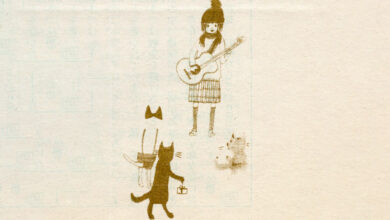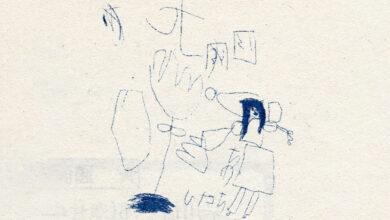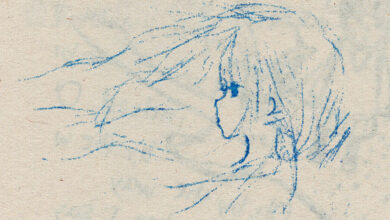復興で消される記憶の痕跡
藤田 敏則
2015年の夏、東京芸大の大学院生二人(共に女性)による “波の下、土の上” という記録映像で構成された作品を鑑賞する機会がありました。彼女達は東日本大震災の翌年から3年以上に渉り岩手県陸前高田市に滞在していたそうです。作品は月日の中で変貌してゆく陸前高田の町と、そこに暮らす住民3人の日常を撮り続ける中でそれぞれの心情を浮き上がらせた内容になっています。
作者の二人が過ごした震災後2年目から3年目にかけては陸前高田に限らず、津波で壊滅した東北沿岸のどこの町も復興に向かって突き進みはじめた時期に重なります。被災した町は先ず瓦礫が搬出されたあと、残りの建物が解体撤去されます。その後は新たな町の再建に向け、高台の宅地造成と盛土による嵩上げが現在(2015年9月)も進められています。陸前高田でのこうした工事は盛土の高さ (10m) 、整地面積共に大規模であり、大掛りなベルトコンベアーを構築して工期短縮が図られています。この時期の住民感情は個々様々で、ひとくくりには論じられません。しかし先の映像作品に取り上げられた年齢や被災状況の異なる3名――“波の下、土の上”は3部作に構成されており、各部毎に住民個々を追跡――の言葉や表情からは、どこか共通する哀感が伝わってきます。この町のこの場所で営まれた生活の全てを亡くした住民が“あの日”から2年以上の間、目にしてきた景色には3.11以前の町の面影を彷佛させる痕跡が、そこかしこに点在していたのです。言及されぬものの画面から伝わるのは、対象者がその“場”に立つことで甦る記憶と重ねた時間が盛土の下に埋もれてしまう事への諦めと哀切でした。作者がこうした人達の喪失感を当初から狙った訳ではないにしろ、あまり顧みることのない時期(3.11から2年目〜3年目)の被災住民の心情を窺い知る希少な記録といえるでしょう。
2009年4月に長女(朋)が陸前高田に住まう夫君に嫁ぎましたが、私はそれ以降未曽有の震災までこの町について何一つ知らずにいました。東北への足が確保できた2週間後の2011年3月25日、娘の消息を求めて漸くこの町を訪れた時に見た光景が私の中の陸前高田の記憶として今も焼き付いたままです。小高い所に立たねば周囲が見渡せぬほどに堆積した瓦礫と、これまでに嗅いだ事のない悪臭を漂わせる足下のぬかるみ、それらがからまったまま点在するコンクリートの建物・・・・・。一面に広がった廃墟の中央には娘があの日出勤した市役所と津波の直前に逃げ込んだ直後、想像もつかぬ恐怖に襲われたであろう市民会館が無惨な姿で向かい合っていました。娘がこの町で暮らしたのは結婚後685日間(2年足らず)でした。職業人(ソーシャルワーカー)として希望を託そうとした町、その証となる場は今、盛土の下に眠っています。
2年目(2013年)の3月11日、取り払われた市民会館の跡に立った私は“偲ぶ場”が失われた事にたとえようのない淋しさを覚えました。住んだ事もなく、“あの日”以前の町を知らぬ私の場合と地元住民の喪失感を重ねる事はできません。只この事は町の再建がスピードや合理性のみならず、人の記憶にも配慮する姿勢があって然るべきでは?・・・・・そんな想いを抱かせる作品でした。
鉄道や病院を含め官公施設の集中していた中心市街地が消滅した陸前高田市の復興はゼロから未来図を描かなければなりません。それは真新しいキャンパスに自由な色や形を与える作業のように見えます。しかし元々基幹産業と呼べるものを持たぬこの町の再生は、経済基盤を整える処から進めなければ人口流出が止まらないという難しい状況を抱えています。唯一観光の目玉、高田松原――7万本を擁する日本三大松原――を失った今、再生への旗印となる『住民が誇れる町の将来像』は見いだせぬままです。槌音を響かせる復興景気も数年後には一段落します。この町はこれから先も当分外からの支援なくしては立ちゆかない状況が続くでしょう。但し、町の将来像は与えられるのではなく住民自身が描かなければなりません。住民が自らの意志で復興の方向性を定める事は新たな町のアイデンティティーの形成にもつながります。そうでなければ陸前高田市はこれから先、一つの自治体として継続する意味までも失いかねません。
関西に在住している私には陸前高田の町の再生と、そこに暮らす人達の平穏を遠くから祈り、見守ることしかできません。そしていつの日か多くの市民が「やっぱり、こごがいい」とつぶやける町の復活をただ願うばかりです。

通称「希望の架け橋」と呼ばれる陸前高田市を縦横に走る巨大ベルトコンベアー