読者つうしん
おたより•裁判傍聴記
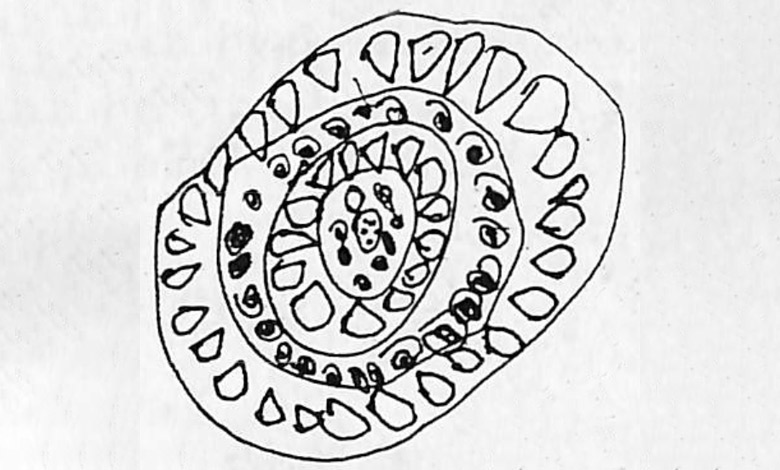
おたより
前略…原発社会のもたらす環境汚染も大きいけれど、何よりも人の心を汚染し、生命や心より大切なものがあろうはずないのに、どんどん悪くなる一方です。公庄さんの裁判も、結局、強い方(権力に近い方)に有利になってしまいクヤシイですね。
お金を多く得る仕事につく人や安定した収入を求める人は、自分の保身の為に何が大切な事であるかが見えていません。見えないようにする根源に学校の管理教育があります。公的学校は、人を育てるのでなく、人を飼育する所と思っています。その辺のところが、「ぐるーぷ•生命の管理はもうやめて」でも話していけるとよいのですがネ
さて、会費とニュース用封筒、少し同封します。
‘93.6.20 稲田多恵子
裁判傍聴記
(西宮) 石井布紀子
生まれてはじめて裁判というものに参与しました。私は以前から”人から裁かれた気になる” “人を裁く” “自分を裁く”ということに深い興味をもっていましたが、それらを考える時いつも”ひとり一人の主観”がかわることによって”生命の平等観”に対して何をどう認識すればよいかが難しくなることを感じていました。
今回地裁に出かけたことで、法の存在や中味の是非はともかくとして、法によって裁きについての判断を行う制度というものの面白さや大切さがあることを改めて、いえもしかしたら初めて実感しました。
高塚高校の事件は、これからの公教育の制度や教育にかかわる人材管理のあり方を見直し、少しでも子どもたちひとり一人の生命を基点とした教育のあり方に近ずくためにと、石田さんや神様が与えて下さったチャンスなのでしょう。
あまりに無力な私ですが、また機会があれば、お話しおきかせ下さい。

